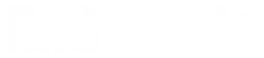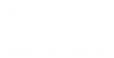コンパクトミキサーの使い方をマスターして快適なDTMライフを!
DTMで音楽制作をするにあたって、必要不可欠ではないものの、あるとなにかと便利なコンパクトミキサー。
今回の記事では、コンパクトミキサーを使用すると何ができるのか、また、どのように使えば良いのか、などに着目して解説していきます。
リハーサルスタジオなどに置かれているパワードタイプのPAミキサーの使用方法については以下の記事をご参照ください。
PAミキサーの基本的な使い方をマスターして快適なリハーサルを!
コンパクトミキサーにはエフェクト内臓のものや、入出力数が豊富なもの、オーディオインターフェース機能を持ったもの、など様々ありますが、今回は最もシンプルな6入力2出力のミキサーYAMAHA MG06を例に取ってご紹介していきます。
DAWの入力側に使用する方法
同時入力数を拡張する
サンプラーやサウンドパッド、シーケンサーなどを使用してリアルタイムレコーディングを行う場合、オーディオインターフェースの入力数が不足することがあります。
コンパクトミキサーを使用して、各楽器をステレオにまとめることで、オーディオインターフェースからみた同時入力チャンネル数を減らすことができ、いままで不可能だった同時録音が可能になります。
この場合、複数の楽器が同一のトラックに録音されてしまうので、事後編集を行いたい場合には、まとめても良いトラックのみをミキサーに立ち上げるようにしましょう。
パッチベイ的に使用する
通常、オーディオインターフェースの入力端子は背面にあることが多く、ラックマウントタイプのものでは、配線変更のたびに裏に回り、隙間からケーブルを抜き差ししなくてはなりません。
コンパクトミキサーの出力端子を常にオーディオインターフェースの任意の入力端子と接続しておき、録音したい楽器をミキサーに接続して録音することで配線変更の手間をかけることなく、入力する楽器を変更することが可能です。
また、雑多な変換ケーブルや延長ケーブルなどをコンパクトミキサーを中心に集約できるため、全体的な配線がスッキリするメリットもあります。
DAWの出力側に使用する方法

ここからは、オーディオインターフェースの出力をコンパクトミキサーに接続して使用する方法についてご紹介していきます。
3/4・5/6入力を使用する場合は、オーディオインターフェースからの出力レベルを-10dBに設定しましょう。
モニターコントローラー・セレクターとして使用する
オーディオインターフェースの出力レベルをモニタースピーカー、ヘッドホンで独立して決められない機種や、モニタースピーカーに音量調整機能が無い機種を使用している場合、コンパクトミキサーを使用することで、個別に任意の音量でモニタリングを行うことが可能になります。
また、複数の出力があるミキサーを使用することで、複数のモニター使用時にモニターセレクターとして使用することも可能です。
レコーティング時のCUEボックスとして使用する
通常、レコーティングスタジオでのレコーディングでは演奏者やボーカリストは手元のCUEボックスで自分のモニターを設定します。
DAWを使用して自宅環境で演奏者用のモニターを作る場合は、現在のMIXバランスを崩したり、別セッションを立ち上げなくてはなりません。
同一セッションでもDAWの出力SENDからパラ出しして、演奏者の手元に置いたコンパクトミキサーに接続することで、レコーディングスタジオ同様に演奏者が自分で快適なモニターを作ることが可能になります。
実際に私も簡易的なボーカル録音の際には、オーディオインターフェースの出力を、ボーカル+DSPベースのリバーブ(モノラル)、クリック(モノラル)、それ以外の2MIXと簡易的にパラレルアウトしてMG06に立ち上げています。
DSPミキサーアプリケーションを使用するよりもその場その場でアーティストが必要なモニターを自分で設定してくれるので、作業時間の短縮にも繋がっています。
DAWの入出力間に使用する
ここでは、オーディオインターフェースの出力をミキサーの入力に、ミキサーの出力をオーディオインターフェースの入力に、と言うように双方向で接続を行うパターンを紹介していきます。
DAWでの入出力アサインを間違えると、入力、出力間でループが発生してしまうため、注意しましょう。
コンパクトミキサーの内臓エフェクトを使用する
コンパクトミキサーに内臓エフェクトが搭載されている場合、DAWからのSEND/RETURN接続で内臓エフェクトを使用することが可能です。
リバーブ類はプラグインを使用することが多いと思うのですが、ミキサー内臓のリバーブがお気に入りの場合、積極的に利用しましょう。
DSPパワーの節約にも繋がります。
ミックスバッファとして使用する
ミックスバッファとは、DAW内部のデジタル段でMIXを完結させずにアナログ段でMIXを行うための簡易的なミキサーのことを指します。
デジタル段でのMIXでは、飽和感というか、空間に音が詰まっていっているのに混ざっていかないような印象を受けることが多々あります。
アナログモデリング系のプラグインなどを使用して倍音成分を付加することで解決することもあるのですが、全てがうまくいく訳ではありません。
アナログ回路では、入力信号を出力するまでの間に複数回の増幅回路を通ることで、特有の音楽的な歪みが発生します。
優秀なプラグインではこの回路の特性的な歪みもうまく再現しているのですが、どうせなら実際にアナログ回路を通した方が早い、といったところでコンパクトミキサーを使用してしまいましょう。
また、フルバンドEQが付いているミキサーを使用してミキサー上でMIXを行ってしまう方法もあります。
こちらも同一のアナログEQを通すことでサウンドの方向が揃い、一体感のあるMIXを作成することが可能です。
手順は簡単です。

INPUT1-6は既に録音されたトラックです。
これをオーディオインターフェースの出力Output1-6へと割り当てます。
この時SENDからではなく、メインの出力先をOutput1-6に設定してください。
INPUT1-6がDAWのメイン出力から出力されてしまうと位相やレイテンシーの問題で効果的に機能しません。
また、トラックをバラバラに出力アサインすることをパラアウト、マルチアウトなどと呼びます。
オーディオインターフェースのOutput端子1-6をコンパクトミキサーの入力端子に接続し、ミキサー上でEQやバランス調整などを行います。
実際のところ、全てノミナルレベルに設定しても、回路上のバッファアンプやサミングアンプを複数回通過するためにサウンドは大きく変わりますよ。
ミキサーのSTEREO出力をオーディオインターフェースのInput 7/8に接続し、DAWで空のオーディオトラックを作成し入力をInput7/8に設定します。
この時インプットモニター機能をONにしておくことで、非レコーディング中でもミキサーからの信号をDAW上でモニター可能です。
コンパクトミキサーに立ち上げたトラックのサウンドが決まったら、先ほどInput7/8を割り当てたトラックを録音状態にして、1曲通しで録音します。
これで、アナログ回路上でMIXしたトラックがDAWに再び取り込まれました。
ちなみに、なぜか今回はLogicを使用してみました。
使用しているDAWやオーディオインターフェースによっては出力端子間のレイテンシーの違い、遅延補正の適用範囲などの影響で元のトラックと時間軸が合わない可能性もあります。
その際には面倒ですが、波形を見ながら適宜修正しましょう。