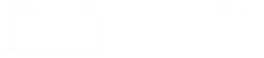ブライダル音響のプロが教える演出効果のテクニック
披露宴・二次会などで、プロが実践している、音楽の演出効果を解説してみましょう。
皆さんは、披露宴などに出席した時、思わず感動してしまったり、涙してしまった事はないでしょうか?
皆さんの、心を動かしてしまったもの。
その正体の一つが、音響効果の力なのです。
今回はシーン別に、プロのオペレーターが心がけているテクニックを解説していきます。
手紙 〜言葉に音楽を寄り添わせ一つにする〜

披露宴も終盤に差し掛かり、結びへ向かいます。
ご新婦さまが、ご両親に感謝の思いをお伝えする感動の場面です。
乾杯で作り上げた、今までのパーティーとは一変、セレモニーへと帰していきます。
厳かに、しっとりと、音響も変化させていくのですが、それが、取って付けたように成ってしまっては、台無しです。
時には逆効果になることも有ります。
皆さんにも経験はないでしょうか?
楽しくふざけ合っていた友達が、急に真顔になり真面目な話をしようとする、そこで沸き起こる爆笑を。
こう成らない為に、手紙への伏線を作っておきます。
歓談中に流す曲の中から、比較的静かな曲を手紙前に挟みます。
こうする事で、手紙への自然な流れが生まれるのです。
いよいよ手紙を促すコメントを司会者が語ります。
「日頃の感謝の気持ちをお手紙にしてお持ち頂きました」
ここでたっぷり間をとる場合も多いのです。
「新婦さま、お読みいただけますか?」あくまでも控えめなコメントです。
ここでの「間」は注目させる為でもなく、ましてや「エネルギー」をためる為でもありません。
動から静へ場面を展開されるために、必要な余白なのです。
この時、音楽は邪魔でしかありません。
司会者が作る「間」に無音で対応します。
そして、新婦様がいざ読み出そうとする少し前、その気持ちに寄り添うように、小さくBGMを加えます。
読み始められたら、さらにボリュームを下げ言葉の空間を作ります。
この時のBGMは「オルゴール」も多く選ばれます。
ご新婦さまの言葉を邪魔しない為に、インスト=オルゴールなのですが、時として、オルゴールの音は固く攻撃的になりがちです。
「ピアノ」や「ストリングスアレンジ」のものが音に丸みがあり、また、感情表現の幅も持っています。
ボリュームはかなり小さめに、煽りなどは必要ありません。
ご新婦さまに寄り添う事、それが重要なのです。
手紙を聞かれているお母様・お父様の気持ちそのものなのです。
読み終わられたら、BGMを元の音量に戻します。
変化はごく僅かです、音量が上がったと気付かれないかも知れません、
しかしそれこそが重要な事なのです。
音響が何をしているかを気付かせてしまうという事は、音響の存在を意識させてしまった事に成ります。
存在は気付かれずとも、ゲストの心は確実に動かされています。
花束贈呈 〜最大の感動は最大の冷静さで生まれる〜

手紙の感動の中、新郎新婦様は花束を手にご両親の元へ進まれます。
今にも走り寄って抱きしめたい、そんな気持ちでいらっしゃる事でしょう。
皆さんは「花束贈呈シーン」に対して渡す瞬間をイメージされる事と思います。
しかし、それ以上に重要なのは、実は歩き出しからご両親の前に着くまでのアプローチです。
音響はあくまで冷静に、花束の曲を流すタイミングを伺います。
この感動への序章は、乾杯やケーキの時ほど容易くは有りません。
盛り上がりへのプロセスは、少々突発的で有ったとしても、ゲストの心は付いてきます。
それが「感動」と成ると、見え透いた演出効果では気持ちは一気に冷めてしまいます。
曲を流すタイミングは司会者のコメントが肝となります。
「言葉では伝えきれない気持ちを花束に込めて、お進みいただきましょう」
このようなコメントの節目で「そっと」流します。
新郎新婦様が、ご両親の元へ近づくにつれ、さらに感動的な言葉が司会者から続きます。
BGMもそれに合わせて音量を少しずつ、少しずつ上げていきます。
そして、ご両親の前に着かれます。
もうご家族の感情は、はち切れんばかりに高まっている事でしょう。
この状況を作ってしえば、後はこちらの思い通りの演出が可能となるのです。
贈呈時にサビ出しをかける場合も良くあるパターンです。
その場合に注意したいのは、効果的な演出も、時として不自然な「演出過多」の印象に成ってしまうという事です。
何が起こっても感動させられる、この状況を作った事に自信あるのなら、これ見よがしな演出を、敢えて避ける判断も必要です。
ベストなのは「サビ出しをしなくともサビが流れること」です。
一見、不可能なように感じるかも知れません。
会場の広さも違えば、新郎新婦様の歩かれるスピードも違う、正確な計算式などありません。
現場の音響はどのように合わせるのか?
事前に音楽のサビまでの時間を確認し、会場の広さを確認します。
そして、「入場」や「お色直し入場」での、新郎新婦様の歩くスピードを覚えておくのです。
そこに「経験」や「感」が加われば、かなり近いところへタイミング合わせることが可能なのです。
必ずしも完璧に一致はしなくとも、感動できる状況が出来ていれば、大きな演出効果が生まれます。
この感動を与えられた時こそ、音響冥利に尽きる瞬間です。
退場 〜日常に戻っても尚感動を継続させる〜

両家代表の挨拶・新郎様の挨拶を終え披露宴のラストシーンです。
新郎新婦様が、会場を後にされ新たな旅立ちへと進まれます。
披露宴としては結びの意味があり、お二人にとってはスタートの意味があるこの時、どちらか一方の意味を強調した演出は、良くありません。
披露宴の結びなら、節目としてのきっかけと終わりを示す事が必要ですし、お二人のスタートなら、明るく世界が開ける印象を持たせたいところです。
そこで、このダブルミーニングを音量の変化で作ります。
司会者が結びの時をアナウンスします。
「本日は誠におめでとうございます!」
そこにBGMが鳴り響きます。
晴れやかな曲が、お二人の幸せな未来を予感させます。
ここで新たなスタートである事の印象を与えます。
新郎新婦様、ご両家ご両親様が順に退場口に進まれます。
ゲストの皆様は、その日一番の拍手で祝福しています。
そして「退場されて終了」それだけではいけません。
退場されてからの音響操作にこそ、退場曲の本当の意味があるのです。
いい音響は曲の消え際や、演出後の処理にも気をくばります。
扉が閉まったなら、少し時間を置いた後、ここでも少しずつ音量を下げ始めます。
司会者がコメントを言い出したからと言って、決して焦って急激に音量を下げては、ゲストは急に現実に引き戻され、それまでの感動が台無しです。
披露宴の終了、そして日常へ移行を和らげ、段階的に切り替える時間を作ります。