【PA入門】ステージモニタースピーカーの基礎知識
モニタスピーカーをステージに設置して音を出すというのは、特にライブのステージでは漠然とは分かっても実際どんなふうにするのか、慣れるまではイメージしにくいものです。
ここでは、あくまで初心者のために初歩的なことを書いていきましょう。
初歩的とは言っても卓の構造、特に信号のルーティング(どういうルートを通して音声信号を出力させるか) をよく理解する必要があります。
ステージにモニタを出す
マイクやらCDやらをミキサーにつないでスピーカーから音を出すというのはちょっと慣れれば誰にでもできます。
その一方で、ある意味でオモテ(客席向き)のスピーカー以上に気を遣うのが、モニタスピーカー。
オモテと同じ音をそのままステージに出すわけではありません。
カラオケ大会なんかはそれで済むけどね。
まずは簡単な仕込み図でイメージを。
奏者(ミュージシャン)の足下にコロガシを2発という想定です。
図の中に突然「AUX」という言葉が出てきました。
とりあえずは「AUX」という言葉だけ頭に入れた上で読み進めてください。

理解のために思い切りハショって描いたので、GEQだとか入れていません。
まず最初は、いきなりで悪いけどモニタはミキサーのAUXという系統の出力から出すんだということを知ってください。
モニタはAUXからと断言しましたが、実際はケースバイケースです。
後述しますがAUX出力がプリフェーダーだったらCDやMD等のオケをモニタに送るときに不便だし、カラオケ大会程度ならステレオ出力をそのままパラってもいいし。
ちょっとお高い卓についてるMATRIX出力をうまく使う方法もあります。
ライブではプリフェーダーのAUXから送ることがほとんどです。
じゃあそのAUXってなんじゃ?
って話なんだけど「Auxiliary」(オグジュアリィ)の略。
ホームオーディオに慣れた人なら見慣れた単語ではあるでしょう。
「補助」とかそんな意味らしいです。
要は、「メインアウト(ステレオ出力)みたいに用途は固めません。
好きに使って良い出力ですよ」という意味でミキサーに設けられた出力系統です。
でも現場で「オグジュアリィ」って呼ぶ人を見たことがありません。
私は「エーユーエックスと呼んでますが「オックス」と発する人も身近にいます。
そういうわけで、ステージにモニターを出すにはどう接続したら良いか、ミキサーの信号の流れを見ながら考えていきましょう。
プリフェーダーとポストフェーダー
下の図は、仮想的な4インプット/モノラル出力のミキサー。
2AUX仕様で、AUX1はプリフェーダー、AUX2はポストフェーダーという設計にしました。
ここでさらに「プリフェーダー」「ポストフェーダー」という新しい言葉が出てきました。
その言葉の意味も含めて、曲線で示した信号の流れを追いながら見ていこう。
メインアウトへの信号の流れを赤の点線で示してあるから、これを基準に見ていくと分かりやすいよ。
一応確認しておくと、メインアウトへの流れは赤の点線で見るとおり、【ゲイントリム >> トーンコントロール >> フェーダー >> マスターフェーダー】ここまでは大丈夫だよね。
プリフェーダー (Pre Fader)

ライブPAでのモニタへの送り出しはほとんどの場合「プリフェーダー」という仕組みのAUX系統を使います。
「プリ」とは、「プリアンプ」のプリ。
あるイベントに先立って何かするのを「プレ・イベント」と言うけど意味は一緒で「○○の前に」という意味。
つまり「プリフェーダー」とは、「フェーダーを通る前の信号を調整します」という意味です。
仮想ミキサーの仕様上、プリフェーダーのAUXは「AUX1」としました。
信号の流れは左側の図で青の実線で示した通り、ゲイントリムを通過した後で赤の点線と分岐し、別の系統へ走っています。
【ゲイントリム >> AUX1トリム >> AUX1マスタートリム】
つまり、トーンコントロールもフェーダーもすっ飛ばしてAUX出力をコントロールするんだ。
どういうことかと言うと、フェーダーを下げきっていようが上げきっていようが無関係に、出力が固定されるということです。
もっと言うと、簡単なミキサーをもう1台持ってきたような感じです。
上記の説明では「トーンコントロールもフェーダーもすっ飛ばして」と書いたけど、機種によってはトーンコントロールを通過するプリフェーダーというのもあるので気をつけて欲しい。
取扱説明書の巻末あたりに「ブロックダイアグラム」というのがあるはずだから、じっくり見てください。
その場合の信号の流れは、【ゲイントリム >> トーンコントロール >> AUX1トリム >> AUX1マスタートリム】となります。
ポストフェーダー (Post Fader)
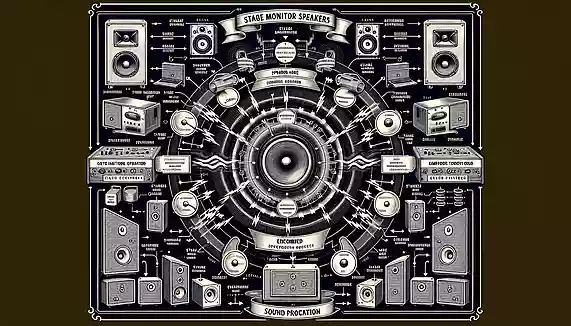 ついでに、エフェクターへの送りによく使われるポストフェーダーのことを書いてみます。
ついでに、エフェクターへの送りによく使われるポストフェーダーのことを書いてみます。
エフェクターのつなぎかたについてはこのページを見てください。
仮想ミキサーの仕様上、ポストフェーダーのAUXは「AUX2」としました。
この信号の流れを、右側の図に青の実線で示しました。
ポストってのは「次の」「後の」とかいう意味にとらえたらOK。
政治の世界で「ポスト中曽根は誰それ……」って言うあれ。
フェーダーはミキサーの一番手前にある縦のフェーダーのこと。
つまり、フェーダーを通った後の信号を調節するトリムという意味です。
信号の流れを見ての通り、操作対象のチャンネルの信号をメインアウトとは別に調節するんだけど、フェーダーを上げ下げすれば勝手に連動してAUX出力が大きくなったり小さくなったりします。
信号の流れは、赤の点線がフェーダーを通過したところから分岐し、別の系統に走っています。
【ゲイントリム >> トーンコントロール >> フェーダー >> AUX2トリム >> AUX2マスタートリム】
もう分かったよね。
この出力は、エフェクタへの送りに使うことが多いよ。
歌謡ショーなどでポストフェーダーAUXに余裕があれば、こいつを返し(モニタ)に使った方が便利なことも多いけど。
【実践】プリフェーダーAUXでモニターを出す
 じゃあさっそく実践してみよう。
じゃあさっそく実践してみよう。
ボーカル2名だけのライブ会場をシミュレートしてみました。
改めて理解して欲しいのは、赤の実線がメインアウトへの信号の流れ、青の実線がプリフェーダーであるAUX 1出力への信号の流れだということ。
こいうふうにプリフェーダーAUXでモニターを出しておけば、オモテの音に一切影響を与えないままモニターを調整することができます。
逆に、モニターに一切影響を与えないままオモテを調整できるということでもあります。
つまり、「客席で聴いた音のバランス」と「奏者が求めるモニターの音のバランス」をまったく独立に調整できるんです。
もしこれがオモテと連動しているポストフェーダー出力だったとしたら……「本番になったら、左の人の声がリハの時よりだいぶ大きいなあ。
ちょっと下げよう」となった時、左の人を下げてオモテのバランスを取ったら、同時にモニターに出ている左の人の声も一緒に下がってしまって、具合が悪い……ということになります。
最近の(2012年初頭現在)卓では、各チャンネルのAUXトリムに対して「プリフェーダーにするか、ポストフェーダーにするか」選ぶことができるスイッチがついていることが多くなってきました。
私はそのような卓を持っていませんが、持っているとしたら、歌謡ショーなどでCDをカラオケにする場合にCDのチャンネルをポストフェーダーに切り替えます。
こうすることで、オケをフェードアウトする時にはフェーダー操作に連動してモニターの音もフェードアウトできるからです。
逆にこのオケまでプリフェーダーにしていると、オモテの音はフェードアウトしているのに返し(モニタ)の音は活きたままCDを停止させるまで出っぱなしということになります。
じゃあプリ/ポストの切替ができない卓ではどうするか。
仕方ないからポストフェーダーのAUXから返したいけど、それはエフェクターで使い切ってる。
困った。
……やりようはありますが宿題にしておきます。
持っている卓の仕様と、現場の要求を正確に把握し、即座に頭の中で接続作業を終わらせることができたら一人前……かな?
?
余談:ライブはミュージシャンとPAの協同制作
特にライブの場合、リハ中は卓の前でじっとしていることは勧めません。
ある程度中音がまとまったと思ったら、自分でもステージに上がって奏者の耳に近いところで自分でもモニターの音を聴いてみましょう。
仕込みの段階でいったん聴いてみて、そこから先は間違いなくイメージができるというのなら別ですが、それでも結構イメージとずれていることがあります。
私はアラフォー世代(本ページ執筆時点)ですが、若いミュージシャンだと、「中音、大丈夫?」との私からの問いに、結構簡単に「あ、大丈夫です。
ありがとうございます」という返事が返ってきます。
でも念のためにステージに上がってみると、音圧が足りなかったり何だったりということがよくあります。
そんな時私は必ず次の手をミュージシャンに提案します。
「もうちょっと返し全体にローを足した方が、やってる感が出るんじゃない?」「あーさっきハウった時、削りすぎちゃったね。
余裕ありすぎなくらいに削っちゃったから、いったん少し戻そうか?」などなど。
ライブは、ミュージシャンの出す声と音を単に客席に送るだけではありません。
ミュージシャンとのコミュニケーションの中で一緒に創っていくものです。
そういう意味で、普段から打ち上げには極力同席する、リハ中の休憩なら一緒にタバコでも吸ってみる(コーヒーでもいい)、そんな付き合いができているとお互いあまり遠慮せずに音への注文を出したり受けたりできます。
もちろん、コミュニケーションの相手がマネージャしかいない時もあるけど、その時はその時。
マネージャは奏者・歌い手を知り尽くしていますから、できるだけ多くの情報を引き出しましょう。


