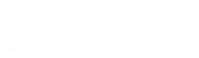頂-ITADAKI-主催者小野晃義さんインタビュー
2017年6月3日、4日におこなわれた野外フェス、頂-ITADAKI-の主催者である小野晃義さんに、頂-ITADAKI-に出店している父の店ONE BLOODで関わるスタッフ、ダギリがインタビューをさせていただきました。
何年もかけて仕掛けをばらまく
ダ:今回インタビューの時間を作っていただきありがとうございます。
それではよろしくお願いします。
まず企画自体の流れとか、フェス当日までの準備期間なんですが、いつ頃から取り組まれているんですか?
やっぱり1年がかりでやっておられるんですか?
小:いや、もう1年がかりというよりも何年もかけてやってるというか。
ダ:何年後、何年後というのを事前にという感じでしょうか。
今も現時点で来年とか再来年の企画とかもされいるってことですかね?
小:ある意味そうだね。
やっぱり、どこでどんな音楽と出会ったりどんな人と出会ったりとかで、どこで繋がるかわからないからね。
ちょっと一見無駄に見えることもずっとやってるというか。
例えばブッキングだったりしたら、うちでは早くて1年前とかかな。
ダ:そうなんですね。
では今やってる今後の準備とか、他にはどういったことをされてたりするんですか?
小:まあ色々仕掛けをばらまいているというか。
ダ:頂ってフェスの中でも色々特殊な感じがするというか、他のフェスに比べて色んなことをされてますよね。
例えばでいいので、新しい企画だったりとか今の現時点で教えていただけることとかってありますか?
小:まぁ一応今年で10年なんで、もし来年もあるとしたら、いい意味でリフレッシュして新しい形で提案できたらいいなって思ってはいるけどね。
向こうがいいよって言うまで続けようかな
ダ:LOVE FOR THE FUTUER(ラブ・フォー・ザ・フューチャー)に関して色々サイトとかでも発表してるんですけど、元々どういった経緯ですることになったんですか?
小:本当はねっていうのはおかしいけど、最初は子どもたちがいっぱい来て欲しいっていうのと、その子どもたちのために子どもを舞台にあげようとかそういうことから始まって、そしたらいきなり地震がきちゃって。
それでそれもやりつつ、なんかできることないかなって思った時に、東北に対してとか被災者に対してなんか……。
かわいそうな子どもがいっぱいいるから、なんかできないかなって思って、今もそのままずっと続けてるんだけど。
ダ:では東北の復興支援が企画の重きになっているという感じでしょうか。
小:今なってるね。
それもたまたま仲良くなった人が、今現在一生懸命やってるから俺たちもその人たちに引っ張られて協力しているというか。
やっぱね、あれって終わっていくもんだったり、徐々にみんな段階があってスタンスがあるんだと思うんだよね。
ダ:正直な所、年数が経つにつれて忘れていくということもありますもんね。
小:そうだね。
ダ:まあ、こう言ったらなんですけど。
「頂だけは忘れない」というかそういうふうに続けるという気持ちがあってという感じなんですかね。
小:明日は我が身だしね。
静岡なんて特に。
ダ:静岡も東海地震が来るって何年も言われてますしね。
小:そうだね。
東北にいるそういうおばさんに会ったりそういうことを繰り返していると、やっぱり情というか気持ちもすごい入っているし。
その人たちが普通の生活ができるようになるまではやっていこうかなって。
ダ:続けるのは本当に難しいことだし、素晴らしいことだと思います。
小:向こうがいいよって言うまで続けようかなっていうスタンスでやってるんだけど。
ダ:他にもおこなっていることといえば、廃油の回収や募金とかされたりしていますよね。
現物でシェアしていることもあったりするんでしょうか。
小:いや現物というよりも、向こうの人たちにアクリルたわしを作ってもらったり。
それを作るのにもお金がかかるから、そうなるために俺たちが金銭的支援をしているというか。
ダ:なるほどなるほど。
小:なんか売り物とかそういうものも、頂としては利益を取らずにLOVE FOR THE FUTUERに関したものの全ての利益は向こうに渡すという気持ちでやっていて。
スタッフもみんなも集まってるし、ずっと続けてくれてるんで。
そういう形で支援してるんだけど。
ダ:そうなんですね。
ミュージシャンよりなにより、スタッフが一番大事
ダ:イベントとして色んなスタッフさんがいると思うんですけど、特にボランティアスタッフのことをお聞きしたいのですが。
スタッフをボランティアって形で補ったりしているっていうのもあるじゃないですか?
そういう理念であったりとか、当日のスタッフの動きとか色々お話聞かせ願いたいんですが。
小:まぁいくつかのポジションに分かれていて、わかりやすくいうと10ぐらいかな?
駐車場の整理だったり入場ゲートだったり、頂だったらリユースカップを洗ったり、ゴミを拾ったり。
だからそういう10個ぐらいのグループに分かれていて、各リーダーに古いボランティアスタッフがいてそういう人たちが先頭になってずっと続けていってくれてるんだけど。
でもまぁ6割ぐらいは同じ人かな。
頂のボランティアは毎年ずっと。
ダ:去年に続いてという、リピーターが多いってことですね。
小:そうだね、10年ずっと来てくれてる人もいっぱいいるし。
ダ:繋がりが強いという感じですね。
小:繋がりのみでやってる感じだよね。
LOVE FOR THE FUTUERもそうだし、ミュージシャンの人たちもなんやかんやで繋がった人たちで、なんかかんやでこう続いてる人たちを大事に思ってるかな。
ダ:だいたいボランティアスタッフの方々っていうのは、いつ頃から動き出されるんですか?
小:んーとね、リーダーが半年ぐらい前かな。
例えば、今年が終わりました、そしたらそのあと結構みんなで考えるんだよね。
あれはこうだっだ、来年はこうしようとか。
それで一旦まとめてから少しブレイクして、半年前ぐらいに集まって年末ぐらいかな頂の場合は。
6月ぐらいにやるから12月ぐらいに集まって、もっかいそこを復習して今年はこうやっていこう、去年とはここをこう変えてここに力を入れようみたいな。
ダ:半年前からの動きっていうのを、その辺からずっとやっていく感じなんですかね?
小:まぁ飲み仲間だったり音楽仲間だったりっていうのが多いし、普段も付き合ってるからその時だけじゃなくて普段も繋がってるかな。
ボランティアスタッフとか誕生日に全部メッセージしてると思うし。
やっぱそこだけでやってたらここまでこれないよね。
ダ:やっぱり繋がりというのを大事に大事にって感じじゃないと続いていかないですもんね。
小:そうそう。
やっぱりみんな子ども生まれて来なくなったりさ、転勤なったりとかさ、仕事がどうこうとか色々あるじゃん。
だから全員が来れるわけじゃないから。
そういうのを続けていくと、2年休んだけどまた来てくれたりとか。
そうやって続いてるかな。
うち、どこよりも仲良くやってると思うよ。
ボランティアスタッフとかが大事にされてるって思ってくれないと、なんか俺たち利用されてるなぁって思われたら続かないし。
ダ:そうですよね、そんな風に思われてるってなったら手伝う気持ちもなくなりますしね。
小:もちろんそんな気持ちさらさらないし、大事にしようと思ってる。
ミュージシャンよりなにより、スタッフが一番大事。
ダ:6割ぐらいは継続しているのはお話からよくわかるんですけど、新しいスタッフさんとかもやっぱり応募とかは多いんですか?
小:来るね。
18歳とか20歳とか、若い子とかもいっぱい来るし。
それがすごいいいと思ってて。
やっぱり新しい人も来ないと、ね。
盛り上がらないし。
来てわかってる人たちがいて、みんなそこに持っていってくれるというか。
そういう感じかな。
ダ:そういう所でいえば、今年から来るとか来年から来るとか。
頂に参加したいっていうのであれば、応募方法とかHPにありますよね。
そういう方は一週間前ぐらいから動き出すんですか?
小:ボランティア?
ダ:そうです。
小:最長で8日ぐらい前からやり出すから、そこからくるスタッフもいるし。
そこから徐々に徐々に集まってくる感じかな。
ダ:だいたい8日ぐらい前から設営とかやりだしますもんね。
小:それこそ僕らは駐車場もないところからキャンプ場のライン引くとことか色々やってるけど。
そういう所からみんなで一斉にスタートしてって感じかな。
ある意味チューニングなんだよ、本番までの。
別にもっとちゃんとやればちゃんとできちゃうんだけど、それをやりながらどんどん仲間が増えていって、やってる感が出てくるというか。
準備ができてくるというか。
いきなりできないじゃん、ね。
ダ:普段は聞けないような珍しいお話たくさんありがとうございます。
それでは次の内容なんですけれど。
ここが他のフェスとは違うとか、頂のウリみたいな所ってどんな所なんでしょうか。
小:サービス精神だと思うよ。
来てくれる人は色んなフェス、パーティがある中で選んできてくれてるわけだし、時間作ってお金払ってきてくれてるっていうのは本当うれしいし。
その人たちを喜ばそうっていう気持ちと迎え入れる気持ちで迎えるっていうのがやっぱ、なんていうのかな。
金払って集めたスタッフじゃ、あぁはならないっていうね。
やっぱ金とかじゃなくてハートでやってくれる人が本当たくさんいて、そういう所に影響されて俺たちもそうなってるんじゃないかなって。
そこは絶対的に自信はある。
ダ:スタッフさんの絆の強さが一番ってことですね。
99.9%じゃなくて100%バイオディーゼルだから
ダ:あとエコに関してなんですが。
廃油であったりとか食器であったりとか、全てリユースできるようになっているわけですが、そういうことを始めた経緯ってとか、何がきっかけで始められたんでしょうか。
小:なんだろうね。
最初は頂の前に浜石祭りっていうのをやったりしてたんだけど、そのころからバイオディーゼル発電してる人とかそういう人がいて、そういう車に乗ってる人とか普通に興味があったから自然に始めたというか。
あえて意識させようと思って、浜石も頂の1回目もバイオディーゼルでやったんだけど、お客さんがいまいちピンときてなくてさ。
だったらこれ、持って来てもらったほうがリアルなんじゃない?
って思ってさ。
そっからテレビ番組とかテレビCM入れたりして、どうやって作るんだとかそのためにみんな持ってきてくれてということをやりだして、結果みんなが持ってきてくれるようになって。
それですごいリアルになってきたんだと思うんだよね。
自分たちの持ってきた油が発電されてフェスがおこなわれているって。
ダ:自分たちの力でフェスを作ってるっていう意識が芽生えたということですね。
小:そうだね。
自分たちの持ってきた油で音がなってそのバイブスを持って帰るみたいな循環。
それがこういい感じでできてるんじゃないかなって。
ダ:そういう廃油回収であったりとかという部分でお客さんに求めるようなことがあることによって、さらにつながりが強くなっていくという感じですね。
小:やっぱりすごいうれしいしこういうのって。
まあステッカーあげたりはするんだけど、別に持ってきたからってその程度でお金になるわけでもないしさ。
でもそうやって俺たちの発信を真面目に素直に受けて、一緒にやろうって持ってきてくれる人がいるとこっちも燃えるよね。
中途半端できねぇなぁって。
今トイレから電灯から、一切中部電力から買ってないから。
99.9%じゃなくて100%バイオディーゼルだから。
これはうちだけだね、あえて全部電気切り替えてやってるから。
これは完全なただのメッセージだから。
効率で考えたらめちゃ悪いけど、そこは伝わるって信じてやってる。
実はこうなんだっていうテーマがすごい大事だと思ってて
ダ:出店ではお肉を使わないってことだったりとか、そういうこだわりもあったりすると思うんですけども。
その肉を使わないっていうのは、やっぱりエコの部分とか考えてらっしゃるんですか?
小:まぁこれ裏テーマでさ。
俺言葉にはしてないんだけど、単純に俺がベジタリアンだっていうのと、そういうミュージシャンが多かったんだよ参加してくれる人も。
そうするとどっちかに合わせなきゃいけなくてさ。
肉食う人は食わない人に合わせられるけど、食わない人は食う人に合わせられないしさ。
それでやってみて3年ぐらいたった時かな。
みんなで話し合って両方あったほうがいいんじゃない?
ってなったんだけど、これはこれでひとつのスタイルで1年に1回だし楽しもうよみたいな感じで。
ダ:逆に僕はONE BLOODで出店してやってて、肉使えないっていうのが難しいって時期もあったんですね。
でも逆に使わないことによって新しい商品というか、個性的なものができたりとかそういうこともあったりして。
すごい、なんかこう素晴らしいこだわりができるようになってといいいますか。
小:単純に俺は自分のパーティで殺生したくない。
うん、それだけなんだよね。
なんか生意気言ってるかもしれないけど。
なんか10000人も集まったらさ、肉だって魚だってたくさんの命を頂くわけじゃん。
そん時にリスペクトなく、なんとなく食べうちゃうのが嫌で、みんなにいただきますって言えっていうのも、すげぇ難しいなって思うし。
まぁ、ある意味俺の自己満足かもしれないけど。
でもそれを仲間のみんなが認めてくれてて。
お客は色々あるんだと思うんだけど、まぁ別に。
嫌だったら来るなぐらいの感じで。
それが頂スタイルになっちゃったかな。
でも俺そういうレストランとかもやってたりしてるけど、表現がやっぱ難しいんだよね。
頂の場合、俺は言葉とかなんか文字にしたりは一切してないわけ。
でも実はそうだっていう。
なんかそういう実はこうなんだっていうテーマがすごい大事だと思ってて。
ダ:正直こういうことを知らないっていうか、実は肉がないっていうのを知らないお客さんも結構来ると思うんですけど。
小:知らないで終わっちゃうっていう人もいるんだよ。
そうだったんだっていう。
それでも良いと思ってるし。
ダ:でも逆に知らないで終わるってうことはそれだけでも全然生きていけるというかそういう道もありえるということですもんね。
小:そうそうそうそう。
ダ:そういうことも考えることもできますもんね。
さりげなくやってるっていうぐらいのがちょうどいいというか
小:ほらレゲエ大好きだし。
インディアンの音楽とかいっぱい聴いてきたし。
やっぱり彼らがどうやって自然をリスペクトして、どういう思いでやってるかっていうのをすごい僕なりに感じててそういうとこ取り入れたいなって。
まあ宗教的に受け取られたりするのは嫌なんだよ。
そういう気は全くなくて、普通にシンプルに。
ダ:やっぱりレゲエとかインディアンとかの自然を大事にするっていう気持ちが非常に強いから、エコだったりとか肉だったりとかっていう頂の色というのが出ているっていうわけなんですね。
小:でもまぁ結構悪そうでさ、そういう感じじゃないでしょ。
パッと見た感じじゃ(笑)。
ダ:まぁまぁ(笑)。
小:ラインナップとか見てるとさ、そこがいいと思ってるんだよ。
そこをなんか「やってまっせ」みたいにあるのはダセーなって。
さりげなくやってるっていうぐらいのがちょうどいいというか、うん。
ダ:わりと出演してるアーティストさんとかレゲエの方たちも、他のフェスと比べると多いですもんね。
小:単純に俺が好きなんだ(笑)。
でもやっぱその繋がりはおっきいし、みんな繋がってるし。
ダ:まぁでも、僕もそこまでレゲエに対して詳しくないというか。
小:そうなの!?
お父さんあんなに詳しいのに(笑)
ダ:そうなんですよね。
まぁそこまで強制させられたりはしてないんで(笑)
それに僕自身も割とロックの方に落ち着いてるというのもあるんで。
でも、そういう僕から言わしてもらうというのもあれなんですが。
レゲエってやっぱ「愛を題材とした」音楽やなっていう意識はあるんです。
そういうレゲエを素材にするというか、レゲエが好きな小野さんとか頂スタッフだったりとかが携わっているから、絆というものや愛のあるフェスなんだなって感じますね。
小:俺、ボブ・マーリーが好きなんだよね。
あの人の歌とか聴いてなるほどなって思うこといっぱいあったし、あの人のライフスタイルとかすごい影響されているというか。
流行りもんは色々変わっていくけど、なんかその肝心なことはずっと残っていくっていうかって感じかなぁ。
ダ:そうですね。
音楽の中のてっぺんを連れてきたらすごいことになる
ダ:それから、フェスの名前なんですが、なぜ「頂」って名前になったんですか?
小:あれが一番時間かかったんだよ、考えるの。
まず頂やる時に考えたのが、どういうジャンルの音楽をやるとか。
俺、元々レゲエのフェスティバルみたいなのばっかりやってたから。
ただライブハウスやってた手前本当ジャンルレスに音楽聴いてて、最初苦手だったジャンルとかも慣れてきたらこういう所格好いいなとか。
この気持ちちょっとわかるっていうのとか、そういうのが出てきて。
もっと広く考えた時に、もうオールジャンルいこうってなったのね、まず。
そのオールジャンル、各ジャンルのてっぺん連れてこようみたいな。
ダ:そのてっぺんの……
小:そう、そう。
そしたらすごいピークのある、すごいてっぺんのあるイベントになるんじゃないかなって。
ダ:わりと頂っていうと、静岡だから富士山っていう意味とかあるんじゃないかとか。
小:いや、もう全然関係ないよね(笑)
どっちかというと音楽の中のてっぺんを連れてきたらすごいことになるみたいな。
レゲエだったらこの人、ジャズだったらこの人とか。
それを俺たちの偏見と好みで決めてるというか。
ダ:そういう感じなんですね。
小:漢字がいいなって思ってたの。
英語は嫌だなっていう。
横文字は嫌でなんとか日本語で作りたいなって。
ダ:一文字だけで頂(いただき)っていう、わかりやすさもありますしね。
小:本当は頂日本平(にほんだいら)大音楽祭だったの。
でもこれ本当は3回目ぐらいで、「頂日本平(だいら)大芸術祭」にしようと最初思ってたぐらいなのね。
なんか漢字の並びが格好いいなって。
しぶいなぁって。
ダ:音楽だけにとらわれず、ライブペイントとか芸術的な部分っていうのが頂にはありますもんね。
小:やっぱいいものはぐっとくるしね。
音楽だろうが絵だろうが写真だろうが。
うん、なんかやっぱそういうのやってる人がいるとオッって思わされるというか、そういう感覚を大事にしてるというかね。
そうすると子どもとかがね、右も左もわかんない小さい子どもとかもね、口ぽっかりあけて影響されたりね、それすごいと思うよね。
もし俺がこのイベント小さい時に来てたら人生変わったなっていう。
なかったしさそんなの。
だからたくさん子どもに来て欲しいな。
そういういいものと触れ合うとなんか良くなるっていうのが、なんか実証してるし。
ダ:割と頂ってこういうブースがあったりだとか、こういう子ども向けというかそういう部分結構多いですよね。
小:そうだね。
やっぱり長いことライブハウスやってたからね。
お客さんが結婚したり、子どもできたりすると来なくなるんだよ。
やっぱライブハウスは来にくいじゃん。
空気も悪いし、音もうるさいしさ。
外でやりたいんだけどそこでチケットのお金とるとさ、行きづらくなるというか。
聴いてないじゃん子どもなんか。
別に何聴きたいってわけじゃないから、だったらもうタダで入れちまえみたいな。
その子たちが大きくなるとまた面白いしさ。
俺の子どもも4年生だったんだけど、もう大学1年生になって今年は7人友達連れてスタッフで参加するし。
そういうのが素晴らしいなって思って。
子どもだったやつらがだんだん大人になってスタッフになってお客になってというか。
ダ:子どもが成長していくという中で、自分が楽しかった思い出というのを自分の子どもに教えていくっていうね。
小:そうだね、そういうのあるねー。
子どもいっぱいいると大人っていい雰囲気になるんだよ。
大人ばっかで呑んだくれてばっかいると、やからになったりするんだよね。
でも自分の子どもがいたり知り合いの子どもがいたりすると、若干格好つけようというか(笑)。
それ大事でさ、すごいセキュリティにもなるし。
子ども可愛いしね。
でもまあ子ども向けの音楽はやろうとは一切思ってないけどね。
ダ:そうですよね。
ラインナップ見ても子ども向けなのは全然ないですもんね(笑)。
むしろ、僕よりちょっと上の世代の人たちが聴いてる感じの人たちが多いですよね。
小:確かに今年とかちょっとまぁ、アダルトになっちゃったなぁって思ってるけど。
俺的には頑張って若くしてるんだけどね(笑)。
ダ:最近のラインナップはアーティストさんが若者でも楽しめるというか、今の売れ筋のというかそういう方も多いなってイメージもありますね。
小:なんか正直アンダーグラウンドでずっとやってきてるから、売れてるだけで気に入らないとかなんかあるんだよね(笑)。
でもそういうのを全部とっぱらって、売れてるとか売れてないとかそういうのじゃなくて、ちゃんとみんながいいなっていうような音楽をさ。
ちゃんと聴いてみると意外に格好いいなって思ったりとか。
で、そういう変に影響されないでちゃんと聴いてみていいなって思う音楽は、若かろうが売れてなかろうがラインナップしようと思ってる。
ずっとそう思ってやってきてるね。
ダ:先ほども言っていたのですが、頂のオールラウンドさというか全ての頂点を目指すっていうところにつながっているんですね。
小:そうだね。
いい音楽とかが流れてたりしたら俺だったらもう最高だなって思うし
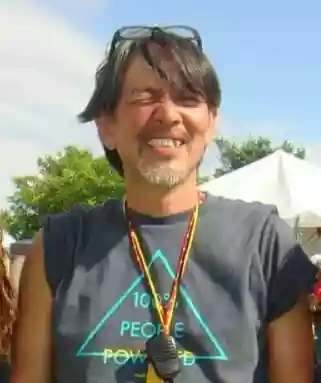 ダ:子ども向けにというか、その辺のお話の続きになるんですが。
ダ:子ども向けにというか、その辺のお話の続きになるんですが。
ひとつの特徴として、キャンプっていうのがあるじゃないですか。
あれはなぜやるようになったんですかね?
小:いや、まぁ単純に吉田って田舎だからね。
泊まるホテルとか少ないんだよ。
吉田でやる=泊まる場所がない。
そしたら2日間もやるとするとお客さんでもう溢れちゃうから。
キャンプができないとイベントができないっていうさ、大前提でいったというか。
ダ:でも逆にキャンプとかがあったりすると、結構子ども向けにはなっているというか。
小:そうだね。
ダ:音楽フェスってなるとどこの誰かもわからない人がライブやってるより、キャンプというイベントがあることによって子どもも楽しめるという感じですよね。
小:そうだね、キャンプだけでも楽しいじゃん、ちょっと出てったらいい音楽とかが流れてたりしたら俺だったらもう最高だなって思うし。
ダ:キャンプの方だけの音楽とかもありますよね。
小:あるね。
ダ:あれ結構お得ですよね。
小:昔だったら夜中でもドンドンやるんだろうけど、もう俺たちも歳だし。
子どももいっぱいいるし、寝かせにかかろうみたいな。
そこはそういう感じにセッティングしてあるね、ムーンステージは。
もう各アーティストに出演依頼するときは、「ここは寝かせるステージです」「決してアゲないでくれ、寝かせてくれ」っていう感じで。
でもそういうのも面白いみたい、ミュージシャンは。
ダ:あんまりないですよね。
アーティストなんか盛り上げてなんぼみたいな所あるじゃないですか。
例えば、自分の音楽がBGMとしてというかそういうふうに使うっていう。
小:ある意味そうだね。
みんな椅子とか持ってきて寝てるからね、ステージの前で。
ある意味失礼だと思うんだけどね。
それはミュージシャンにもいってるんだけど、頂のムーンステージにそれがお客さんの最高の反応なんだっていう。
去年ゴンチチとかががやってた時なんか、全員寝てたからね。
ばっちりだなって。
そういうコンセプトも面白んじゃないかなって。
朝早いし、1日長いし。
ダ:疲れますしね、1日2日通したらね。
小:疲れるよー、そういうのいいと思うよ。
伝わり方とか入ってき方が変わる
ダ:あともうひとつ特徴的なことと言えば、キャンドルタイムなんですが。
キャンドルタイムのこだわりとかって何かあったりすんですか?
それをしようとなった経緯とか。
小:それは1つ、キャンドル職人のちろりろうそくっていう友達がいてその人のろうそくが素晴らしいっていうか。
もう初めて見た時からすごい感動して、うわこの人と一緒にステージやりたいなって思って。
まあ昔からよくやってた時は、キャンドルと照明をうまく使ってなんかいい感じでやってたんだけど。
やっぱりさっきの100%バイオディーゼルの話じゃないけど、中途半端にやると伝わんないんじゃない?
みたいな。
100%キャンドルの灯りオンリーって、やったらすごいんじゃないかなって思って。
トイレまで消すからね全部。
ダ:そうですねえ。
小:まあある意味クレームも出るけど、それが頂スタイルだというかあの感じはちょっと自信あるよ、うん。
なかなかああはならないっていうか、やっぱりずっと10年続けてきてあの雰囲気を出してるっていうか
ダ:正直そうですよね。
頂だから許されるというか、そういう部分も結構多いのかなって感じがするんですけど。
まあ何も知らない人が来たら真っ暗じゃないか!
とか見えにくい!
だとか。
キャンドルタイムに限らず、それこそ頂じゃないとありえないというのは結構感じるなというのはあります。
10年も続けてきてスタイルも確立してきて、お客さんにしても理解してきたというか全員でつながっているのかなというのを感じますね。
小:ありがとう。
でもね1回目の方がみんな納得してたよ、なるほどねみたいな。
まあ1500人くらいしかいなかったけど、1回目とか。
でも逆に知ってるお客さんも多いし、ほとんど仲間が来てるみたいな。
ダ:知り合いの知り合いみたいな感じで始まっていく所があったってことですよね。
小:こうやってやるぞこうやってやるぞってみんなに言って、やってく時にまあ直接言えるから俺も凄い伝わってるなみたいな。
そういうのがあって段々段々増えてきてあのデカさでライブになっているというか。
なかなかないと思うよ、色々見たけど。
似たようなのはあるけどちょっと違う。
その自信はめちゃめちゃあるから。
ダ:結構こだわりの強さっていうか中途半端じゃないところを凄い感じますね。
小:やっぱ音楽をやってきてさ、音楽ってすげえいい音と雰囲気、これがセットされないと、音だけよくてもさあ。
例えば太陽ギラギラで40度ある時に、まったりした音楽聴いてもまったりできないじゃん。
やっぱその気温でその感じで、そういう照明でそうなるから。
そういう雰囲気になるというか。
伝わり方とか入ってき方が変わるというかさ。
例えばクラブだったら真っ暗くて目閉じてるような感じで音だけが入ってくるから、耳が研ぎ澄まされるみたいなそういう感じだよね。
セッティングが全てだと思う。
ダ:その空間作りっていうのはキャンドルタイムしかり、あのムーンステージしかり、そういうのをこだわっているなって。
小:あの2つは肝だと思うよ、メインだから頂の。
でも正直に俺全部自信あるよ
ダ:色々頂の特徴というのはあると思うんですけど、今年の特徴みたいな今年は違うぞみたいなものってあります?
小:今年はね、いろんな思いが詰まってるね。
昔からの仲のいいバンド連れてきたり、ロバート・グラスパーみたいな憧れのバンドが来てくれたり。
こういろんなとこにいろんな話をしながら準備してきたことが少し形になったかなと思ってるし。
全部が全部は全然なってないけど、8割方は形になってないけどその2割くらいが形になったから多分お客さんも昔の友達もいっぱいくると思うし。
10年間の思いを歴史を全部感じるようなショーにしたいなと。
土曜日の朝一番から日曜日の終わりまでDJ気分で本気で繋げてるから全部。
絶対この展開いいぞって思ってやってるし、それをわかってくれたらグッとくるんじゃないかなと思ってて、それを1人でも多くのお客さんに感じてほしいなって。
もう自己満足だけどねある意味。
その自信はあるかな。
ダ:今年注目のアーティストとかありますか?
小:それは難しいなあー、俺が色々言うのは。
ダ:アーティストがこの場にいる状況で言うのもなんですけどね(笑)。
小:でも正直に俺全部自信あるよ、うん。
もう全員嫌って言うほど聴いたから。
嫌って言うほど聴いて嫌って言うほど考えて、オファー出してるし。
あえて誰なんだろうな、ロバート・グラスパーにしとこうかな無難なところで。
まあ、ロバート・グラスパーは頂としてはおしゃれすぎると思うんだけど。
ブラックミュージック大好きな僕らとしてはもし叶うならやってみたかったアーティストっていうか。
ダ:わりとこう、ブッキングにも思い入れが強かったというか。
小:そうだね、もちろん決まると思ってないしね。
グラスパーとか決まっちゃったよみたいな感じだよね。
まあ、あとダブセン(DUBSENSEMANIA)、犬式かな。
ダ:やっぱそうですね。
これは、復活するという所でしょうか。
小:まあ俺はここまでしていいものなのか、他のアーティストもいっぱいいるからいろんな思いがあるけど個人的にはね。
やっぱ復活とかってさ、ドラマがあるじゃん。
昔で言ったらPLASTICSが復活したりGOMAが復活したり、やっぱそういう舞台に選んでもらえるっていうのはうれしいし、こっちも気合いも入るし。
特別だからさ、復活する場所っていうのは。
そこを俺たちがセッティングするっていうのは光栄だよね。
ハマリどころ満載です
ダ:お客さんに見ていただきたいところというか、見どころというか。
ここをこうわかってもらいたいっていうことはあったりしますか?
さっきもちょっと出たんですけれども、流れを感じていただきたいというかというのがあったんですけど、こういうお客さんにっていうのあるのでしょうか?
小:俺ぶっちゃけね、何も考えてない人もハメたい。
わかってるやつはわかってるから。
好きなやつとかずっとそれ考えて来てるから。
でもいい意味でよくわかんないけど来たとか、この人を見たくて来たとか目的があってくるんだけど違うことにやられたりとか。
そうやって音楽ってハマってくじゃん。
だからどこでハマるかわかんないぞっていう
トラップはいっぱい仕掛けてあるつもりだけどね。
ハマリどころ満載ですよ、うん。
ダ:では、最後になるんですけど。
今回10週年になるイベントに対しての意気込みみたいなものってありますか?
小:いつもと変わらず自然体で肩の力抜いてやることかな。
本番まではがっちりいくけど、本番はもうあんまり気合い入れすぎずに。
ダ:ありのままの自分ということでしょうか?
小:そうだね、なるようになると思うし。
何かが起きた時に受け入れられる器というか、そういう感じになっていればいいなぁと思ってね。
ハプニング大いに大歓迎というか(笑)。
ダ:逆にそのほうがハプニングを楽しめるような。
小:それがライブだからね。
まかせてよ、バッチリよ。
ダ:今回はバタバタとお忙しい時に、貴重なお話をたくさんしていただきありがとうございました。
小:いえこちらこそ。