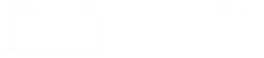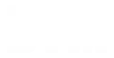【DTM初心者のための】Logic Pro(ロジックプロ)の使い方。MIDI打ち込み〜楽器の選択
Apple社が製造、販売している高機能DAW「Logic ProX」の操作や、覚えておくと便利なコマンドなど順を追ってわかりやすく説明させて頂いています。
第2回となる今回は、前回のインストール編の続きとして、DTMの基本となるピアノロール画面でのMIDI打ち込みの基本を紹介させて頂きます。
鳴らしたい楽器を探す(楽器の選択)
Logicには購入時点で多くの音源が付属しています。
とてもありがたいことですが、初めてDAWに触れる方は漏れなく「鳴らしたい音(楽器)がどの音源にあるのかわからない」と思うことでしょう
しかしLogicは気が利きます。
全ての音源のプリセットを網羅し、そこから欲しい音を選ぶ為のライブラリが存在します。
[Y]を押します。
画面左端、インスペクタの隣に出現した画面が「ライブラリ」です。

トラックに何も音源が読み込まれていない状況で、「Bass」「Drum Kit」「Orchestral」等、それぞれの項目をクリックすれば、それらのプリセットを持つ音源と、そのパッチを自動的に読み込んでくれるという素晴らしい機能です。
トラックに既に音源を読み込んでいる場合でも、[Shift]を押しながらインストゥルメントスロットをクリックする(音源名が白枠で囲まれる)と、その音源内のプリセットだけを一覧表示してくれます。

用語、コマンドのおさらい
MIDIノート
MIDI音源を再生する為の音符のようなもの。
これを入力する事を「打ち込む」と言う。
MIDI音源のみで完結した音楽を「打ち込み系」というのはここから。
参考:MIDIが良く分かる。
バンドマンのためのDTMの基礎知識
リージョン
MIDIノートや音声信号の入れ物となるもの。
ツールキー
MIDI打ち込みをする時、リージョンを切り離したい時、またはくっつけたい時などそれぞれの作業にあった道具を選択する際に使用する。
[T]を押す事で開く。
[T→P]で鉛筆ツール、[T→I]ではさみツール等。
ワークスペース
MIDIリージョン等を設置したりするエリア。
ベロシティ
MIDIノートの強弱を表す数値。
これを全く編集せず、すべて同じ数値で打ち込む事を「ベタ打ち」と言い、あまり良くないとされる。
ソフトウェア音源
パソコン(DAW)上で使用する為にデータ化された音源。
サンプラーもモデリングシンセもすべて包括してソフトウェア音源と呼ぶ。
対義語は、実機である「ハードウェア音源」となる。
シンセサイザー
音を波形から編集し、合成(シンセサイズ)する機械。
日本での第一人者としては、冨田勲氏が有名。
モデリングシンセサイザー
上記シンセサイザーをソフトウェア音源にしたもの。
PC上でシンセサイザーの回路をシミュレート氏、波形から音を作り出す。
サンプラー
ソフトウェア音源の種類の1つ。
実際に録音した音を読み込み、鍵盤で演奏する。
高い音質で録音されたデータを読み込む為、高級サンプラーになると高いマシンパワーを要求される。
だが、サンプラー用の追加音源等が豊富に販売されている為使い勝手が非常に良い。
また、自分で録音した音を読み込み新たなプリセットを作ることもできる。
プリセット
各音源の為に、製造者が予め用意したパッチ。
読み込めば自動的に適切なセッティングに音源が組み変わり、必要な音が出せる。
プリセットを編集し、新しいプリセットとして保存する事も可能。
最後に
一気に覚えようとすると大変かもしれませんが、一つ一つ確認して、一度覚えたら忘れないと思います。
まずは触ってみるところから初めてみてください。
少しでも参考になれば幸いでございます。
こちらも参考に:【DTM初心者のための】Logic Pro(ロジックプロ)の使い方。
インストール編
ライタープロフィール
DTMer
akira
京都を中心に活動する音楽ユニット「UNnamed pathfinder」のアレンジャー。
「UNnamed pathfinder」は、キャッチーなメロディ、多彩なコードワークにどこか物憂げな歌詞が魅力のコンポーザー385と、高い表現力と様々なジャンルを操るアレンジャーAkiraの二人によるユニット。
ユニット名は、「名もなき開拓者」を意味し、ジャンルに囚われない二人の作風を表している。
ウェブサイト:https://m.soundcloud.com/akira_6275/
ブログ:https://radishswitsh.wixsite.com/unnamed-pathfinder
Twitter:https://twitter.com/akira25472
YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCECBXlnmnOBDb6lSDacxV_g