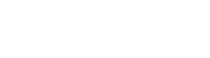Franz Schubertの人気曲ランキング【2026】
壮大な彼の音楽はドイツ歌曲においてしばしば歌曲の王と呼ばれるほど。
彼の作り出した音楽の伸びやかで聴いているだけで癒やされるような美しい旋律は、誰もが一度は聴いたことがあるでしょう。
シューベルトの曲を人気順にランキングにまとめてみました。
ぜひ優雅な時間を過ごしてみてください!
- 【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽
- Robert Schumannの人気曲ランキング【2026】
- Ludwig van Beethovenの人気曲ランキング【2026】
- Franz Lisztの人気曲ランキング【2026】
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- Johannes Brahmsの人気曲ランキング【2026】
- ロベルト・シューマン|名曲、代表曲をご紹介
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- Bedřich Smetanaの人気曲ランキング【2026】
- Frederic Chopinの人気曲ランキング【2026】
- Johann Burgmüllerの人気曲ランキング【2026】
- Antonín Dvořákの人気曲ランキング【2026】
- 【小学生に人気の曲は?】みんなが知ってる&歌いたい人気ソング!【2026】
Franz Schubertの人気曲ランキング【2026】(11〜20)
《高雅なワルツ》op.77Franz Schubert15位

ロマン派を代表する作曲家フランツ・シューベルトのピアノ舞曲をご紹介します。
1827年に作曲された『高雅なワルツ集』は、12曲のレントラーから成る優雅な作品です。
友人との集いで生まれたこの曲は、ウィーンの社交界の雰囲気を感じさせます。
演奏時間は約12分と短めで、親しみやすい旋律が特徴。
ピアノを始めたばかりの方にもおすすめです。
各曲は自由に組み合わせられるので、好みの曲だけを弾くことも可能です。
シューベルトの魅力がたっぷりの本作で、ウィーンの華やかな舞踏会気分を味わってみてはいかがでしょうか。
「白鳥の歌」より第4曲「セレナーデ」Franz Schubert16位

うつうつとした気分、壁にぶつかった時に聴きたい曲。
仕事や学業、家庭など、生活上いろいろな問題に出会います。
解決の手を打たなければいけませんが、何より気持ちがきゅうしてしまいますね。
忙しい中でひと息つくひまもなく、いつの間にかエネルギーを消耗していたことに気付きます。
そんな時、この曲のせつなく悲しい旋律が手を止めて休むきっかけになります。
考えるのは必要です。
でもひとまずはこの曲の世界に身をゆだねて落ち着きませんか。
アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D821Franz Schubert17位

フランツ・シューベルト作曲の『アルペジョーネ・ソナタ イ短調 D821』です。
1824年にウィーンのギター製造者ヨハン・ゲオルク・シュタウファーによって発明された、チェロを小ぶりにしたような6弦の弦楽器「アルペジョーネ」のために作られた曲です。
しかし、出版された1871年にはアルペジョーネが廃れていたため、チェロやヴィオラ、コントラバスで演奏されるようになりました。
ソナチネ イ短調Franz Schubert18位

歌曲で名が知られているシューベルトですが、バイオリンの曲にも数々手がけています。
ソナチネとは、ソナタ形式から成り立っているもののソナタに比べ音構成が簡潔に作られている曲のことなのです。
簡潔とは言えど、掛け合いに大変凝っているのでソナタ以上のクオリティを感じます。
ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960 3楽章 アレグロ・ヴィヴぁー©げデリカテッツァFranz Schubert19位

珠玉の旋律が心を解き放つ名作。
1828年9月に完成した本作は、第3楽章で軽やかな中にも繊細さを併せ持つ楽曲構造が魅力的です。
8小節の主題が巧みに展開され、転調を重ねながら、明るい変ロ長調から同主調の変ロ短調へと移り変わる情感が豊かな響きが印象的です。
独特の拍節感と和声進行によって生み出される陰影のある旋律は、聴く者の心に深い感動を与えます。
フランツ・シューベルトが創意工夫を凝らした転調技法やリズム処理の妙技が随所に光る本作は、クラシック音楽の深い味わいを求める方や、ピアノ音楽の構造的な美しさに魅了される方におすすめの一曲です。
ピアノ五重奏曲 イ長調 作品114 D667《ます》第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェFranz Schubert20位

明るく快活な雰囲気が漂う室内楽の名作は、フランツ・シューベルトが22歳の時に作曲した珠玉の作品です。
ピアノと4つの弦楽器による独特の編成から生まれる豊かな響きと、生き生きとした旋律の掛け合いが印象的です。
力強いピアノと弦楽器の対話が織りなす音の世界は、まるで若者たちが喜びに満ちた集いを楽しんでいるかのような雰囲気を醸し出しています。
1819年に裕福な鉱山技師の依頼で作曲された本作は、自然の美しさや人々の活力といったポジティブな情景を音楽で描き出しています。
クラシック音楽の中でも親しみやすい旋律と表現力を持ち合わせた本作は、室内楽の素晴らしさを体感したい音楽ファンにぜひお勧めしたい一曲です。
Franz Schubertの人気曲ランキング【2026】(21〜30)
ピアノ五重奏曲 イ長調 作品114 D667《ます》第3楽章 スケルツォ、プレストFranz Schubert21位

非常に速いテンポで演奏される明るく軽快な室内楽曲です。
ヴァイオリンが跳ねるように奏でる陽気な主題に、他の楽器が呼応する様子は、まるで春の小川で戯れる生き物たちを思わせます。
1819年に22歳で作曲されたこの作品は、チェロの愛好家であった鉱山技師の依頼により生まれました。
3拍子のリズムが生み出すダンスのような躍動感、ピアノと弦楽器の巧みな掛け合い、そして低音楽器による豊かな響きが、聴く人の心を魅了します。
かつてJR東日本常磐線いわき駅のホームで発車メロディとして使用されていたこともある本作は、室内楽の名曲として広く親しまれています。
音楽を通じて喜びや活力を感じたい方、自然の息吹や日常の楽しさを音で表現した作品に触れてみたい方におすすめの1曲です。