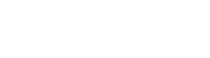Franz Lisztの人気曲ランキング【2026】
ハンガリーで生まれ、19世紀にヨーロッパで活躍したピアニスト・作曲家のフランツ・リスト。
非常に高いピアノスキルを持っていて「ピアノの魔術師」という異名を得たほどです。
今回は名曲ぞろいの彼の作品からもっとも人気のあるものをセレクトしました。
紅茶でも召し上がりながらどうぞ!
Franz Lisztの人気曲ランキング【2026】(1〜10)
愛の夢 第3番Franz Liszt1位
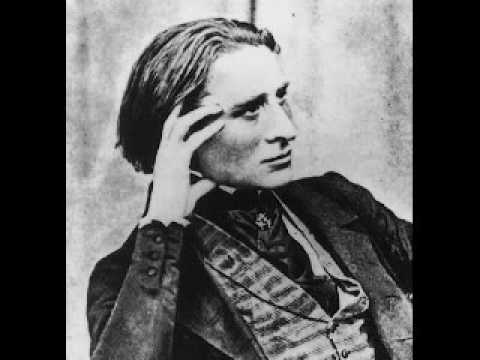
ロマン派を代表するフランツ・リストの代表作。
1845年に歌曲として生まれ、1850年にピアノ独奏版に編曲されました。
家族や友への愛を歌う詩を元に、リストの恋愛経験も反映されています。
美しいメロディと豊かな和音が特徴で、愛の深さと複雑さを見事に表現しています。
ピアノの技巧を存分に活かしながら、優しさや切なさも感じられる名曲。
愛する人と過ごす時間を大切にしたい時に、心に染み入る美しいこちらの作品をぜひ聴いてみてください。
ラ・カンパネラFranz Liszt2位

鐘の音を模した繊細な旋律が印象的で、高音域での跳躍や装飾音が美しく響き渡ります。
1851年に改訂されたピアノ曲は、ロマン派音楽の真髄を感じさせる情熱的な表現力と、技巧的な演奏が特徴です。
フランツ・リストは、1831年にパガニーニの演奏に感銘を受け、ヴァイオリン協奏曲の主題をピアノ用に編曲。
映画やテレビ番組のBGMとしても度々使用され、多くの人々の心を魅了してきました。
本作は、静かな環境で集中して勉強したい方にオススメです。
鐘の音のような透明感のある音色は、心を落ち着かせながらも適度な緊張感を保ってくれるでしょう。
パガニーニによる大練習曲 S.141 第3番「ラ・カンパネラ」Franz Liszt3位

ロマン派の天才ピアニスト、フランツ・リストによる名作。
パガニーニのヴァイオリン協奏曲を題材に、ピアノならではの技巧を駆使して作られた超絶技巧の曲です。
鐘の音を思わせる高音の響きが印象的で、左手の動きも複雑。
1838年に初版が発表され、1851年に改訂版が出されました。
ヘ音譜表の読解力を高めたい方や、左手の演奏力向上を目指す方におすすめ。
華麗な旋律と跳躍の正確さが要求される、ピアノ練習曲の傑作といえるでしょう。
半音階的大ギャロップFranz Liszt4位

リストの名作『半音階的大ギャロップ』。
『超絶技巧練習曲』の『マゼッパ』や『鬼火』とともに、リストの難曲として名高い作品ですね。
そんな本作の難所はなんといっても4-5指を用いた細かい動きではないでしょうか?
指がつりそうになるいやらしい構成に加えて、幅広い跳躍やオクターブも連発します。
並の上級者では正しく演奏することが難しい作品です。
他のリストの作品に比べると、演奏効果がやや低いことで低評価を受けることもありますが、増三和音や全音音階の響きが好きな方にとってはツボに入る作品といえるでしょう。
ハンガリー狂詩曲 第2番Franz Liszt5位

超絶技巧を要する難曲を数多く作曲したピアノの魔術師フランツ・リストの『ハンガリー狂詩曲 第2番』。
こちらの曲も例にもれず非常に難易度が高く、プロのピアニストでも演奏に苦戦する作品の一つです。
重厚な雰囲気から始まり、徐々に華やかさを増していく様子は、まさに圧巻!
明るく美しいメロディと力強いリズムは、長年にわたり多くのピアノ学習者やピアノ愛好家を魅了し続けています。
弾きこなすには相当な練習が必要になりますが、ドラマチックな世界観を楽しみながらチャレンジしてみてください!
超絶技巧練習曲 第5番 『鬼火』Franz Liszt6位

フランツ・リストの楽曲は、超絶技巧と詩的表現を兼ね備えた名曲として高い評価を受けています。
本作は、夜に浮かぶ揺らめく青白い光の幻想的なイメージを象徴しています。
半音階的な速い音型が絶えず続き、音の揺らぎが「鬼火」の幻想的な動きを思わせます。
変ロ長調の調性感を持ちながらも、時折現れる不協和音的な響きやリズムの変則性が、神秘的な雰囲気を作り出しています。
1851年に完成したこの曲は、ピアノ音楽の発展に大きく貢献しました。
クラシック音楽に興味がある方や、技術的な挑戦を求めるピアニストの方におすすめの一曲です。
メフィスト・ワルツ 第1番 s.514 『村の居酒屋での踊り』Franz Liszt7位

ピアノ演奏史に残る超絶技巧の名曲として知られる悪魔的な舞曲です。
1861年に公開された本作は、村の居酒屋での妖艶な舞踏会を題材に、冒頭から激しいリズムと五度の和音で聴き手を魅了します。
中間部では夜鶯のさえずりを模した繊細な音の表現があり、情熱的なワルツと対照的な美しさを放ちます。
管弦楽曲からピアノ独奏用に編曲された本作は、ヴラディーミル・アシュケナージなど、世界的なピアニストたちによって演奏されています。
ロマン派音楽の革新的な和声進行と、狂おしいまでの技巧が渦巻く本作は、華麗なステージを目指すピアニストや、クラシック音楽の極みに挑戦したい方におすすめの一曲です。