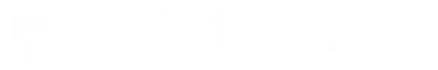1999年に日本で10番目の世界遺産として登録された日光東照宮。
江戸幕府を開いた徳川家康を祀っていることはよく知られていますが、その豪華絢爛な彫刻や建造物に込められた思いまで知っているという方はあまり多くないかもしれませんね。
そこで今回は、日光東照宮の豆知識を知れるクイズを作成してみました。
実際にお出かけになる前に知っておくと何倍も楽しめる豆知識をご用意しましたので、ぜひ楽しんでいただければ幸いです。
- 挑戦しよう!小学生向けの4択歴史クイズ。歴史の授業をおさらい
- 華厳の滝にまつわる豆知識クイズ。日光の観光地について深く知ろう!
- 大人向けの難しいクイズまとめ【難問】
- 小学生向けの盛り上がるクイズ。みんなで一緒に楽しめる問題まとめ
- 【世界遺産】二条城の豆知識が深まる3択クイズ
- 金閣寺にまつわるクイズ。金閣寺を理解するための豆知識
- 平等院鳳凰堂ってどんな場所?日本が世界に誇る建造物を知れるクイズ
- 【子供向け】11月の雑学クイズ&豆知識問題。楽しく知識を深めよう!
- 楽しい10月の雑学クイズ&豆知識問題!子供向けの盛り上がる問題
- 小学生向けの日本一クイズ。「日本で最も〇〇なもの」を当てよう!
- 【小学生向け】楽しくて身につく都道府県クイズ
- 犬にまつわる雑学クイズ。豆知識が身に付く3択問題
- 知りたくなかった?!気になる怖い雑学&豆知識
日本が誇る世界遺産!日光東照宮を深く知れるクイズに挑戦!(1〜10)
日光東照宮は、どの都道府県にあるでしょうか?
- 栃木県
- 静岡県
- 岐阜県
こたえを見る
栃木県
日光東照宮は、栃木県の日光市に位置しています。徳川家康を祀るこの神社は、彫刻や建築で知られ、特に有名な「眠り猫」や「三猿」などは多くの観光客を引き付けています。
徳川家康を祀った東照宮は、日光以外にいくつあるでしょうか?
- 約3箇所
- 約13箇所
- 約130箇所
こたえを見る
約130箇所
実は、日光東照宮以外にも日本各地に約130箇所の東照宮が存在します。徳川家康は江戸時代の初代将軍であり、その死後、神聖視されて多くの地域で東照宮が建立されました。これらは家康を祭神としており、日光東照宮と並んで家康を称える場となっています。
日光東照宮の名前の由来は?
- 家康の幼名に由来する
- 家康の諱(いみな)にちなんでいる
- 家康が死後に追贈された名に由来する
こたえを見る
家康が死後に追贈された名に由来する
日光東照宮の「東照」は、徳川家康が死後に追贈された神号「東照大権現」に由来します。この追号は家康の遺徳を称え、太陽が常に東から昇ることから、家康の治世が永遠に続くようにとの願いが込められています。東照大権現とは、すなわち太陽のように明るく照らす、偉大な権現(神の化身)という意味です。
三猿の彫刻は、日光東照宮のどこにあるでしょうか?
- 本殿
- 陽明門
- 神厩舎
こたえを見る
神厩舎
日光東照宮にある三猿の彫刻は、「神厩舎」(しんきゅうしゃ)の彫刻の一部です。この彫刻は、「見ざる、言わざる、聞かざる」という三つの格言を教えるという意図が込められており、「悪いことは見ない、言わない、聞かない」という意味を象徴しています。
上神庫に施された彫刻が「想像の象」と呼ばれている理由は?
- 実際には存在しない造形の象であるため
- 彫刻が施された象が夢の中に現れることから
- 彫刻家が見た幻想を元に制作されたため
こたえを見る
実際には存在しない造形の象であるため
日光東照宮の上神庫にある「想像の象」は、実際の象を見たことがない職人が想像で彫刻したものとされています。そのため、実物の象とは異なる特徴を持つこの彫刻は、「想像の象」と呼ばれています。耳が小さく、体の比率も実際の象とは異なる等、日本人の象に対する想像が具現化された作品として知られています。
陽明門が別名「日暮し門」と呼ばれている理由は何でしょうか?
- 門の前で見とれている間に日が暮れるから
- 日光が門に当たりにくい構造になっているから
- 夕日が門を美しく照らすから
こたえを見る
門の前で見とれている間に日が暮れるから
日光東照宮の陽明門は非常に精巧かつ豊富な彫刻で装飾されており、「これを見ているうちに夢中になり、気づけば日が暮れていた」ということから、「日暮し門」という別名がつけられました。
有名な東回廊の眠り猫、その裏側にある雀の彫刻にはどんな意味があるでしょうか?
- 猫と雀が共存する平和の象徴
- 猫の夢の中に登場する雀を表現
- 工匠の技術を競うため雀も緻密に彫られた
こたえを見る
猫と雀が共存する平和の象徴
眠り猫の彫刻は、実際には目を閉じていないため、いつでも目を覚まして雀を捕らえることができる状態を示しています。しかし、雀が安心してその場にいる様子から、猫と雀が共存する平和の象徴として表現されているとされます。この彫刻は、生きとし生けるものが争わずに共に生きる理想的な世界を願う思いが込められていると考えられています。