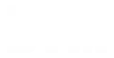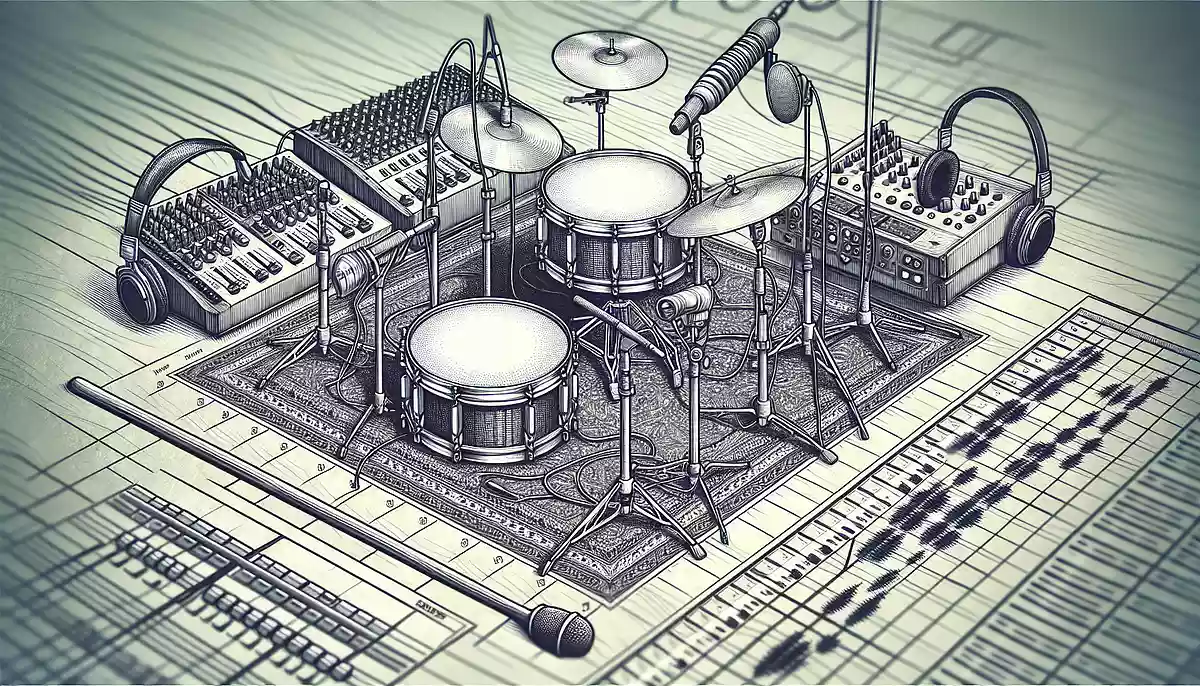ロック・ポップスのドラムパターンでは、いわゆるバックビート、2拍目、4拍目に必ずと言っていいほどスネアドラムが入っています。
ドラムセットの中でも、登場頻度の高い重要なパートと言えるでしょう。
今回は、そんなスネアのマイキングを聴き比べてみました!
マイクの距離や角度の異なる4パターンを録り比べて動画にしましたので、ご覧ください!
- 【ピアノ曲】聴き比べで楽しむパッヘルベルのカノン~ジャズ・ロック~
- DTMで絶対にやってはいけないたった1つのタブー
- プロドラマーが選ぶ。本当に見て欲しいトレーニング動画
- 【邦楽】ドラムがかっこいい曲まとめ【2026】
- ドラム中級者にオススメの練習曲。表現力や演奏力を養える楽曲まとめ
- ドラムのイントロがかっこいい曲
- YouTuberギタリストが選ぶ!ギターストロークの練習曲。邦楽ロック編
- 【2026】ドラム初心者のための練習曲。簡単でかっこいいおすすめ曲
- 楽器別のバンド初心者にオススメの曲
- 【三拍子の名曲】あのヒットソングも!?邦楽&洋楽の人気曲を厳選
- 【リズム】16ビートが使われている邦楽人気曲まとめ【2026】
- 【聴き比べ】個性豊かな『シュガーソングとビターステップ』カバー曲
- ピアノ伴奏パターン|伴奏付けや弾き語りに役立つアレンジをピックアップ
今回の収音環境について
今回使用したマイクはSHURE SM57、スネア収音の定番です。
どのチャンネルもHA(=ヘッドアンプ、マイクプリアンプ)のレベル設定は統一しており、コンプレッサーやEQ等のエフェクト処理はしていません。
スタンダードな立て方その1
まずはスタンダードな立て方その1。
 マイクの指向性の延長線上に、ヘッドの中央とシェル(胴)の中心が来るイメージでマイクの角度をつけています(下図)。
マイクの指向性の延長線上に、ヘッドの中央とシェル(胴)の中心が来るイメージでマイクの角度をつけています(下図)。
 狙う際にはマイクの真後ろからのぞき込むようにすれば、どこに向いているのかが分かりやすいと思います。
狙う際にはマイクの真後ろからのぞき込むようにすれば、どこに向いているのかが分かりやすいと思います。
この立て方だと「スティックがヘッドに当たるときのアタック音」と「胴鳴りの余韻のある音」がバランスよく収音できます。
僕がドラムを録る際にはこの立て方を最初に試してから、録り音に応じて角度や距離を調整しています。
スタンダードな立て方その2
次にスタンダードな立て方その2。
 その1と同様、マイクの指向性の延長線上に、ヘッドの中央とシェルの中心が来る角度です(下図)。
その1と同様、マイクの指向性の延長線上に、ヘッドの中央とシェルの中心が来る角度です(下図)。
 異なるのはマイクの距離。
異なるのはマイクの距離。
先ほどとは違い、マイクがスネアのリムにかかる距離まで近づいています。
アタック音と胴鳴りの音がバランスよく収音されているのは先ほどと同じですが、マイクがリムに近いことで、「カーン」という金属的な音が強調されます。
また、近接効果により低音も強調され、モコモコとした部分も目立ちます。
上から狙う立て方その1
今度は上から狙う立て方をやってみましょう。
 表のヘッドの中央は狙わず、スネアサイド(裏のヘッド)の中央に向けるイメージで角度をつけています(下図)。
表のヘッドの中央は狙わず、スネアサイド(裏のヘッド)の中央に向けるイメージで角度をつけています(下図)。

この立て方だと胴鳴りの音はほとんど収音できませんが、その分アタック音が目立つ明るい音になります。
ほかの立て方と比べると音が短くなったように感じるのではないでしょうか。
上から狙う立て方その2
最後に上から狙う立て方をもうひとつ。

ヘッドの端ギリギリのところを狙い、マイクを完全に真下に向けています(下図)。

リムの「カーン」という音がもっとも強調された音になりました。
なおかつ、スタンダードな立て方1と比較するとモコモコとした部分は少なく、明るい雰囲気になっているのが分かると思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
マイクの立て方ひとつでスネアの音がガラリと変わったのがお分かりいただけたかと思います。
今回4パターンの立て方を紹介しましたが、どの立て方が良いとか正しいとかいうことではありません。
たとえば、近接効果による低域の強調も、「ローが邪魔だ」ととらえるか「太くなった」ととらえるかは、ジャンルや曲調、テンポ感次第で変わってきます。
また、シェルの材質やヘッドの種類、チューニング、ドラマーの叩き方によっても当然音のキャラクターは変わります。
大切なのは、求める音の方向性に応じて、臨機応変にマイキングを使い分けること。
今回の記事がその一助となれば幸いです。