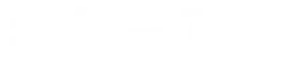エレキギターに最近興味を持った人は、「エレキギターの種類ってどのくらあるの?」「ギターによる音の違いは?」など、気になることも多いのではないでしょうか。
今回は代表的なギターをタイプ別にピックアップして、その違いや特徴をまとめてみました。
これからエレキギターを始める初心者の方にとって参考になれば幸いです。
- 【挑戦】エレキギター初心者のための練習曲
- 意外と知らない!?ゲイン(GAIN)とボリューム(Volume)の正しい使い方
- ギターの効果的な練習方法。今すぐやめるべき無駄な練習とは?
- ギターを買ったらまずやるべきこと。末長く使うためのチェックポイント
- バンド初心者にオススメの曲。簡単で盛り上がる曲
- 【エレキギター初心者のための】トレモロユニットの基礎知識
- ギターコードっていくつ覚えないといけないの?
- 中古ギターを購入するときに注意したい7つのポイント
- 世界に誇る人気の国産ギターメーカー・ブランド一覧
- ピアノで弾いてみたい!初心者におすすめのビートルズの曲まとめ
- ギターサウンドの奥深さ。ギターがかっこいい曲まとめ
- 楽器別のバンド初心者にオススメの曲
- 【コードが簡単】ギターが簡単な邦楽人気曲まとめ
種類によって音が違う
エレキギターは構造やパーツ、木材の材質、ボディーの形状など、さまざまな要素が絡み合うことで音色が変わってきます。
現在では見慣れたタイプばかりかもしれませんが、エレキギターは音楽の歴史とともに歩み続け、現在も日々進化しているのです。
とはいえ、ギターを始めたばかりの方にとっては、微妙な音の違いなどはなかなか分からないものです。
でもそれでいいんです。
最初は好きなギタリストが使っているタイプを選んで、とにかくまずは弾き始めてください。
エレキギターの種類と特徴
ストラトキャスター・タイプ

http://forums.fender.com/viewtopic.php?f=6&t=48158
ストラトキャスターは、Fender社が1954年から発売しているエレキギターで、現在もなお根強い人気を誇っています。
他の多くのギターメーカーからもほとんど同じ形のギターが発売されていて、Fender社のそれとは区別されますが、名前も「ストラトキャスター・タイプ」などと呼ばれています。
とても影響力の強い、エレキギターの代表的な機種のひとつで、エレキギターを始める上で、まずマスターしておきたいタイプのギターといえるのではないでしょうか。
ちなみに歴史としてはこの後紹介するテレキャスタータイプのほうが古く、Fender社が元々製造していたテレキャスターを発展させたものになります。
さまざまなシーンに対応できる幅広い音色のバリエーションがこのギターの大きな特徴で、ロックだけではなくポップス、ジャズ、フュージョン…など、多くの音楽ジャンルで活躍しています。
3つのシングルコイルのピックアップを中心に構成されていることで、より細やかなサウンドを表現できるのです。
さらに、トレモロユニット(アームとも呼ばれる)をブリッジ部分に搭載し、音程を揺らす効果(ビブラート)をかけることができます。
大音量で歪ませる場合には、シングルコイル特有のノイズが発生することになりますが、それも含めたところの「味」が評価され、現在でもスタンダードなエレキギターのタイプとして愛用され続けています。
使用有名ギタリスト
ジミ・ヘンドリックス / エリック・クラプトン / ジェフ・ベック / リッチー・ブラックモア / デヴィッド・ギルモア / バディ・ガイ / ロバート・クレイ / スティーヴィー・レイ・ヴォーン / ハイラム・ブロック / エドワード・ヴァン・ヘイレン / ブラッド・ギルス / スティーヴ・ルカサー / スティーヴ・ヴァイ / イングヴェイ・マルムスティーン / ロリー・ギャラガー / エリック・ジョンソン / ジョン・メイヤー / ジョン・フルシアンテ / Char / 森園勝敏 / トモ藤田 / 鈴木茂 / 春畑道哉 / 安達久美 etc…
レスポール・タイプ

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Les-Paul/Gibson-Custom/50th-Anniversary-1959-Les-Paul-Standard.aspx
レスポールは、1952年にGibson社から発表されたエレキギターです。
ストラトキャスタータイプと同様に、発売以来いまも数多くのギタリストに愛用され続けています。
発表当初はピックアップにシングルコイルタイプに近い「P-90」を搭載するタイプが主流でしたが、シングルコイルを二つ並べたようなハムバッカーピックアップを発表してからは、これがレスポールタイプの最大の特徴となりました。
ストラトキャスタータイプに比べると「ノイズに強く・太い音」を出すことができて、大音量で派手なサウンドを好むロックギタリスト向きのギターといえるのではないでしょうか。
2種類の木材を貼り合わせた独特の構造ゆえに重量があり、初心者や女性にとっては慣れるまで少し重く感じるかもしれません。
https://youtu.be/JcVjgqc8Ms4?t=2m21s
使用有名ギタリスト
エリック・クラプトン / ピーター・グリーン / マイク・ブルームフィールド / ミック・テイラー / キース・リチャーズ / ジミー・ペイジ / ポール・コゾフ / ピーター・グリーン / ミック・ロンソン / ミック・テイラー / ディッキー・ベッツ / ジョー・ペリー / スラッシュ / ザックワイルド / ゲイリー・ムーア / エース・フレーリー / ピーター・フランプトン / スティーヴ・ジョーンズ / マイク・ブルームフィールド / 松本孝弘 / 奥田民生 / 斉藤和義 / Ken Yokoyama etc…
テレキャスター・タイプ

http://www.skymusic.com.au/Fender-Classic-60-s-Telecaster.html
テレキャスターはエレキギターの歴史の中でも最も古く、1949年頃にFender社から「エスクワイヤー」の名を冠して発売されました。
ソリッド・ボディやボルトオン・ネックなど、それまでの伝統的なギターの概念からは大きく離れたものでしたが、ユーザーからの好評を得て、エレキギターの定番タイプとして多くのギタリストが愛用しています。
空洞部分がないのが構造の特徴で、ネックとボディの木材は完全分離しているタイプが基本です。
弦はボディ裏から通すようになっており、弦に対してシンプルで無駄がなく取り扱いやすい構造です。
そしてサウンドの特徴は、なんといってもシングルコイルを活かした「チャラーン」「シャキーン」といった澄んだ高音域です。
ハムバッカーに比べてノイズを拾いやすい欠点もありますが、音の立ち上がりやまとまりはよく、クリーンのアルペジオでもキレのあるカッティングでも大活躍するギターです。
ほかのギターと比べるとリードフレーズの抜けこそ派手ではないですが、アンサンブル中でほかの楽器の帯域を邪魔することなく存在感を持つエレキギターとなっており、近年の日本のバンドでは「ギターボーカルがテレキャスター」といスタイルも定番になりつつあります。
https://youtu.be/Gsjo3S5WNxs?t=1m27s
使用有名ギタリスト
ジェームズ・バートン / ジミー・ペイジ / ジョー・ストラマー / キース・リチャーズ / アンディ・サマーズ / マディ・ウォーターズ / ジョージ・ハリスン / ブルース・スプリングスティーン / ジ・エッジ / ウィルコ・ジョンソン / ジョニー・グリーンウッド / トム・モレロ / ゲム・アーチャー / アベフトシ / 橋本絵莉子 / TK / 岸田繁 etc…
SG・タイプ

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/SG/Gibson-USA/SG-Standard.aspx
SGタイプも歴史は古く、GibsonのSGはレスポールスペシャルの進化系として、1959年に誕生しました。
ボディはマホガニーという木材の一枚板で厚みも薄く、ダブルカッタウェイが基本となっており他のギターと比べると軽いのが特徴です。
その軽さゆえに、ストラップをつけて立って演奏する際には、手で支えていないとヘッド側に傾いてしまう欠点もあります。
SGスペシャル、SGスタンダード、SGカスタム…などさまざまなタイプがあり、豊かな中低音はそのままに、現代にいたるまでなお進化を続けている優れたギターです。
クリーンはもちろん、歪ませて使用しても余分な雑味が少なく音抜けも良いことから、近年では重低音系のギタリストにも愛用されています。
https://youtu.be/CSxfDJ7eayw?t=55s
使用有名ギタリスト
アンガス・ヤング / トニー・アイオミ / カルロス・サンタナ / フランク・ザッパ / エリック・クラプトン / ジョージ・ハリスン / ジミー・マッカロク / ディッキー・ベッツ / デレク・トラックス / ピート・タウンゼント / ロビー・クリーガー / ポール・ウェラー / グレン・ティプトン / ドン・ウィルソン / ジ・エッジ / マニュエル・ゲッチング / バーナード・サムナー / リヴァース・クオモ / トム・リントン / パトリック・スタンプ / 岡野昭仁 / 椎名林檎 / Nakajin / 山内総一郎 / ハヤシヒロユキ etc…
フルアコースティック・タイプ

http://www.gretschguitars.com/products/index.php?partno=2401404805
アコースティックギターのようにボディが空洞の構造になっている、エレキギターです。
ボティーの大きさがアコースティックギターと同じくらいなので、アコギからフルアコースティックタイプに持ち替えても違和感なく演奏できます。
代表機種は、Gretsch社のG6120やG6136(ホワイトファルコン)と呼ばれるもので、1950年代の全盛期にカントリーやロカビリーのギタリストに愛用され、エレキギターとしての地位を確立しました。
サウンドの特徴としてはコード感を失わず美しく響くので、コード主体のギタリストに愛用されることが多いです。
歪ませて使用する場合もありですが、他のタイプと比べると細やかな音作りが難しいので、アンプ直の素直な音がもっともこのギターの良さを引き出せます。
使用有名ギタリスト
ウェス・モンゴメリー / ジャンゴ・ラインハルト / ジョー・パス / チェット・アトキンス / ジョージ・ハリスン / ブライアン・セッツァー / チェット・アトキンス / ニール・ヤング / エディ・コクラン / パット・メセニー / チャーリー・ワッツ / スティーヴン・スティルス etc…
セミアコースティック・タイプ

https://www.pinterest.com/ajhthijssen/gibson-es-335/
フルアコースティックギターに比べるとボディが薄く、空洞部分も狭くなっているのが特徴です。
「ソリッドボディにアコースティックサウンドをくわえるという」コンセプトで1958年にGibson社が発表したES-335がセミアコースティックタイプのもともとの始まりです。
他にもEpiphoneのCasino、Dotなどがこのタイプにあたります。
サステインのあるサウンドやハウリングの少なさで、ジャズ系ギタリストに好まれます。
もちろん歪ませてロック系などにも幅広く使えます。
見た目もオシャレで、ステージ上でも圧倒的な存在感を放ちます。
使用有名ギタリスト
B.B.キング / ラリー・カールトン / ロイ・オービソン / エリック・クラプトン / チャック・ベリー / ノエル・ギャラガー etc…
フライングV・タイプ

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Flying-V/Gibson-USA/Flying-V-120.aspx
変形ギターの代表格、フライングVタイプは、文字通り「V」の形をしたギターです。
1958年にGibson社からエクスプローラーと共に発売されるも、当時はあまり人気が振るわず生産を終了してしまったのですが、その後、有名ギタリストが使用し始めたことで徐々に人気が出始めていったギターです。
ボディーは軽く、ネックも握りやすい上、重心の低い音が出せるので、ライブで派手に動き回るハードロックやメタルバンドのギタリストによく使用されます。
一方でV字型のボディ形状が原因で、座って弾く際には固定が難しい欠点もあります。
ハムバッカータイプのピックアップが搭載されていて、しっかりとした抜けの良い中低音がサウンドの特徴です。
使用有名ギタリスト
アルバート・キング / ジミ・ヘンドリックス / レズリー・ウエスト / キース・リチャーズ / ポール・スタンレー / マイケル・シェンカー / レニー・クラヴィッツ / 高崎晃 / 橘高文彦 / 木下理樹 etc…
エクスプローラー・タイプ

http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Explorer/Gibson-USA/Explorer.aspx
エクスプローラーは、Gibson社から1958年にフューチュラという名前でデビューし、一時は生産がストップしたものの、1975年の再生産後に多くの著名ギタリストに使用され有名になりました。
年代的にハードロックやメタルバンドのギタリストに愛用者が多いです。
外観は「変形ギター」という印象ですが、ハムバッカーピックアップを搭載したそのサウンドは、低域・高域共にバランスが良く、無理なくしっかり鳴ってくれます。
フライングVなどの変形タイプと違って、座っても安心して弾けるのも特徴です。
使用有名ギタリスト
リック・ニールセン / アレン・コリンズ / ジェイムズ・ヘットフィールド / マーティ・フリードマン / 高見沢俊彦 / PATA / 山本恭司 etc…
最後に
エレキギターの形状だけを見れば、当時から現在に至るまでそれほど変化はありませんが、肝心の中身、サウンドは今現在も進化し続けています。
好みのジャンルやプレイスタイルに合わせてチョイスするのも理想ですが、使いこんでいくうちに新たな使用方法を編み出していくのもまた、これからの音楽の進化に必要なのではないでしょうか。