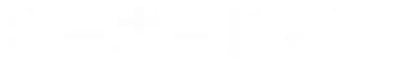MIDIと聞くとどうしても打ち込みやシンセ奏者のためのもの、と思いがちですが、使いこなせば作曲やトレーニング、機材のコントロールまでバンドマンにとっても大変便利な規格です。
基本的なことをまとめてみましたので、はじめてDTMなどされる方の参考になれば幸いです。
- DTMで絶対にやってはいけないたった1つのタブー
- 音楽作る時に出てくる「打ち込み」って何のことですか?
- 初心者の僕が選んだのはコレ!自分のDTM環境に合うオススメMIDIキーボードBest5+1
- 【誰でも曲が作れる!】GarageBand(ガレージバンド)の基本的な使い方
- ドラム打ち込みのコツ。グルーブの支配者を理解しよう!
- 【冬休みに集中練】バンド初心者にオススメな簡単コピー曲まとめ
- DTMや作曲に役立つ!ドラム打ち込みの基本
- 車内空間を彩ってくれる!ゆとり世代の方におすすめのドライブソング
- 楽器用ケーブルの種類と特徴。バンドマンのための基礎知識
- 【2026】生成AI・人工知能が作った海外のおすすめ曲まとめ【洋楽】
- ライブで打ち込みと同期する方法
- 楽器別のバンド初心者にオススメの曲
- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】
MIDI(ミディ)って何?
MIDIとは、国際標準となっている電子楽器の規格のことです。
キーボードやシンセサイザーなどの楽器や、オーディオインターフェースやエフェクターなど機器に搭載しているあの端子のことです。
MIDI(ミディ、Musical Instrument Digital Interface)は、日本のMIDI規格協議会(JMSC、現在の社団法人音楽電子事業協会)と国際団体のMIDI Manufacturers Association (MMA) により策定された、電子楽器の演奏データを機器間でデジタル転送するための世界共通規格。
物理的な送受信回路・インターフェース、通信プロトコル、ファイルフォーマットなど複数の規定からなる。
世界共通の規格になった経緯
1970年代の終わりから80年代初頭にかけて、アナログシンセサイザーが一般ユーザーに普及していきました。
シーケンサを使ってシンセサイザーを自動演奏させるという発想も、すでにこの時代に生まれていたようです。
ただ当時は、規格がメーカー間で統一がされていないと問題があったり、シンセサイザーを外部からコントロールするということは簡単ではありませんでした。
そしてシンセサイザーにマイクロコンピュータが内蔵されるようになり、演奏情報をデジタル化することが容易となり各メーカーはデジルタル信号による伝達方式を開発するものの、それぞれ独自の企画では普及までに至りませんでした。
そごで1981年頃からメーカー間でデジタル信号による伝達方法の標準化についての話し合いが始まりました。
1981年、ヤマハやコルグ、カワイ、ローランド等、国内外計6社によって規格案が整理され、初版のスペックができあがった。
その後、3年を経て協会(MMA: MIDI Manufacturers Association)も設立。
そして1982年1月にアメリカで行われた会合で最初のMIDI仕様が誕生し、その内容が同年10月に専門誌「KEYBOARD」誌上で初めて一般に発表されました。
MIDIを使いこなせるとこんなに便利!
使用例の一部をご紹介します。
アンプチャンネル・エフェクトの切り替えが同期できる
MIDI端子が搭載されているものであれば、チャンネル切り替えの情報や、エフェクトループのON・OFFなどにも使用できます。
例:ギターアンプチャンネル切り替え
1台の鍵盤で、何台もコントロールできる!
MIDI端子には、一般の音声ケーブル同様、INPUTとOUTPUTがあります。
それらを接続することで、MIDIコントローラー(例:鍵盤やPAD)で、鳴らしたい音源の音を鳴らすことができ、コントロール(演奏)が可能です。
使用例:複数の音源を演奏、PADで演奏
DAWソフトのプラグイン音源のコントロールもできる
コントローラーをパソコンもしくは、オーディオインターフェースに繋げれば、ソフトウェア内の音源を鳴らすことができます。
それら使用して演奏情報(MIDIデータ)を入力すれば、そのデータは記憶できます(再生すると、自動演奏が可能)。
使用例:ドラム、シンセサイザーなどの打ち込み
MIDIファイルとして書き出せる
MIDIファイル(演奏情報)としての扱いも可能です。
例えば楽譜ソフトにMIDIファイル取り込むと、演奏したデータの楽譜が作成できます。
使用例:楽譜作成・書き出し
MIDIは楽器やコンピュータの世界だけではない!
通信カラオケや携帯電話の着信メロディの自動演奏装置などは、MIDIのデータなのです。
- 街のカラオケルームの「通信カラオケ」はお店にMIDI音源がおいてあり、カラオケの演奏データは、MIDIで送られて来るのです。
- 携帯電話の着信メロディの送受信にも活用されています。
- また、テーマパークやアミューズメント・スペースでの自動演奏装置の多くはMIDIシステムによるものです。
- さらに、MIDIシステムは、照明装置や、各種スイッチングの自動制御装置とも連動し、ステージやホールなどでも大活躍しています。
知っておきたいMIDIの基礎知識
演奏情報や機器の操作をコントロールするために知っておきたい基礎知識です。
代表的な事柄をざっくり上げますが、すべて覚える必要はありません。
自身が使用する項目だけを覚えておくといいと思います。
MIDIは音声ではない
MIDIはあくまで音や機材をコントロールする規格です。
音声の情報は含まれていません。
接続の仕方
MIDI機器の接続には、MIDIケーブルが必要になります。
(PCならUSBケーブル)
MIDIケーブルの中を流れる信号は一方通行のため、ルールに合わせて接続しないといけません。
MIDI INPUT端子
演奏情報を受け取るための端子です。
受け取った情報を基に音楽を演奏するためのもので、音源側に接続します。
音源のなかにはキーボードが付いていないタイプのものもあります。
MIDI OUTOUT端子
演奏情報を送り出すための端子です。
演奏情報を出力できる機器のほうに接続します。
キーボードタイプの他に、管楽器型・ギター型・ドラム型などの入力装置があります。
MIDI THRU端子
受け取った情報をそのまま送り出すための端子で、MIDI OUTと役割は若干異なります。
例えば、キーボードを弾かなくても、MIDI INから受け取った情報がMIDI THRUから出力されます。
こうすることで「1台のキーボードで複数の音源を鳴らす」というような使い方が出来ます。
音の高さ=ノート・音の強さ=ベロシティ・音の長さ=デュレーション
MIDIでは、演奏情報の音を表す3要素を数値で表します。
これらの情報を決めてやることで、メロディやリズムなどの細かい情報をMIDIデータとして作成できます。
ノート(Note)
音の高さ・音名のことです。
音名は「ド→C、レ→D、ミ→E、ファ→F、ソ→G、ラ→A、シ→B」のアルフェベットで表します。
そして音名の後ろにオクターブを表す数字を付けます。
例:C3、B5など数値で表現する場合は0から127までです(この番号を「ノートナンバー」と呼びます)。
88鍵のピアノの音域をノートナンバーで表すと21(A0)から108(C8)となりなります
ベロシティ(Velocity)
音の強さのことです。
ノート情報に含まれるパラメータで、そのノート情報(1音)の音の大きさを操作できます。
0で音がでなく、1で一番弱く(小さい音)、127でもっとも強い(大きい音)です。
(0〜127で調節)
音の長さ=デュレーション(duration)
音の長さ(音符の種類)のことです。
シーケンサーソフトの分解能にもよりますが、4部音符の長さで960、8部音符で480…などで表します。
ただ、これは100%弾いた場合の話で、楽譜表記のスタッカートの場合は960の60%とか、テヌートの場合は960の120%など、曲や音源によって長さを調節する必要があります。
MIDIデータを操作する画面は大きく分けて4種類
様々なデータ入力方法があります。
ピアノロール画面
一般的に打ち込み(情報入力)などでは一番使用されている画面です。
横が時間軸で、縦が音程です。
ステップ入力画面
ステップ入力というのは、デュレーションと入力する音符の間隔をあらかじめ決めておいて、MIDIノートを入力していくものです。
コードのような複数の音符を一度に入力する時や、ドラムのような等間隔でMIDIノートを入力する場合に使うと便利です。
スコアエディタ
五線譜の画面です。
譜面を書く感覚で、MIDI情報を入力できます。
イベントリスト
一つ一つの音の情報のリストです。
数値で表記されるので、視覚的に操作するのは難しいかと思います。
コントロール・チェンジ(チャンネルメッセージ)
受信側の機器が複数の場合、それぞれに任意の受信チャンネルを設定することによって任意の機器にのみMIDIのメッセージを送り込むことが可能になるのです。
(それらをまとめてチャンネルメッセージといいます)
コントロール・チェンジとは
MIDI機器をコントロールする時に使うコントロール番号のことです。
ノート以外の様々な演奏情報を伝えるために使用されます。
主にCC#0-63は連続可変系統、CC#64-95はスイッチ系統、CC#96-121は特殊系統、CC#121-127はモード・メッセージ用として割り当てられています。
番号を示す際には「CC#」という書き方をする事が多くなっています。
例:
CC#1:モジュレーション(音を揺らす)CC#7:ボリューム(音量を調整する)CC#10:パン(左右の定位を決める)CC#11:エクスプレッション(音量を調整する)CC#64:ホールド1(音を伸ばす)
プログラム・チェンジ(チャンネルメッセージ)
プログラム・チェンジとは音色の切替をするためのメッセージです。
MIDI音源側に使用する音色を切り替える際に使用します。
システム・メッセージ
大きく分けるとリアルタイムメッセージとコモンメッセージの2種類あります。
両方を組み合わされて使用されます。
リアルタイムメッセージとは
リアルタイムメッセージは、MIDIシーケンサなどの同期演奏の為のものを中心としたメッセージのことです。
例:
F8H:タイミングクロック(同期演奏を行うためのクロック)FAH:スタート(先頭から演奏を開始する)FBH:コンティニュー(現在の位置から演奏を開始する)FCH:ストップ(演奏を停止する)FEH:アクティブセンシング(断線などのトラブルを防ぐダミー情報)FFH:システムリセット(電源をオンにした状態にリセットする)
コモンメッセージとは
リアルタイムメッセージと組み合わせて使用します。
例:
F1H:MTCクォーターフレーム(タイムコードの絶対時間を伝える)F2H:ソングポジションポインタ(演奏を開始する位置を指定する)F3H:ソングセレクト(演奏する曲を指定する)F6H:チューンリクエスト(オートチューンを行う)F7H:エンドオブエクスクルーシブEOX(エクスクルーシブの終了を表わす)
MIDI検定もあります!
電子音楽のソフトウェア、コンピュータネットワークでやりとりされる音楽データや、通信カラオケの送信データ、携帯電話の着信メロディにいたるまで、電子音楽の事実上の標準規格となっていく状況です。
MIDIを使った音楽制作の現場では、MIDIに関する知識を持ち、データの制作・監修ができる人材が求められており、そんな中で「よりMIDIの規格を広める」意図で始まった検定試験のことです。
MIDI認定制度はMIDI規格を広く一般社会に普及啓蒙する事を目的に、規格内容の認識・活用レベルを標準グレード化してMIDIを活用できる人材を数多く創出する事を目指して平成11年度よりスタートしました。
当初のグレードは初級クラス3級からのスタートでしたが、現在までに上級クラス2級、入門クラス4級も制定され、各クラスにあった検定制度のガイドブックの充実も図られ、検定試験会場は全国の主要都市で開催されるまでになっております。
最後に
今回は、たくさんの機器を操作上では、覚えておきたいMIDIの基礎知識でした。
一気に覚えることは難しいと思うので、MIDI機器を使用し始めた際に分からないことがあるときに読み返してもらえたらと思います。