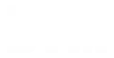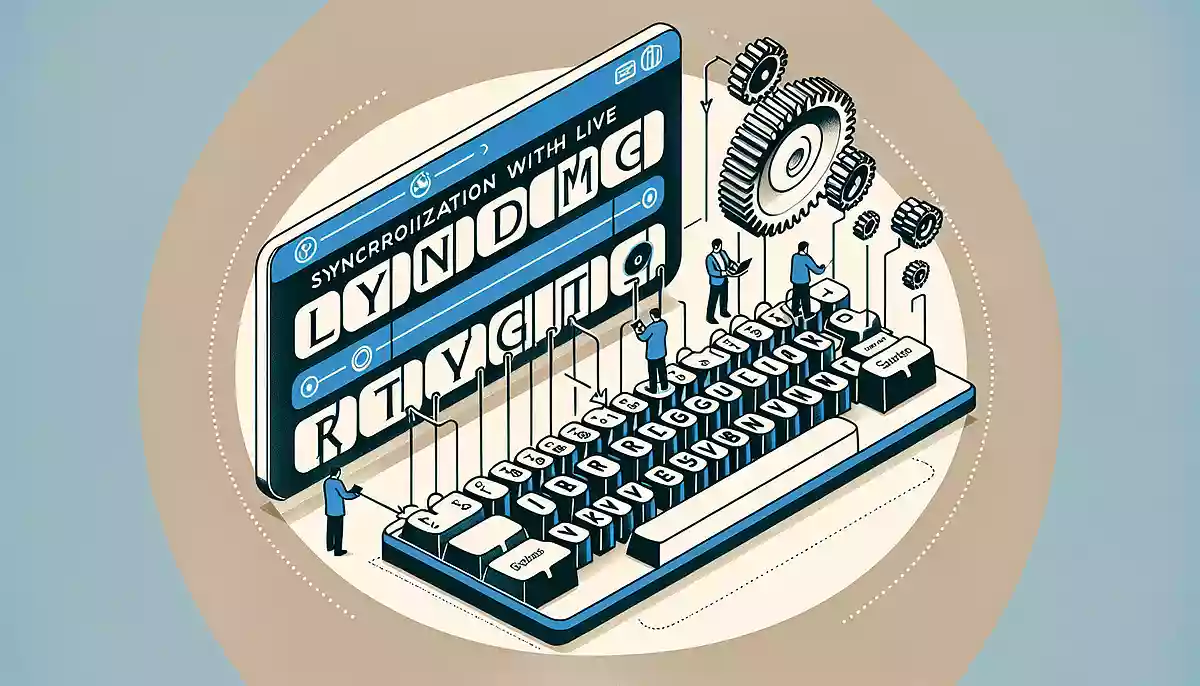ライブで打ち込みと同期する方法
ライブで打ち込みの音源を鳴らしたい!
打ち込みの音とどうやってテンポを合わせるの?
今回はライブにおいて生演奏と打ち込みパートを同期する方法についてまとめてみました。
生演奏以外の音も鳴らしてライブがしたい!
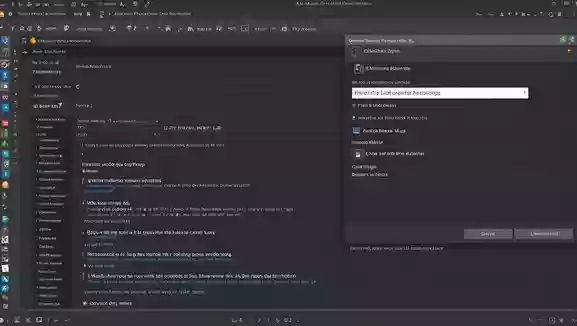
https://unsplash.com
ライブの魅力はなんといっても生演奏ですが、自分の演奏以外の音も流して「もっと豪華にしたい!
」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際に演奏していなくても1つの楽器としてとらえ、事前にそれを仕込んでおくのもライブに向けての立派な準備と言えるでしょう。
より自分の演奏が引き立つような「打ち込みサウンド」を鳴らしてみませんか?
そもそも「打ち込み」ってなに?

https://unsplash.com
打ち込みとは、演奏情報を入力しておいて(打ち込んでおいて)、それを再生させたり打ち込みパートと生演奏が同時に鳴らして初めて成り立つサウンドのことを差します。
バンドメンバー以外の音が欲しい場合は、それを自動演奏してくれるように事前に用意しておく必要があります。
そのためにレコーディングしたり、MTR(マルチトラックレコーダー)や、DAWソフトなどを使用して作ったりすることも、まさに「打ち込む」と呼ばれるものです。
シンセサイザーの音、ピアノの伴奏、ストリングスパート、リズムトラック、飛び道具のような効果音、音源サンプル、コーラスパート、ハモリなど……とにかく生演奏以外の音を鳴らすためには「打ち込み」が必要なのです。
ちなみに下の動画では、サカナクションのボーカル、山口一郎が「打ち込みとの同期について」自らのラジオ番組内で解説しています。
リズムを合わせるにはテンポの同期が必須

https://unsplash.com
打ち込みパートがメインのリズムで鳴っている場合は、そのリズムに合わせて演奏すればいいだけの話ですが、曲の展開途中に出てくるような場合は発音のタイミングをそろえなければいけません。
それらは生演奏と打ち込みのテンポや曲構成を同期することで解決するのですが、ステージで演奏する際には何かしらテンポガイドをモニターしながら演奏しないと、打ち込みパートとテンポを同期することはできません。
かといってリズムガイド(クリックやメトロノームなど)をステージ上で鳴らしてしまうと、その音が客席にも聴こえてしまい好ましくありません。
つまり当たり前ですが、リズムガイドは演奏者にのみ聴こえなければいけないのです。
そしてそれらの役割は、バンドでの場合は基本的にドラムパートの役割になることが多いのと、演奏中の曲の出だしのカウント、リズムキープは必須になります。
それらを計算し、スタジオでは何度もテストし練習する必要があります。
日本でいち早く打ち込みと同期させた演奏を取り入れたバンド、YMOの古いライブ映像でその様子が確認できます。
バンドメンバー全員がこの時メトロノームのクリック音を聞きながら演奏しています。
https://www.youtube.com/watch?v=kdalyjjfVxY
今回は、そんな打ち込みパートを同期して鳴らす方法をいくつかご紹介します。
ライブで生演奏と打ち込みパートを同期させる方法
ポータブルプレイヤー・タブレットを使用する
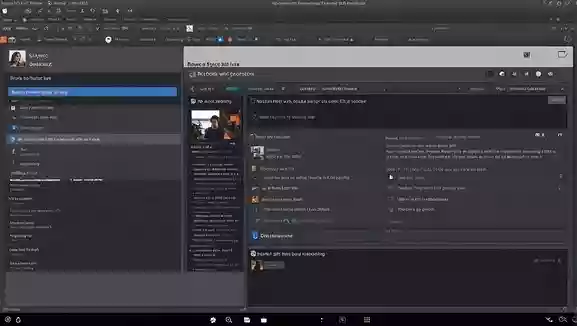
お持ちの音楽プレイヤーを使用する方法で、こちらで大変分かりやすく紹介されています。
DJ機材専門店PowerDJ’s / バンド演奏と打ち込みパートを同期させる一番簡単な方法
LR出力の片側に打ち込みパートを、もう片側にリズムガイドを事前に用意しておき、それぞれ別々に出力させる方法です。
例えば以下のような感じです。
- Lch(PANもっとも左へ):打ち込みパート → PA側へ(※モノラルでの出力になります)
- Rch(PANもっとも右へ):リズムガイド(クリック) → 演奏者(ドラムパートなど)がモニター
ケーブルは以下のようなケーブルを使用します。
EXFORM製 iOS DJアプリ対応スプリットケーブルが入荷!
注意点としては打ち込みパート作成の際に、目的の音をそれぞれLRにしっかりPANで振り切ってしまわないと、リズムガイドが外に漏れてしまう可能性があります。
そして画像の接続例では、 iPhoneを使用していますが、本来はあまりオススメしません。
電話が鳴ったり、通知があるとその音も鳴ったりして事故になるからです(笑)。
どうしても使用する場合は、機内モードをONにしたり、通知をOFFにしたりしておきましょう。
もしくは過去使用していたスマホなどをプレイヤーとして使用しましょう。
あとは、ライブ本番中にバッテリーが無くならないように、ライブ前にはバッテリーの残量をチェック、充電忘れずに行いましょうね。
パソコンを使用する

https://unsplash.com
こちらはDAWソフトの音声をオーディオインタフェースなどからそのまま外に鳴らす方法です。
リアルタイムで打ち込みパート内のバランスを調整したい場合は、こちらのほうがオススメです。
ただしパソコンの動作が途中で止まったりするリスクはあります。
他のソフトウェアを終了させ、バッファーサイズを高めに設定してCPU負荷を減らすなどして、少しでも動作停止のリスクを減らします。
サンプラー・PADを使用する
打ち込みパートを、叩いたり押したりして鳴らす「楽器」としての扱いにします。
ステージの演奏者がPADを操作すれば、目的の音が発音されるようにサンプラーなどに仕込んでおきます。
参考:手軽にサンプリング!
Roland SP-404の使い方
CD-R音源を用意しておく
リズムトラックを打ち込みパートとして鳴らす場合は、リズムガイドの必要はありませんので、そのままCD-R音源を鳴らす方法がオススメです(普通にカラオケで歌うみたいな感じです)。
その際には、ライブ会場のPAさんと事前に打ち合わせしておきましょう。
- モニター音量チェック
- どのトラックを流すのか?
- どのタイミング・きっかけで流すのか?
……など
「ドラマーがいない!」「バンドメンバーがいない!」という状況のライブステージではシンプルで確実な方法かもしれません。
用意するものも少なくていいので、機材トラブルなどのリスクもありません。
用意しておきたいもの
続いて用意しておきたいアイテムの紹介です。
打ち込み音源データ
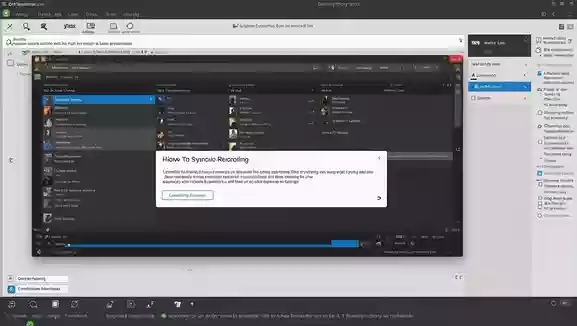
https://www.pexels.com
これは必須です!
打ち込みパートは、ライブ会場での鳴りを想定したトラック作りが問われます。
練習やリハーサルも本番同様に、生演奏と一緒に鳴らしてチェックしておきましょう。
イヤホン・ヘッドホン
インナータイプのイヤホンがオススメです。
しっかりモニターでき、なおかつ演奏時に外れにくいものが理想です。
参考:打ち込みとの同期をしたい時のドラマー用モニターミキサーやイヤホンまわりの解説 (ドラムのセッティング)
ヘッドホンアンプ
「クリック音が小さくて聞こえない!
」という場合は、ヘッドホンアンプを使います。
ヘッドホンアンプをイヤホン前につなぐことで、生音に負けないしっかりした音をモニターできるようになります。
ただしイヤホンからの音漏れが、ライブ会場で響き渡ってしまうと……かっこ悪いので音量はほどほどにしておきましょう。
参考:ドラマー用ヘッドフォンアンプ SLICK FLY DH-01
DI・各種ケーブル・キャノンケーブル
打ち込みパートの出力は、基本的にDIを通してPA側へ送ります。
DI(ダイレクトボックス)は、インピーダンス変換したり、アンバランス信号を、バランス信号に変換したりします。
こうすることで高域が減衰したり、ノイズが載りにくくなります。
ダイレクト・ボックス とは、電気楽器および電子楽器をミキシング・コンソールに接続するために用いるインピーダンス変換器である。
レコーディングの現場などにおいて機器の間のインピーダンスの相違を調節し、直接(=ダイレクトに)つなぐ目的で用いられる。
しばしばD.I (ディー・アイ)とも呼ばれる。
ライブハウスなどではDIやキャノンケーブルは常備されているため、こちらでわざわざ用意する必要はないかもしれませんが、ステージセッティングの都合上、持っていると便利な場合もあります。
最低でもイヤホンプラグなどの各種変換ケーブルはこちらで用意しておくようにしましょう。
参考:楽器用ケーブルの種類と特徴。バンドマンのための基礎知識
機材を設置する台・スタンド
ライブ当日に置き場所で困らないように、事前に準備しておきましょう。
リアルタイムで操作する場合も多いので、演奏中にズレたり落ちたりしないように気をつけましょう。
電源タップ
電源を要する機材が多い場合は、あらかじめ電源タップでまとめて準備しておくようにしましょう。
これでセッティングもスムーズに行えるはずです。
リズムガイドをモニターするドラマーの方へ

https://pixabay.com
リズムガイド(クリック)を聴きながら演奏しなければいけないので、リズムキープが大切になります。
打ち込みパートを作成するに当たって、リズムガイドは自分がモニターしやすい音色やパターンを選ぶようにしましょう。
そして何よりその環境に慣れるために、何度も練習を重ねる必要があります。
それでは、ドラムを演奏するにあたって代表的な聴き取りにくい、演奏しにくいクリック音とはどんなものなのかを整理しておきましょう。
- 小説の頭の拍がわからない
- 表の拍、または裏の拍がわからない
- シンバルの打音で一瞬クリック音が聴こえなくなる
- 自分のショット音が全く聴こえない
これらが、問題点として最も多い4点です。
最後に
バンドに打ち込みパートを加えるメリットとしてまず「表現の幅」が広がることが挙げられます。
なにより大切なのは「打ち込みと生演奏が同時に鳴って初めて成り立つサウンド」をイメージすることが重要だと思います。
生演奏の邪魔になっては本末転倒です。
試行錯誤はあると思いますが「ライブのクオリティをより高める手段」として、これを機に1度チャレンジしてみてはどうでしょうか。