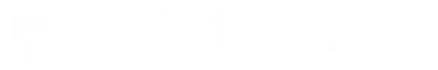奈良の大仏にまつわるクイズ。日本を代表する大仏への理解を深める豆知識
日本の各所にお寺があり、そのいくつかには大仏が建てられている場合がありますよね。
そんなお寺の大仏の中でも、奈良の大仏はとくに有名ではないでしょうか。
今回はそんな日本を代表する大仏と言える、奈良の大仏にまつわる豆知識をクイズにして紹介します。
この日本の象徴的な大仏がどの時代にできたのか、どのような願いか込められているかを知って、奈良の大仏への理解を深めるだけでなく、そのほかの大仏に興味をもつきっかけにしてみるのはいかがでしょうか。
奈良の大仏にまつわるクイズ。日本を代表する大仏への理解を深める豆知識(1〜10)
奈良の大仏の正式名称はなんでしょうか?
- 興福寺大仏
- 盧舎那仏坐像
- 東大寺大仏
こたえを見る
盧舎那仏坐像
奈良の大仏の正式名称は「盧舎那仏坐像」です。この大仏は東大寺の大仏殿に安置されており、盧舎那仏は仏教における宇宙的存在の仏を表しています。盧舎那とは、「照る」という意味があり、すべてを照らし、智慧を与える仏とされています。また、奈良の大仏は国宝に指定されており、日本の仏教彫刻の代表作のひとつです。
誰の発願によって建てられたでしょうか?
- 聖武天皇
- 孝謙天皇
- 藤原仲麻呂
こたえを見る
聖武天皇
奈良の大仏は、聖武天皇の発願によって建立されました。仏教を国の繁栄と安定につなげるため、国家鎮護の思想のもと、東大寺に設置されたこの巨大な大仏は、平城京の象徴的存在であり、歴史的にも文化的にも重要な意味を持っています。
ポーズにはどのような意味があるでしょうか?
- 煩悩や畏れを取り去り、願いをかなえる
- 仏教の教えを広める
- 悪霊などの悪いものを退散させる
こたえを見る
煩悩や畏れを取り去り、願いをかなえる
奈良の大仏様は右手を上げ、手のひらを前に向けている「施無畏印」という印を結んでいます。これは、あらゆる恐れを取り除き、悩みや障害を乗りこえさせてくれるという意味があります。また左手は平らにして、手のひらを上に向けた「与願印」を結んでおり、これは人々の願いをかなえるという意味が込められています。2つの印を組み合わせることで、大仏様は訪れる人々の煩悩や畏れを取り除き、願いをかなえてくれると信じられています。
東大寺は戦火で2回焼失、大仏も含めて再建されてきました。現在の大仏はどの時代に建てられたものでしょうか?
- 鎌倉時代
- 室町時代
- 江戸時代
こたえを見る
江戸時代
東大寺は、過去に2度、戦火で大きな被害を受けて焼失しました。最初の焼失は1180年、その後の再建は1185年に始まる平安時代末期ですが、1692年に再び火災で大仏殿が焼失しました。その後、元禄年間に江戸時代の初期に再建が行われ、現在に至る大仏はその際に再建されたものです。
東大寺の宗派はなんでしょうか?
- 天台宗
- 浄土宗
- 華厳宗
こたえを見る
華厳宗
東大寺は華厳宗に属しています。華厳宗は中国から伝わった仏教宗派の一つで、宇宙的な仏教思想「華厳経」を中心とした教えを広めることで知られています。信仰対象の大仏とともに現在でも華厳宗の大本山としての役割も果たしています。
奈良の大仏の現在の大きさはどれぐらいでしょうか?
- 約5メートル
- 約10メートル
- 約15メートル
こたえを見る
約15メートル
奈良の大仏は、約15メートルの高さを誇ります。この大きさも国内外の多くの観光客をひきつける魅力のひとつですね。建造された当時は約16メートルであったと言われており、再建にともなって少しだけ小さくなっているのはさみしいポイントですね。
大仏の足元の花瓶にとまっている蝶の、実際にはない特徴とは?
- 人間の顔
- 足が8本
- 羽が1対
こたえを見る
足が8本
足が8本という特徴が実際にはないということに焦点を当てています。蝶は昆虫の仲間であり、通常の昆虫の足は6本ですよね。ここであえて足を8本にしていることで、普通ではないもの、神聖なものとしての役割を果たしています。