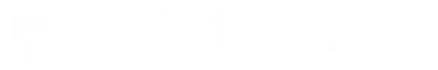自由の女神像に関する面白い雑学。アメリカを代表する象の豆知識
アメリカ合衆国のニューヨーク港にある自由の女神像は、自由を象徴する像として世界中の人びとから親しまれています。
像は観光スポットとしても人気を集めていますが、設置された背景には歴史的なできごとが関係しているので、面白い豆知識がたくさんあるんですよ。
そこでこの記事では、自由の女神像をテーマにした雑学を一挙にまとめました。
圧倒的な存在感を放つ像にまつわるエピソードを紹介していくので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!
自由の女神像に関する面白い雑学。アメリカを代表する象の豆知識(1〜10)
自由の女神のレプリカが日本に存在する
自由の女神といえばアメリカのシンボルですが、実はそのレプリカが日本にあるんです!
場所は東京都港区のお台場で、レインボーブリッジに向かって立っていますよ。
サイズは本物の7分の1で、フランスとの友好の記念として建てられました。
この像が人気となったため、日本にはお台場以外にも自由の女神がいくつか存在します。
また、世界にもレプリカがいくつか存在し、フランスにはアメリカからの返礼品として小さな自由の女神が贈られていますよ。
像の足元には鎖の破片がある
自由の女神のかんむりは世界の大陸と海、右手のたいまつは自由と希望を表しています。
それでは、自由の女神の足元にある鎖の破片にはどんな意味があるのでしょうか。
そもそも自由の女神の足は鎖でつながれているんです。
しかし右足だけは一歩踏み出した状態で、鎖は破片となり散らばっています。
これはさまざまな抑圧や束縛から自由となり、すべての人は平等ということを象徴しているんですよ。
あまり注目しない足元ですが、大切な意味が込められているんですね。
像の正式名称は世界を照らす自由
日本で自由の女神と呼ばれている、たいまつを掲げていることで有名なアメリカのシンボルの像。
実は正式な名前は「世界を照らす自由」と言います。
フランス語では「la Liberté éclairant le monde」、英語では「Liberty Enligtening the World」と書きますよ。
女神となった由来は、フランス語の「Liberté」が女性名詞であること。
自由の女神という名前の像だと思っていた方も多いのではないでしょうか?
ちなみに自由の女神とは、日本独自の呼び方なんですよ。
像はフランスからアメリカに贈られたものである
アメリカのシンボルといえば自由の女神ですよね。
当然、アメリカで制作されたものだと思っている方が多いのではないでしょうか?
しかし実は、自由の女神はフランスから寄贈されたものなのです。
1886年、フランスの彫刻家であるフレデリック・オーギュスト・バルトルディさんがアメリカ独立100周年を記念して制作しました。
ちなみに自由の女神の内部構造の設計には、エッフェル塔を設計したところで知られる、ギュスターヴ・エッフェルさんが参加しているんですよ。
像が緑色の理由は銅が酸化したから
自由の女神といえば緑色というイメージが強いのではないでしょうか?
しかし実はあれは酸化してあの色になっただけで、元は銅でできているんですよ。
アメリカに寄贈された時は銅の色、茶色だったんです。
ではあの緑色は何かといえば、緑青というサビ!
自由の女神が設置されている場所はニューヨーク湾にあるリバティ島ですよね。
つまり潮風で酸化してしまい、あの色になったんです。
知らないと元からあの色だったのかな?と思ってしまいますが、サビとは驚きですね!
かつて像は灯台としても使用されていた
自由の女神はアメリカのシンボルとして知られている像ですが、灯台としての役割を担っていることをご存じでしたか?
現在はもうその役目を終えているそうですが、ニューヨーク湾に到着する船の運航をサポートしていたそうです。
そもそも自由の女神は灯台として使うことを想定されていたため、ニューヨーク港の方を向いているんですって。
女神が手にしているたいまつは灯台としてのものですが、雲との反射で運行に支障をきたすため中止されたそうです。
像が左手に持つ銅板はアメリカ独立記念日が刻まれている
右手には希望の光となるたいまつを持っている自由の女神。
アメリカのシンボルであり、観光名所としても知られていますね。
自由の女神のたいまつは有名ですが、左手に持っている本のようなものが何かをご存じでしょうか?
あれは独立宣言書の銘板で、アメリカ独立記念日の1776年7月4日が刻まれているんですよ。
自由の女神は自由の象徴であり、かぶっている冠や足元のくさりにも意味が込められています。
その一つひとつを知った上で見ると、また印象が変わるかもしれませんね。