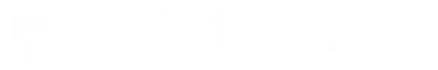思わず誰かに話したくなる!11月の雑学&豆知識特集
秋も深まり、肌寒さを感じる11月。
紅葉狩りやさつまいもなどの味覚狩り、七五三や文化の日など、日本の伝統行事や旬の楽しみがたくさん詰まった季節ですよね。
そんな11月には、身近なところに驚きの豆知識がたくさん隠れているのをご存じですか?
各行事に関する歴史や、旬の味覚に関すること、紅葉の雑学まで。
この記事では、思わず誰かに話したくなる一般向けの11月にまつわる雑学&豆知識を紹介します。
知れば知るほど奥深い、11月の魅力を一緒に探っていきましょう!
思わず誰かに話したくなる!11月の雑学&豆知識特集(1〜10)
イチョウは恐竜がいた時代からあった
イチョウの木は恐竜が地球を歩いていた時代から存在していた生きた化石と呼ばれる植物です。
大昔から姿をほとんど変えずに生き残ってきたのは、環境への適応力が非常に高いことも影響しています。
現代の街路樹として親しまれているイチョウ並木を眺めるとき、恐竜の時代の景色と重ね合わせると不思議な時間のつながりを感じられるでしょう。
秋の黄色に染まった葉は美しいだけでなく、長い歴史の証でもあります。
身近にあるのに壮大なスケールを秘めている雑学です。
千歳飴は長さ1m以内、直径1.5cm以内と決められている
七五三に欠かせない千歳飴には、実はきちんとした規格があります。
長さは1メートル以内、直径は1.5センチ以内と決められており、その細長い形には長寿や健やかな成長の願いが込められているんですよ。
子供の健康を祈る縁起物として親しまれ、紅白の色合いがさらにおめでたさを際立たせます。
普段はただ甘い飴として受け取っていたものにも、実は深い意味と歴史が隠されていることに気づくと七五三の行事がより特別に感じられるでしょう。
知るだけで誰かに話したくなる雑学です。
「小春日和」は11月頃に使われる言葉
春の陽気を思わせるフレーズですが、実際に使われるのは11月頃の小春日和。
旧暦で10月から11月を小春と呼んでいたことから、晩秋から初冬にかけての暖かく穏やかな日を指します。
冬に向かう中で一時的に訪れる優しい日差しに、春を感じるような温もりを覚えることから生まれた表現です。
誤って春に使ってしまう場合も考えられますが、正しい意味を知ると季節の言葉の奥深さに気づけます。
日本人の自然に向けた感覚や風景が思い浮かぶ、季節を味わう豊かな雑学です。
もみじの花言葉は「美しい変化」
秋を代表するもみじには美しい変化という花言葉があります。
春から夏には青々とした緑の葉をしげらせ、秋になると鮮やかな赤や黄色に装いを変える姿が、人の成長や人生の移ろいに重ねられてきました。
散りゆく瞬間さえも美しく、はかなさの中に力強さを感じさせます。
鮮やかに色づいたもみじを目にすると、この花言葉を知っているだけで一層深い感動を覚えられ、自然の持つ表情の豊かさを改めて感じられるでしょう。
変化を受け入れる大切さを伝えてくれる味わい深い言葉です。
「勤労感謝の日」は戦前は「新嘗祭」と呼ばれていた
新嘗祭は、その年の新穀を神様に供え、収穫に感謝する日本の伝統的な儀式です。
「勤労感謝の日」が11月23日になったのには、かつて新嘗祭がおこわれていた日だからとされております。
天皇陛下が自ら新穀を神前にささげ、その年の豊作を感謝し、国の安泰を祈るという、非常に重要な宮中行事でした。
新嘗祭は戦後、国民の祝日として「勤労感謝の日」に生まれ変わりました。
勤労感謝の日は単なる休日ではなく、私たちの日々の生活を支えてくれている人々や自然の恵みに感謝する大切な日ですね。
本来咲く季節ではない秋に花が咲く花を「帰り花」という
本来咲くべき春や夏ではなく、秋にふと咲いてしまった花のことを指す帰り花。
気温の変化や天候の影響で花が季節を間違えたように咲く姿は、どこか儚げでおもむきがあります。
冬に向かう冷たい空気の中で咲く花は自然のいたずらともいえる光景であり、古くから俳句や和歌の題材としても親しまれてきました。
季節外れに咲く一輪の花に出会うと、不思議な気持ちとともに自然の力強さを感じさせます。
秋の情緒を深く味わえる、日本の自然豊かな風景が広がる風流な言葉です。
祝日である「文化の日」の制定は、日本国憲法が公布されたことに由来する
1946年11月3日に日本国憲法が公布されたことから、11月3日が「文化の日」と言われるようになりました。
日本国憲法の公布は戦前の国家主義的な体制から、民主主義国家へと生まれ変わった日本において大きな出来事でした。
文化の日になると各地で博物館や美術館の無料開放や音楽会などが開かれています。
文化の日は単なる祝日ではなく、私たちが平和で豊かな社会を築くために日本の文化の大切さを再認識する日ですね。
この機会にぜひ日本の歴史ある文化に触れてみるのもオススメですよ。