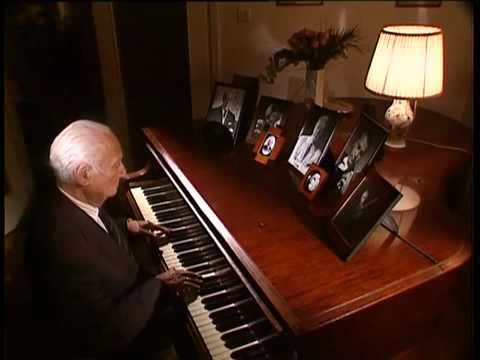Frederic Chopinの人気曲ランキング【2026】
ポーランド生まれでフランスでも活躍した作曲家のFrederic Chopin(1810-1849)。
彼は若くして亡くなりましたが、多くの名曲を世に送り出しました。
今回は彼の手がけた作品の中でも人気のある曲をセレクトしました。
- ショパンの名曲。人気のクラシック音楽
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- Franz Schubertの人気曲ランキング【2026】
- 【高難度】ピアノの詩人ショパンの難しいピアノ曲を一挙紹介!
- Scott Joplinの人気曲ランキング【2026】
- Franz Lisztの人気曲ランキング【2026】
- Johann Burgmüllerの人気曲ランキング【2026】
- César Franckの人気曲ランキング【2026】
- Sergei Rachmaninovの人気曲ランキング【2026】
- Cécile Chaminadeの人気曲ランキング【2026】
- Ludwig van Beethovenの人気曲ランキング【2026】
- Gabriel Fauréの人気曲ランキング【2026】
- François Couperinの人気曲ランキング【2026】
Frederic Chopinの人気曲ランキング【2026】(1〜10)
練習曲 作品10-3「別れの曲」Frederic Chopin8位

『別れの曲』として知られている、フレデリック・ショパン作曲の『練習曲 作品10-3』。
ショパンは、テクニック的な要素に加え、高い芸術性を備えたピアノのための練習曲を27曲手掛けていますが、なかでもこの曲は美しいメロディと親しみやすい曲調で人気の高い作品の一つとされています。
ショパンの練習曲のなかでは、比較的難易度の低い楽曲ですが、細かなテクニックの練習は必須です。
しかし、指の動きだけにとらわれて機械的な演奏にならないよう、メロディのなめらかさや中間部の曲調の変化などを意識して弾けるとよいでしょう。
別れの曲Frederic Chopin9位

フレデリック・ショパン自身が「こんな美しい曲は書いたことがない」と語ったというエピソードが残されているほど、非常に美しいメロディーと和声を持つ『別れの曲』。
ドラマやCM、映画などでたびたび使用されている穏やかな部分の間に、性格の異なる明るく快活な部分が挟まれています。
「別れの曲を弾けた!」といううれしさを実感できるのは、やはり有名な前半と後半のフレーズではないかと思います。
シンプルなアレンジの楽譜で、作曲者も自画自賛の美しい音楽を堪能してみてはいかがでしょうか?
ワルツ 第4番 ヘ長調Frederic Chopin10位

快活な曲調から『子猫のワルツ』とも呼ばれている『ワルツ 第4番 ヘ長調 作品34-3』。
ネコが走り回って遊んでいる光景が目に浮かぶような、かわいらしい作品ですよね。
発表会曲やコンクールの課題曲として取り上げられることも多く、演奏効果の高い曲として親しまれています。
冒頭部分のアルペジオは高らかに堂々と、そして、キラキラと輝くような右手の細かなパッセージは、明るくクリアな音で演奏しましょう。
左手の伴奏は、とにかく軽やかに前向きに弾けるよう、片手の練習も丁寧に行ってみてくださいね。
Frederic Chopinの人気曲ランキング【2026】(11〜20)
アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22Frederic Chopin11位

管弦楽とピアノによるポロネーズ部分と、ピアノ独奏のアンダンテ・スピアナート部分からなるフレデリック・ショパンの『アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22』。
鍵盤の上をなでるような繊細なタッチ、体の重みをピアノに伝えるように弾く重厚なタッチなど、さまざまなタッチと音色を使い分けが必要な、高度なテクニックと緻密な感性を要する難曲です。
だからこそ、自分なりの「美しい演奏」を完成させられた際には喜びもひとしお!
まさにまわりから「かっこいい!」と言われること間違いなしの1曲といえるでしょう。
ワルツ 第1番 変ホ長調 Op.18「華麗なる大円舞曲」Frederic Chopin12位

フレデリック・ショパンの華麗なワルツは、愛を誓い合う結婚式にぴったり。
1833年に作曲され、翌年に出版されたこの曲は、ショパンのワルツ作品群のなかで最初に世に送り出されました。
華やかな変ロ音のファンファーレから始まり、5つの部分で構成された曲調は、新郎新婦の門出を祝福するかのよう。
後にバレエ『レ・シルフィード』でも使用されるなど、多くの人々に愛され続けています。
大切な2人の幸せな瞬間を彩るピアノ演奏として、ぜひ選んでみてはいかがでしょうか。
練習曲 Op.25-1「エオリアンハープ」Frederic Chopin13位

演奏を聞いていると難しく聞こえていますが、その中でも優しそうな1曲を紹介します。
それがフレデリック・ショパンの有名な練習曲『練習曲 Op.25-1「エオリアンハープ」』です。
『牧童』ないし『牧童の笛』という名前でも知られている作品で、ショパンの作品のなかでは中級者の登竜門のような存在として知られています。
楽曲全体を通じて奏でられる分散和音の音色が特徴で、テクニックだけでなく高い表現力が求められます。
広いアルペジオ部分はテンポやタッチの揺れが起きやすいため、そこを意識しながら仕上げましょう。
ノクターン 第20番 嬰ハ短調「遺作」Frederic Chopin14位
フレデリック・ショパンが1830年に作曲したノクターン。
全21曲からなるうちの、第20番は、姉のルドヴィカへの献呈とともに、『ピアノ協奏曲第2番』の練習用として書かれました。
ショパンの死後21年たった1875年に出版されたため、『遺作』と名付けられています。
レント・コン・グラン・エスプレッシオーネの穏やかなテンポで、左手の分散和音に対して右手が情感豊かな旋律を奏でる構成。
序奏部、中間部、再現部の三部構成で、美しい旋律と華やかな装飾音がメランコリックな雰囲気を引き立てています。
ショパンの内面的な感情や思索が反映された本作は、繊細な音色を味わいたい方にオススメです。