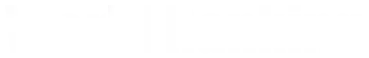洋楽の泣ける歌ランキング【2026】
洋楽の泣ける歌のランキングから視聴回数が多い順に最新のランキングトップ100を一挙に紹介します!
感動できる歌、悲しい歌、ときにはそんな曲に身を任せて思いっきり泣いてしまってはどうでしょう。
ストレスの発散、次に進むきっかけにしてみてください。
プレイリストも毎週更新中です。
洋楽の泣ける歌ランキング【2026】(1〜10)
Lose You to Love MeSelena Gomez1位

失恋の痛みを通して自分自身を取り戻していく軌跡を描いた、セレーナ・ゴメスさんの代表的バラードです。
2019年10月にアルバム『Rare』のリード・シングルとして発表され、彼女にとって初となる全米ビルボード・チャート1位を獲得しました。
ミニマルなピアノと生々しいボーカルだけで始まる冒頭から、ストリングスとコーラスが重なっていく構成は、傷ついた心が少しずつ回復していく過程そのものを表現しているかのようです。
本作に込められた「あなたを失うことで、ようやく自分を愛せるようになった」という逆説的なメッセージは、別れを経験したすべての人の心に深く響くでしょう。
感情を剥き出しにしたくなるほどつらい経験をした方にこそ、静かな強さを感じさせるこの一曲を聴いてほしいですね。
PhotographEd Sheeran2位

曲名の「写真」から連想されるように、家族みんなが写っている写真をアルバムにして家の奥深くに大切にしまってあるようなイメージです。
「あなたの帰る場所はここにあります」と言ってくれている温かみのある曲です。
The Heart Wants What It WantsSelena Gomez3位

この曲の冒頭で、Selena Gomez本人のボイスノートが収録されていて、そこには馬鹿みたい、あなたは全て私のせいにしていると言っておりおそらく長年交際していたJustin Bieberについての曲だと言われています。
One Last TimeAriana Grande4位

甘く切ない歌声が心の奥深くまで響き渡る、失われた恋の最後の一夜を願う女性の思いを描いた珠玉のラブソング。
ボーカルのAriana Grandeさんの、感情豊かな歌声が楽曲の魅力を存分に引き出しています。
2015年2月にアルバム『My Everything』からリリースされた本作は、ダンスポップとEDMの要素を巧みに融合させた楽曲です。
「もう一度だけ、あなたを家に送りたい」という切実な願いが込められた歌詞は、失恋した誰もが共感できる内容。
大切な人との別れを受け入れられずにいる方や、過去の恋を思い出したい方におすすめの一曲です。
See You Again ft. Charlie PuthWiz Khalifa5位

心に深く刺さる友情への想いが込められた珠玉のバラード作品です。
アメリカ出身のラッパー、ウィズ・カリファさんとチャーリー・プースさんによる感動的なコラボレーションは、親しい人を失った悲しみと再会への希望を美しく歌い上げています。
2015年3月に映画「ワイルド・スピード SKY MISSION」の主題歌として制作され、故ポール・ウォーカーへの追悼の意味も込められました。
本作はビルボード・ホット100で12週連続1位という驚異的な記録を樹立し、世界中の人々の涙を誘いました。
大切な人との別れを経験した方、家族や友人との絆を改めて感じたい方に特におすすめしたい一曲です。
Tears In HeavenEric Clapton6位

あまりにも深い喪失感の中から生まれた、鎮魂歌のようなバラードです。
イギリス出身の伝説的ギタリスト、エリック・クラプトンさんの楽曲です。
若くして亡くした我が子へ、天国で再会したら自分のことがわかるだろうかと問いかける、そのあまりに純粋な想いが胸を締めつけます。
アコースティックギターの静かな調べは、悲しみの中に灯る小さな希望の光のようです。
この楽曲は1992年1月に映画『Rush』の主題歌として公開され、ライブ・アルバム『Unplugged』は全世界で2600万枚以上を売り上げました。
どうしようもない悲しみに暮れる夜に、聴いてみてはいかがでしょうか。
Thinking Out LoudEd Sheeran7位

イギリスを代表する世界的シンガーソングライター、エド・シーランさんによる珠玉のバラードを紹介します。
2014年に発売された名盤『×』に収録されている本作は、穏やかなギターの音色とソウルフルな歌声が魅力です。
愛する人と共に年齢を重ね、70代になっても変わらず愛し続けるという永遠の誓いが込められた歌詞は、聴く人の涙腺を刺激しますよね。
全英チャートのトップ40に52週連続でランクインし続けるという、史上初の快挙を達成したことでも知られる名曲です。
大切な人を想って静かに泣きたい時や、心温まる愛の歌に浸りたい時にぴったり。
ミュージックビデオでのダンスも感動的なので、ぜひチェックしてみてください!