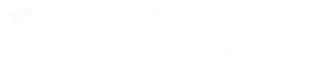【小学生向け】3月にまつわる雑学まとめ
3月にはひな祭りやホワイトデーなどの行事があるほか、春がやってくる季節でもありますよね。
この記事では、そんな3月にまつわる雑学を小学生向けに一挙に紹介していきますね!
小学生の方にもなじみのある事柄を中心に、昔ながらの文化にまつわるものから花や動物などの自然にまつわるものまで、幅広い雑学を選びました。
きっとまだご存じでない雑学もあると思いますので、ぜひこの機会に覚えていただき、お友達や家族に自慢してくださいね。
それでは楽しみながらご覧ください!
- 3月にまつわる雑学クイズ。行事や風物詩についての問題まとめ
- 【小学生向け】4月にまつわる雑学まとめ
- 学校にまつわる雑学クイズ。自慢したくなる豆知識まとめ
- 【桜クイズ】子供向けの桜に関する雑学&豆知識クイズ
- 桜に関する豆知識。春のお花見が楽しくなる雑学まとめ
- 花粉症にまつわる雑学。対策にもなる豆知識
- 【常識&雑学】小学生向け知識になるマルバツクイズ
- 【子供向け】12月の雑学クイズ&豆知識問題!行事や季節のことを学べる!
- 【どこまで知ってる?】小学生向け 食べ物クイズ
- 知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学
- 【子ども向け】3月にオススメ!ひな祭りや卒業式など簡単折り紙アイデア集
- 小学生にオススメの春にぴったりの絵本。小学校が楽しみになる絵本
- 2月の雑学クイズ。節分やバレンタインなど季節の豆知識を3択で出題
【小学生向け】3月にまつわる雑学まとめ(1〜10)
3月は弥生のほかに、花月や桜月とも呼ばれる
3月になると、寒さよりも暖かさを感じる日が多くなりますよね。
3月は弥生という別名で呼ばれることは有名で、カレンダーにも書かれていることもあるのでご存じの方が多いのではないでしょうか。
しかし、弥生以外にも花見月や桜月と呼ぶこともあるんですよ。
3月はどちらかというと桃の花のイメージがありますが桜を使う表現には理由があります。
日本はかつて、月の満ち欠けで一カ月を決める旧暦を使用していました。
旧暦の3月は現在の4月ごろを指すので別名に桜がつくようになったそうですよ。
ほかにも花月や花咲月などもあります。
今回の記事をきっかけにして、12カ月の呼び方を調べてみてはいかがでしょうか。
うぐいす色と実際のウグイスの色は異なる
ウグイスの鳴き声は、春が来たことを知らせてくれるようですよね。
うぐいす色のお菓子やパンなども、春になると目にすることが多くなります。
うぐいす色の鮮やかな黄緑色に、新緑など爽やかな気持ちになるのではないでしょうか。
ですが、実際のウグイスの体色とうぐいす色には違いがあるようです。
実際のウグイスは茶色っぽい色で、光の加減では緑色にも見えることもあります。
一方でうぐいす色は鮮やかな黄緑色ですよね。
このような違いが生まれた理由には諸説ありますが、鮮やかな黄緑色で眼のふちが白い鳥のメジロとウグイスを間違えた説などが挙げられます。
ウグイスの鳴き声が聞こえたら、ぜひこの雑学で盛り上がってみてくださいね。
たけのこは1日で1m以上も伸びることがある
たけのこは春の味覚の一つ。
有名なチョコレートのお菓子にもなっているので、小学生もたけのこのイメージが浮かびやすいですよね。
調理に使う際のたけのこは、コロンとしたかわいらしい姿ですが、地面から生えているたけのこは1日に1m以上伸びることもあるそうですよ。
竹の若芽であるたけのこは成長スピードがとても速いんですね。
ちなみに、地表に出る頃は一日に数cmから数十cm伸びますが、日を追うごとに成長スピードを速めていきます。
【小学生向け】3月にまつわる雑学まとめ(11〜20)
沖縄と北海道では花粉症にならない
くしゃみや鼻水がでるなどの症状に悩まされる花粉症。
年々、花粉症になる小学生も最近は増えています。
実は沖縄と北海道では杉による花粉症になる可能性が低いんです。
理由は、沖縄と北海道には人工で植えた杉林がほとんどないことが原因です。
戦後の復興や都市開発により多くの材木が必要になり、国は杉の人工林を多く植えました。
海外から安く材木が手に入るようになり、日本の杉の需要が低下し、多くの人工杉林が残る状態に。
残っている多くの杉が、花粉をまき散らし花粉症を悪化させているそうですよ。
つくしは筆ににていることから漢字で「土筆」と書く
地面からひょこりとかわいい頭を出して、生えているつくし。
つくしは漢字で「土筆」と書きますよ。
「土」も「筆」もつくしに関する読み方はありません。
日本独自の当て字で、つくしの生えている様子からきているそうですよ。
筆が土から生えてきているように見えることから「土筆」となったそうです。
最近ではつくしを見る機会があまりない地域の方もいるのではないでしょうか。
春の雑学とともに、図鑑で調べたり郊外へ出かけてみるのもオススメですよ。
ひし餅は心臓の形を模したと言われている
3月の桃の節句に、おひな様を飾るご家庭もあるのではないでしょうか。
ひな人形にはひし餅やひなあられ、甘酒などをお供えしたり、いただきますよね。
中でもひし餅は、ひし形で緑、白、ピンクの3色が特徴。
実はひし餅は心臓の形を模したものといった説がありますよ。
中国発祥の風水学では、心臓の形はひし形をしているそうです。
命をイメージする心臓と同じ形にしたひし餅を食べることで「強い生命力が宿る」と考えられました。
桃の節句は子どもの健康を願うお祭りなので、縁起のよいひし餅も飾ることになったそうですよ。
ホワイトデーにマシュマロを渡すと「嫌い」というメッセージになる
3月14日はバレンタインデーのお返しをするホワイトデーです。
お店ではお返し用のお菓子などが販売されていますよね。
お返しにマシュマロというと定番ですが、マシュマロを贈ると嫌い、やお断りの意味になるといわれているそうです。
マシュマロは口の中に入れると溶けて消えてしまいます。
消えてしまうことから「関係は続かない」ということにつながるそうです。
しかしホワイトデーの由来を知るとマシュマロを贈るイメージが変わりますよ。
実はホワイトデーのきっかけになったお菓子はマシュマロなんです。
もともとはマシュマロでチョコレートを包み「もらったチョコレートを優しい気持ちで包む」といった温かな意味があったそうですよ。