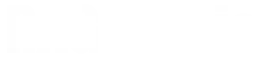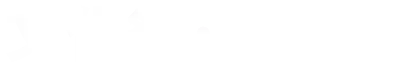【小学校向け】文化祭にオススメの出し物・レクリエーション
小学生が楽しみにしている行事の一つ、文化祭。
「ふれあい祭」や、学校名を入れて「◯◯発表会」などと独自の名前で開催されることもありますね。
この記事では、小学校の文化祭にぴったり!
クラスが一体となって楽しめる出し物、レクリエーションを紹介しています。
クラスの教室でおこなえる出し物から、体育館やグラウンドなど広い場所で楽しめるレクリエーションなど、いろいろなアイデアを紹介していますよ。
なかなかアイデアが決まらない時は、よければ参考にしてみてくださいね。
【小学校向け】文化祭にオススメの出し物・レクリエーション(1〜10)
ジェットコースター

「文化祭に大きな目玉がほしいなあ」とお考えの方にオススメなのがジェックコースターです。
「ジェットコースターなんて作れるの?」と思う方もいるでしょう。
もちろん小学生の力だけで作るのは少し難しいかもしれませんが、大人の方が中心になって作れば夢のような話でもありません。
木でジェックコースターが進む枠を作り、乗り物は四角い大型バケツの底に車輪を取り付けるだけでOK!
コツはあまり大きなものを作らないこと。
1度のカーブ、あとは直線のみ、そんな簡易的なコースでも楽しさは十分に伝わりますので。
動画サイトにアップされている手作りジェットコースターもぜひ参考にしてくださいね。
スラックアウト

思いっきり体を動かして楽しめるスラックアウトはいかがですか?
スラックアウトというのは1から9までの番号が振られたパネルが枠にはまっていて、そこめがけてボールを投げるというゲームです。
ただ体を動かすだけでなく、どこを狙おうかなと考えながら取り組めるのが魅力ですね。
また、どれだけ的に当てられるか記録を競えるので、お友達と取り組んでも盛り上がりそうです。
ちなみにスラックアウトは段ボールでも作れますよ。
1度作れば翌年以降も使えるので便利です。
宝探しゲーム

秘密兵器ともいえる盛り上げイベントといえば「宝探し」。
旅行サイトの「じゃらん」で検索してみても、宝探しのできる全国の観光スポット、もう本当に全国各地にあります。
町おこしのイベントで宝探しを開催している自治体もあるんですよ。
純粋に宝を探す形式でも、いまはやりの謎解きを組み合わせたものでも、盛り上がることは間違いないです。
体力や学年で差が出ない工夫さえしっかりすればあとは楽しむだけだと思います!
また地域学習や総合学習の一環としても利用できそうです。
茶道体験

豊臣秀吉さんの側近ともなった茶聖、千利休さん。
諸説ありますが、そのカリスマともいえる影響力を恐れ、最後は秀吉さんに切腹を命じられたとか。
茶の道だけにまい進していた?
わけではなかったんですね。
高校には茶道部もあるかと思いますが、小学生にとって茶道はやや縁のないなもの。
そこで、茶道体験の催しを用意するのはどうでしょう。
簡単な作法さえ覚えれば結構自由度のあるお茶の道、きっと小学生でも楽しめると思います。
苦いお茶に添えられた和菓子も魅力的なんですよね!
魚つり

画用紙で作った魚たちを釣り上げる、魚つりゲームはどうでしょう。
魚には金属製のクリップをつけておき、磁石のついた釣ざおでフィッシング。
「制限時間内に何匹釣れるか」などをルールにして、成功したら賞品がもらえるという仕組みにすれば、とても盛り上がると思います。
魚を作るという工作的な楽しみ方もできて、もちろん遊んでもおもしろい、いろいろな角度からの魅力を持ったアイデアではないでしょうか。
目指せ、学校一の釣り名人!
◯◯かるた大会

かるたは昔からある遊びの一つで、スポーツ競技として大会もおこなわれていますよね。
そんなかるたを、文化祭の出し物としておこなってみるのがいかがでしょうか。
昔の遊びに触れる機会として催しても良いですし、実際に参加者同士で勝負しても良いですね。
ただかるたするだけでは……と思われる場合は、その地域の特産品などをテーマにオリジナルかるたを作ってみるのもオススメですよ。
テーマを身近なものにすれば、かるたを知らない子供たちも興味を持ってくれるかもしれません。
赤ちゃん写真当てクイズ

ワイワイ盛り上がれる赤ちゃん写真当てクイズもオススメです。
こちらはモニターやスクリーンに赤ちゃんの写真が映し出され、それが誰かあてるという内容です。
「僕だったのか」とおどろきや発見があるかもしれませんね。
また成長を実感するきっかけにもなりえるでしょう。
スケジュールや会場にもよりますが、可能なら全員の写真が登場するという風にした方が楽しめるかもしれません。
それから写真を表示するのは静止画ではなく、動画での方が盛り上がりますよ。
サーキット

体育館や校庭でオススメな、思いっきり体を動かせるアトラクションが、サーキット。
ミニハードルや三角コーンなどを活用して作る、コンパクトな障害物競走みたいなレクリエーションです。
リズミカルに跳んだり、スピーディーに駆け抜けたり、運動好きなお子さんならとくにハマってくれそう。
ハードルの高さや物同士の距離感を変えて、簡単に難易度調整が可能なので、いくつかのコースを作っての選択式にするのがいいかもしれません。
演劇

発表会の定番の演目といえば演劇ではないでしょうか。
みんなで取り組む一体感を感じられますし、見ている人も次はどうなるのかなとワクワクできるのが魅力です。
まずは先生が台本を制作し、それに合わせて配役や役割を決めていきましょう。
「どうしたらうまく演じられるかな」、「どうしたらより楽しんでもらえるかな」さまざまな視点から考えることで工夫する力が身につくでしょう。
また1つの作品に取り組むことで、結束が強まりそうです。
マルバツクイズ

みんなでクイズを楽しみたいという場合には、マルバツクイズがピッタリです。
こちらはご存じの通り、出題されたクイズにマルかバツで答えるというルールです。
体育館など広い空間を2つに分け、それぞれを〇のエリアと×のエリアに分け移動することで答えてもらうのもありです。
そして正解した人だけが残るという風にしていけば、ゲーム性も高まります。
わかりそうでわからない、絶妙な難易度の問題を考えてみてください。
また答えを知っておどろけるような問題も盛り上がります。