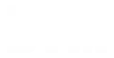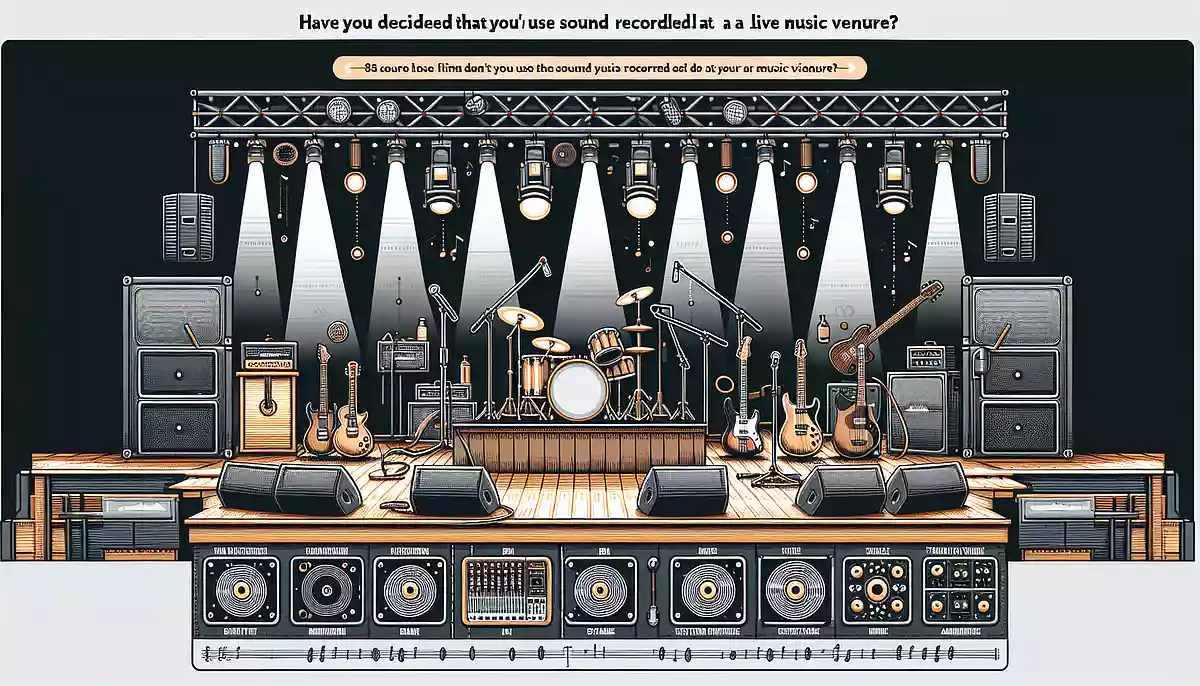音楽活動をしていればライブハウス出演することもあるでしょう。
出演時に申し込む機材レンタルのオプションに、出演時のステージパフォーマンスをビデオやCDなどに収録してくれるサービスがあります。
それらは多くの場合、自分たちのパフォーマンスや演奏ミスをチェックする最低限のツールとして活用するに留まります。
それが済んだら捨てないにしても、引き出しやクローゼットにお蔵入りしてしまうケースがほとんどです。
そんなライブハウス録音した音源が人に聞かせても恥ずかしくない「音質」にできればさまざまな利用価値が生まれます。
YouTubeにUPしたり、オーディション用音源、演奏の出来が良ければ安価で販売できるかもしれません。
そんなハイブリッド音源の作成法を紹介します。
- 【低音】高難易度なベースが聴ける邦楽まとめ【かっこいい】
- 【低音】ベースソロが光る邦楽曲まとめ【2026】
- カラオケが上手く聞こえる曲
- カラオケで歌うとかっこいいヒップホップ|歌うコツも解説!
- 【男性向け】ミックスボイス練習曲・高音が出やすくなる参考曲
- 【2026】バンド初心者へ!ライブで盛り上がる人気バンドのおすすめ曲
- 【音痴でも大丈夫!】カラオケで歌いやすい曲・練習曲を紹介
- 【男性向け】歌が上手くなる曲はこれ!カラオケ練習に効果的な楽曲
- 【苦手な人も必見】カラオケで歌いやすい曲
- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】
- 【男性向け】声が低い方でも高得点が狙えるカラオケ曲
- 裏声が多い曲を歌いたい。カラオケで裏声の練習にもなる楽曲
- 人気曲のアコースティック・バージョン。アレンジやカバー曲まとめ
蔵入りしてしまうライブハウス音源の特徴
- 迫力がない&スカスカ
- 楽器のバランスが悪い&臨場感の欠落
- 気持ちよくない&なぜかチープさが増し違和感がある
聞いていて気持ちよくない音は繰り返し再生する気にはなれません。
音に自信を持つバンドほど、チープさがデフォルメされた微妙な音源は死んでも聞かせたくないもの(笑)。
特に重圧なサウンドと音圧が魅力となっているロックバンドには致命的問題。
YouTube公開時、歌が中心の「弾き語り」なら妥協できても、バンドの場合はその音楽自体が台無しになる。
PA卓のデジタル化も進み、会場でのPAバランスに左右されることなく録音ができるようになりました。
エア録音などとミックスされ以前と比べてその音も改善しています。
しかし空気感を損なうライン録音は根本的な欠点を解消するのが難しい。
YouTube投稿されたバンド動画の主流はエア録音
YouTubeに積極的に動画投稿しているバンドは、最近の音楽用ビデオレコーダーを利用してのエア録音によるものが多いです。
ライン録音に比べて違和感が少なく、ある程度のクオリティで配信するには便利です。
しかし、ちょっと歌が聞こえにくくなったり、収録位置が悪くて空調のノイズなどをまともに拾ってしまうこともあり、素人的なサウンドを脱却するにはプロレベルの入念なセッティングが必要です。
ライン録りの方が「使える音源」として抜本改善できる可能性が高い
ライブハウスで多く利用される「ライン録り」は空気感や音圧がなくなってしまうことが独特の「ショボさ」につながっています。
その弱点を改善すれば、ノイズが少なくエア録音では得られないかっこいいハイブリッド音源に生まれかわる可能性が高い。
- 空気感
- 音圧感
これらをいい感じ肉付けするのがポイントです。
実際には高い音圧を出しているベース&ドラムのブースト、楽曲の中心であるボーカルが気持ち良く聞こえるバランスを目指します。
DAWでいい感じのライブ音源にする作成方法

オリジナル曲を演奏するバンドならメンバーがProToolsやCubase、LogicなどのDAWを所有しているでしょう。
ライン録りの音源をDAWに取り込みハイブリッド音源加工に挑戦してみましょう。
レコーディング時のダイナミクス系エフェクト(コンプレッサー、リミッター、マキシマイザー)を的確に使いこなせればいい感じに仕上げられます。
意図的に各種パラメーターを調整できることがおおよその基準。
繊細なセッティングが必要となり、長くバンドをやっていても楽器用のエフェクターしか使ったことがない人やDAWのプリセットだけで音楽制作している人にはやや敷居が高いかもしれません。
「コンプかけてドンシャリにすればいいんでしょ」と、簡単に結論づける方がいますが、以下の方法で細かく音作りした音とは雲泥の差が出ます。
変なノイズが入っていない奇麗な音源でしたら、ざっくりと以下のプラグインをインサートして加工してます。
オーディオリペアツールを用いた事前のノイズ処理テクニックもあれば入念にします。
コンプやマキシマイザーでさらにノイズが強調されてしまうので。
エフェクトルーティンと各エフェクト設定のポイント
(ルーティン例)EQ→コンプ→リバーブ→マルチバンドコンプ(→エンハンサー ※ステレオイメージャー)→エキサイター→EQ→マキシマイザー
EQ
カットを中心に各パートの楽器が位置する帯域を補正して音像のバランスを細かく調整していきます。
ライブ音源は超低音部に余分なノイズ成分も多く乗りがちなので、軽くローカット(30Hz前後のポイント)をしておきましょう。
コンプ
全体的にピークをつぶしてまとまり感を強めていきます。
ロック系はここでかなりつぶしてしまった方が良い場合もありますが基本はあまりつぶしすぎずにアタックを20ms以上リリースも100ms前後で歌や大きなピーク音を抑える感じで使用するのがベターです。
ビンテージ系のプラグインで積極的に色をつけていくのもおすすめ。
リバーブ
ライン録音はリヴァーブ自体も録音されていますが、空気感が薄れてしまうことが多いのでここでほんのり入れるとぐっと臨場感が向上します。
4〜15%くらいの割合でブレンドさせていきます。
音作りによりインサートする位置は変更した方が良い場合があります。
映像が有る場合はハコのサイズを想定したクラブを模したセッティングが良いが、プロっぽく仕上げるならやはりホール系が雰囲気を作りやすい。
マルチバンドコンプ
3つか4つの帯域ごとにコンプレッションができますが、ここではつぶすことよりも帯域ごとの強弱を調整していきます。
ライブでズンズンいうベースやキックドラムを強調したいならEQ処理で無理やり加工するより、ここで中低域をブーストした方がいい感じになります。
歌の聞こえ方ともバランスをとり、中低域を2〜5dbくらいブーストするといい雰囲気が出ます。
ボーカルバランスが大きすぎる時は中高域のスレッショルドを低めに抑え込み、コンプの効きを強めに設定し抑えます。
全体的にブースト処理ばかりしてしまうと、音が洪水してしまいますので、頭に通したEQでカット中心の処理しておくことがポイントです。
エンハンサー(ステレオイメージャー)
全体の音像をなじませるためにエンハンサーなどを調整しましょう。
ステレオ音像をコントロールできるステレオイメージャーでしたら、ベースやキックドラムの帯域はセンター位置にタイトに、歌のリバーブ成分やギターなどの成分(中高域)はやや広げるイメージに調整するとまとめやすいです。
エキサイター
抜けの悪い楽器などがありましたら、その帯域にエキサイター(その他サチュレーション)で色付けを加えます。
センターやサイドごとに調整できるプラグインもあるので、楽器が位置しているポイントを重点にエディットします。
ボーカルの抜けが悪い場合はシンプルにセンター音像の声成分(中域〜中高域)に微細な色を付ける作業で一気に良くなります。
EQ
マキシマイザーをインサートする直前にEQで音を整えましょう。
未調整でいい感じになればそれで問題ありませんが、暴れすぎた音像を抑えたり少し強調したい部分をこの段階で最終的な微調整を行います。
キックドラムとベースが被る85〜110Hzの帯域をQを強めに設定し、一気にボトムのグレードができるカット部分を探ります。
-0.2〜0.4dBくらい。
マキシマイザー
最終的な音圧調整のためにマキシマイザーを使用します。
プラグインごとに調整できるパラメーターが異なり一概のセッティングはありません。
入ってくる音像の下処理が大切なので、直前にインサートされたEQ調整を対にして作業し。
派手につぶしすぎないことがポイントです。
大きくはマスタリングと呼ばれる音処理工程に近いのです。
きちんとレコーディングされた音源に比べ、ライブは音像やノイズが暴れており、録音に関する下処理が何もない状態からスタートしますので、そのアプローチは調整というよりも大胆な加工という考え方で進めていきます。
ライブハウスでライン録音(2016年)された音をパンチあるサウンドへ
まとめ
マルチレコーディングされた最新のライブ音源より劣りますが、ぐっと聞けるサウンドに加工できます。
1曲ずつ仕上げるマスタリング作業のような手間をかける必要はありません。
ライブ収録したビデオ音声を処理することで、擬似的なライブアルバムが作れます。
YouTube投稿のネタ、簡易的な配布音源としても利用ができるクオリティ。
エア録音よりずっと聴きやすく、ライブハウスならではのエッセンスも感じられます。
YouTubeは多くの曲をUPすればするほど、SEO効果が期待できます。
生バンドがベストな音源(正式なレコーディング)を量産するのは経済的なことやスケジュールも含め、簡単ではありません。
せっかくのライブパフォーマンスを効率的に活かしきることを考えてみてはいかがでしょうか。