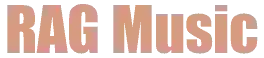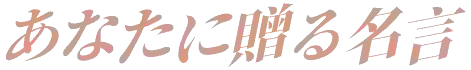AI レビュー検索
プラトン の検索結果(1〜10)
自分に打ち勝つことが、最も偉大な勝利である。プラトン
古代ギリシャの哲学者であったプラトン、その思想は西洋哲学の源流として後世にも語り継がれています。
そんな歴史に残る偉大な哲学者が残した思想の中でも、自分との向き合い方を考えさせられるような内容です。
生活の中でさまざまな勝敗があったとしても、自分に打ち勝つことこそがその何よりも価値があることなのだと伝えています。
自分を律すること、誘惑に打ち勝つことが難しいからこそ、それをなせることが偉大なのだと実感させてくれますよね。
一羽のツバメが来ても夏にはならないし、一日で夏になることもない。このように、一日もしくは短い時間で人は幸福にも幸運にもなりはしない。アリストテレス

アリストテレスは、古代ギリシャの哲学者で、プラトンの弟子であり、ソクラテス、プラトンとともに、西洋最大の哲学者の一人とされ、その多くの自然研究の業績から「万学の祖」とも呼ばれています。
物事をなしえたり、幸せになったりするには時間がかかり、短い時間でそれらを達成することは不可能なのだとさとしてくれています。
なんでも早く手に入れたいと願うのはまちがいなのでしょうね。
樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ。ニーチェ

ニーチェ(1844年- 1900年)は、ドイツの哲学者、古典文献学者で、実存主義の代表的な思想家の一人として知られています。
すべてにおいて、果実や報酬が一番大切なのではなく、まずその種をまくことが大切なのだと諭してくれています。
いかなる財宝とくらべようとも、良友にまさるものはないではないか。ソクラテス
西洋哲学の基礎を築いた人物として知られながらも、謎多き人物として語り継がれているギリシャ出身の哲学者、ソクラテス氏。
「いかなる財宝とくらべようとも、良友にまさるものはないではないか」という名言は、仲間という存在の尊さを語っていますよね。
人や時代によって価値が変化する物質的なものより、奇跡的に出会えた存在の方が大切という感覚は、古代においても大きな意味を持っていたのではないでしょうか。
最初期の道徳哲学者の1人として数えられるソクラテス氏ならではの名言です。
創造力は知識よりも重要だ。知識には限界があるが、創造力は世界を覆う。アインシュタイン

アインシュタイン(1879年-1955年)は、20世紀最大の物理学者です。
彼が残したことばはどれも、そうか!
と思わせてくれたり、感嘆することばかりです。
知識は大切ですが、自分でなにかを創造することはそれよりもっと限界がない、無限なものだと、誰もがもっている創造の力をはたらかせる大切さを教えてくれます。
下学上達
こちらの格言の意味は身近なものから学んで、次第に深い学問に通じることを意味しています。
音楽でいえばスケール練習やリズム練習をしているうちにいろいろできるようになっていくというイメージでしょうか。
どの学習でも最終到達地点は似ていたりする場合もあると思うので、一度そうやって頂点に達した人は、他のことでも上達が早いのかもしれませんね。
あなたも学んでみたいと思ったことを手近な一歩から始めてみてはいかがでしょうか。
人は心が愉快であれば終日歩んでも嫌になることはないが、心に憂いがあればわずか一里でも嫌になる。人生の行路もこれと同様で、人は常に明るく愉快な心をもって人生の行路を歩まねばならぬ。シェイクスピア

シェイクスピア(1564年- 1616年)は、イギリスのルネサンス演劇を代表する劇作家、詩人で、最も優れた英文学の作家と言われています。
生涯で、四大悲劇「ハムレット」、「マクベス」、「オセロ」、「リア王」をはじめ、「ロミオとジュリエット」、「ヴェニスの商人」、「夏の夜の夢」、「ジュリアス・シーザー」など多くの傑作を残しました。
優れた人間の内面の心理描写をしつづけたシェイクスピアは人生の真実を語っているように思います。