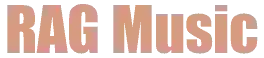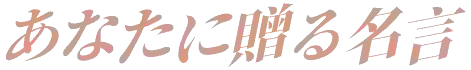古代ギリシャを起源とする、世界中の哲学者による名言
哲学、と言われると、どういったものか説明できますでしょうか。
その起源は古代ギリシャにまで遡ると言われ、人間の存在、宇宙、道徳、知識、真理といったものについて考察する学問として現在まで発展してきました。
今回は、そんな哲学者たちによる名言をご紹介します。
様々な真理を追求する学問だからこその言葉は、きっと迷った時の道標になってくれますよ。
シンプルなものから難解なものまでリストアップしましたので、ぜひチェックしてみてくださいね!
古代ギリシャを起源とする、世界中の哲学者による名言(1〜10)
去る者は去れNEW!アレクサンドロス大王
古代ギリシャの帝国のひとつ、マケドニア王国の君主アレクサンドロス大王。
歴史上において最も成功した軍事指揮官とも言われるアレクサンドロス大王は数々の名言をのこしました。
そのなかでも短くも強い意志が感じられるこちらの名言は、長い遠征に疲れ切っていた大勢の兵士たちに語った言葉です。
去る者は去れ、たとえ少数になったとしても、遠征をして戦う意欲がある者とともに遠征を続けていく、という意味が込められています。
垣根は相手がつくっているのではなく、自分がつくっているアリストテレス
古代ギリシャを代表する哲学者で、倫理学や論理学の分野で多大な影響を与えたアリストテレス。
彼が残した言葉は、人間関係の悩みを解決するきっかけになります。
他者との間に生じる壁や問題を相手のせいだと思うこともあるでしょう。
しかし、その壁を作り出しているのは自分であることを示しています。
過去の失敗や後悔が原因で、他人を信じることを恐れてしまうこともありますよね。
この教えは自分の内面を見つめ直し、心を開くことで新たな可能性が広がることを表しています。
対人関係の改善や自己理解を深める助けにもなる名言です。
この世で情熱なしに達成された偉大なことなどないゲオルク・ウィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、ドイツ観念論を代表する哲学者です。
彼の言葉は、情熱の持つ圧倒的な力を強調したものです。
人類が達成してきた偉業の多くは、熱意や執念によって実現されてきたという視点が込められています。
困難な状況でも諦めずに挑戦し続ける姿勢は、時として奇跡的な結果を生むものです。
目標に向かって進む上で情熱がいかに重要かを改めて気づかせてくれます。
何かを成し遂げるには単なる努力では足りず、心からの情熱を持つことの大切さが伝わる名言です。
存在するとは、行動することであるイマヌエル・カント
批判哲学ともいわれる近代哲学の基礎を作り上げたドイツの哲学者、イマヌエル・カント。
彼が残したこの言葉は、存在するということの本質を行動に結びつけて解釈したものです。
ただ存在するだけではなく、行動することによって初めて価値が生まれるという考え方を示しています。
理想や目標を掲げるだけでは不十分で、それを実現するための具体的な行動がともなわなければ意味がありません。
小さな行動でも積み重ねることで自己実現や社会への貢献につながることを教えてくれる名言です。
たくさん持っている人が豊かなのではなく、たくさん与える人が豊かなのだエーリヒ・フロム
社会心理学や哲学の分野で活躍したドイツの思想家、エーリヒ・フロム。
豊かさの本質を物質的な所有ではなく、他者に与える心に見いだそうとする考え方を示した言葉です。
現代社会では、財産や地位の多さが成功や幸福の象徴とされることがありますが、その価値観に一石を投じています。
他者に惜しみなく与えられる心の広さこそが、真の豊かさであるという彼の哲学は、日常の人間関係や社会活動においても大きな意味を持つでしょう。
何かを与えることで人との絆が深まり、結果として自分の幸福感も高まるのだと教えてくれる言葉です。
推察ができる者は多いが、決断を下せる者は少ない。シャルル・ド・モンテスキュー
法学や政治学の分野で活躍したフランスの哲学者、シャルル・ド・モンテスキュー。
知識と行動の間にある大きなギャップをするどく指摘した彼の名言です。
ものごとを推察したり分析したりする能力は多くの人が持っていますが、それを実行に移す勇気や決断力を持つ人は少ないのが現実です。
未来のリスクを予測していても、決断を先延ばしにしてしまう経験がある方もおられますよね。
考えるだけではなく、一歩踏み出すことの重要性を教えてくれます。
そしてその一歩が、人生を大きく前進させるチャンスになるかもしれませんよ。
人生は後ろ向きにしか理解できないが、前向きにしか生きられないセーレン・キェルケゴール
実存主義の先駆けとされるデンマークの哲学者、セーレン・キェルケゴール。
彼の言葉は、人生の理解と生き方に対する独特の視点を示しています。
過去を振り返って初めて物事の意味を理解できる一方で、未来に向かって進む勇気が必要であるという考え方です。
失敗や苦難の経験が後になって自分を成長させたと気づくこともあるでしょう。
この教えは、悩みや不安を抱えながらも前進することの大切さを教えてくれます。
どんな状況でも歩みを止めず、未来に希望を見いだす姿勢が人生を豊かにするカギなのかもしれませんね。