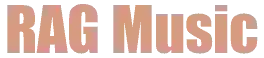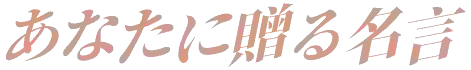AI レビュー検索
二宮尊徳 の検索結果(1〜10)
遠きをはかる者は富み、近くをはかる者は貧す二宮尊徳
二宮尊徳は、二宮金次郎の名でも知られる江戸時代の人物です。
報徳思想を唱え、農村復興を目指して尽力しました。
そんな彼が、農村復興に取り組む中で説いた言葉がこちらです。
「遠きをはかる者」とは、将来を見据えられる人のことで、「近くをはかる者」とは、目先の利益にとらわれて先のことを考えられない人のことを指します。
この言葉のあとに続く節では、秋に収穫できる植物の種を春にまくことや、100年後立派に育つ杉の木を植えることなどが「遠きをはかる」の例として挙げられています。
現代でもこの考え方はとても重要なものですよね。
小を積んで大を為す二宮尊徳
日本全国の小学校に銅像が建てられていたことで有名な二宮尊徳。
二宮金次郎の名前で知られている彼は江戸時代の農政家であり、倹約と努力の大切さを説きました。
大きな目標を成し遂げるためには、日々の小さな積み重ねが不可欠であることを教えています。
荒廃した村を復興させる際、彼はコツコツと地道な改革を進め、持続可能な農業と共同体の繁栄を実現しました。
この思想は、現代の個人の成長や組織の成功にも応用でき、小さな努力がやがて大きな成果につながることを示しています。
日々の行動の一つひとつが未来を作ることを教えてくれる名言です。
楽しみを見て直ちに楽しみを得んと欲するものは、盗賊鳥獣に等しい。人は勤労して後に楽しみを得る二宮尊徳

二宮尊徳(1787年〜1856年)は、江戸時代後期の思想家、農政家です。
農村復興政策を指導したことで知られています。
努力をしたら、した分のものが手にいれられる、しかし、それなりの努力であれば、それなりのものしか手に入れられない、ということなのでしょう。
背筋がのびることばですね。
五重塔に彫られた十二支が寅から彫り始められている理由は何でしょうか?
- 家康公が寅年生まれだったから
- 寅の方角が日光東照宮の正面にあたるから
- 東照宮を建立した当時の風水思想に基づくから
こたえを見る
家康公が寅年生まれだったから
日光東照宮の五重塔に十二支が寅から彫り始められている理由は、徳川家康公が寅年生まれだったためです。家康公への敬意を表して寅から彫られました。
日光東照宮の名前の由来は?
- 家康の幼名に由来する
- 家康の諱(いみな)にちなんでいる
- 家康が死後に追贈された名に由来する
こたえを見る
家康が死後に追贈された名に由来する
日光東照宮の「東照」は、徳川家康が死後に追贈された神号「東照大権現」に由来します。この追号は家康の遺徳を称え、太陽が常に東から昇ることから、家康の治世が永遠に続くようにとの願いが込められています。東照大権現とは、すなわち太陽のように明るく照らす、偉大な権現(神の化身)という意味です。
徳川家康を祀った東照宮は、日光以外にいくつあるでしょうか?
- 約3箇所
- 約13箇所
- 約130箇所
こたえを見る
約130箇所
実は、日光東照宮以外にも日本各地に約130箇所の東照宮が存在します。徳川家康は江戸時代の初代将軍であり、その死後、神聖視されて多くの地域で東照宮が建立されました。これらは家康を祭神としており、日光東照宮と並んで家康を称える場となっています。
是非に及ばず織田信長
豊臣秀吉、徳川家康とともに三英傑と呼ばれる日本の武将、織田信長。
天下人となるも、家臣である明智光秀による謀反で失脚したことで知られていますね「是非に及ばず」は、本能寺の変の際に織田信長が述べたと言われている言葉です。
意味としては、「どうにもならない」。
謀反を起こしたのが明智光秀と聞き、そう言ったそうです。
この言葉には諦めの気持ちとされる説、前向きな言葉だという説があります。
どちらにせよ、心に響く名言ですね。