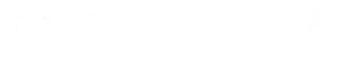【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
懐かしい童謡や民謡、わらべうたの優しいメロディを耳にすると、まるで時空をこえたように、幼い頃の思い出が鮮やかによみがえってきます。
皆さんにも、幼少期から心に残り続ける「懐かしの歌」があるのではないでしょうか。
本記事では、日本を象徴する童謡唱歌や、各地で大切に歌い継がれてきた民謡、わらべうた、そして、お遊戯会やレクリエーションなどさまざまなシーンで親しまれている童謡をご紹介します。
日本の四季と文化、そして人々の日常を優しく映し出す童謡の世界へ、心温まる音の旅に出かけてみませんか?
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(1〜10)
とおりゃんせわらべうた

江戸時代から歌い継がれる日本のわらべうたで、神奈川県川崎市の川崎大師参道で歌われていたとされる歌です。
鬼役の2人が手をつないで門を作り、みんなで歌いながら間をすり抜けていく遊びで親しまれてきました。
歌詞には子供の7つの祝いでお札を納めに参る内容が込められ、神聖な場所への畏怖の念も表現されています。
幼い頃に近所で集まって遊んだ記憶をお持ちの方や、横断歩道の信号機から流れるメロディでご存知の方にとって、懐かしさを感じながら歌える1曲といえるでしょう。
手をたたきましょう作詞:小林純一/原曲:チェコ民謡

手拍子というシンプルな動作から始まる喜びの表現が、子供たちの心に自然と響く温かい楽曲です。
小林純一さんがチェコ民謡に日本語の歌詞を付けた本作は、覚えやすいメロディと親しみやすい言葉で構成されており、保育園や幼稚園でもひんぱんに歌われています。
また、NHKの教育番組や童謡集で取り上げられ、多くの世代に愛され続けてきました。
手をたたく動作がリズム感や運動能力の発達を促すため、親子のコミュニケーションツールとしてもはもちろん、高齢者施設でのレクリエーションにも最適な作品といえるでしょう。
桃太郎作詞:不詳/作曲:岡野貞一

誰もが知る日本の昔話を歌にした、岡野貞一さん作曲による不朽の童謡。
1911年に文部省の教科書に掲載されて以降、100年以上にわたって多くの子供たちに親しまれてきました。
犬、猿、きじを仲間にして鬼ヶ島へ向かう勇敢な物語が、覚えやすいメロディにのせて描かれています。
フジテレビの番組『じゃじゃじゃじゃ〜ン!』では替え歌として使用され、JR西日本岡山駅では接近メロディとしても親しまれているこの楽曲。
全6番までの歌詞を物語とともに振り返りながら、みんなで歌うのもオススメです!
かえるのがっしょう作詞 :岡本敏明/原曲:ドイツ民謡

覚えやすいメロディで誰もがすぐ歌えるようになってしまうこの楽曲は、ドイツ民謡を原曲とし、岡本敏明さんが日本語の歌詞を付けました。
輪唱といえば、まず思いつく曲ですね。
2小節ごとにどこからでも入れるため、加わるタイミングをつかみやすいのもポイントです。
歌詞は1番のみ、しかもとてもシンプルなので、歌詞をおぼえることに時間を取られず、すぐに輪唱を楽しめます。
幼稚園や保育園、小学校で輪唱に挑戦するときは、「せーの!」と大きな声で、入るタイミングを促してあげましょう。
こぶたぬきつねこ作詞・作曲/山本直純

おなじみの4匹の動物たちがしりとりでつながる愛らしい童謡。
手遊び歌としても親しまれている人気作品です。
山本直純さんが作詞作曲を手がけた本作は、NHKの『おかあさんといっしょ』で放送され、多くの子供たちに愛され続けています。
1999年8月には斉藤昌子さんと杉並児童合唱団によるバージョンがリリースされ、その後もさまざまなアーティストがカバーしました。
シンプルで覚えやすいメロディと動物の特徴的な鳴き声が印象的で、幼稚園や保育園での手遊びタイムにピッタリですね!
ひげじいさん作詞:不詳/作曲:玉山英光

みんなで大きな声で歌いながら、顔の前で手をくるくる回してひげを作った思い出がある方も多いのではないでしょうか?
シンプルで覚えやすいメロディに合わせて、ひげじいさんやこぶじいさんなどさまざまなキャラクターの手の動きを楽しむ手遊び歌です。
幼稚園や保育園で長年愛され続けてきた本作。
021年や2022年には複数のアーティストによる録音版もリリースされています。
手指の運動能力やリズム感を育みながら、親子で一緒に歌って遊ぶのにピッタリの1曲といえるでしょう。
いぬのおまわりさん作詞:佐藤義美/作曲:大中恩

迷子になってしまった子猫を優しく助けようとする犬のおまわりさんの心温まる物語を描いた本作は、佐藤義美さんの温かな作詞と大中恩さんの親しみやすい楽曲が絶妙に融合した日本を代表する童謡です。
困った表情で「ニャン、ニャン、ニャン」と鳴く子猫の気持ちに寄り添いながら、カラスやスズメにも助けを求める犬のおまわりさんの優しさと奮闘ぶりが、聞く人の心をほっこりと温めてくれます。
1950年代から1960年代にかけて制作されたこの楽曲は、NHKの『みんなのうた』や『おかあさんといっしょ』などの教育番組で親しまれ、多くの子供たちに愛され続けています。