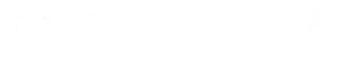【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
懐かしい童謡や民謡、わらべうたの優しいメロディを耳にすると、まるで時空をこえたように、幼い頃の思い出が鮮やかによみがえってきます。
皆さんにも、幼少期から心に残り続ける「懐かしの歌」があるのではないでしょうか。
本記事では、日本を象徴する童謡唱歌や、各地で大切に歌い継がれてきた民謡、わらべうた、そして、お遊戯会やレクリエーションなどさまざまなシーンで親しまれている童謡をご紹介します。
日本の四季と文化、そして人々の日常を優しく映し出す童謡の世界へ、心温まる音の旅に出かけてみませんか?
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 日本の唱歌・童謡・わらべうた|世代をこえて歌い継がれる心に響く名曲
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 童謡の人気曲ランキング【2026】
- 【みんなのうた】時代を越えて愛され続ける懐かしの名曲・人気曲
- 【手遊び】子どもに人気!流行の手遊び歌&懐かしのわらべうた集
- 【秋の童謡】秋のうた・唱歌・わらべうた。秋に歌いたい名曲集
- 【小学校の音楽】教科書に掲載されたことのある人気曲&懐かしの歌一覧
- 【童謡メドレー】誰もが知っている定番&人気の名曲プレイリスト
- 【みんなのうた】泣ける名曲。もう一度聴きたい感動ソング
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 京都の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(31〜40)
おしくらまんじゅう

親しみやすいメロディと、まんじゅうのイメージを使った遊び心のある歌詞が魅力の1曲です。
寒さをしのぐための知恵から生まれた本作は、暖かさと笑顔を分かち合える遊びとして世代を超えて受け継がれています。
遊び歌としての価値だけでなく、冬の季語として俳句にも詠まれるなど、日本の文化に深く根付いた作品です。
寒い冬に、実際におしくらまんじゅうをしながら歌えば、きっと子供たちも肌のぬくもりとともに、友達や家族と過ごす時間の素晴らしさを感じられるはずです。
さくらさくら

この曲の作者は不明ながら国際的に知られている日本の代表曲。
詩のなかに霞か雲かも区別がつかない山の桜を歌っているのは、日本人なら誰でもさくらの美しさを思い出します。
さくらで有名な小金井公園のある最寄駅の武蔵小金井駅はJRの発車メロディともなっています。
汽車ぽっぽ

車も殆ど走っていない頃の遠出の交通機関は汽車でした。
飛行機もプロペラの時代でしたがありましたが、やはり運賃が高いので汽車と船が一般的です。
機関車なぞはろくに踏切もない時代に学校帰りには必ず見かけて何車両あるかなど数えていた事もありました。
その汽車でさえ年に1度乗るか乗らないかの時代ですので、ウキウキ気分で歌いたい気持ち単純な詩の中によく表れている童謡です。
チューリップ作詞:近藤 宮子/作曲:井上武士

赤、白、黄色のチューリップが並んで咲く美しい春の情景を描いた、日本で最も愛され続けている童謡の一つです。
近藤宮子さんの作詞には「どの花にもそれぞれの美しさがある」という多様性を認める温かなメッセージが込められており、井上武士さんの親しみやすいメロディとともに、子供から大人まで自然に口ずさめる魅力があります。
幼稚園や小学校の音楽授業で広く親しまれ、2006年には日本の歌百選にも選定された本作。
春の訪れを感じたいときや、子供と一緒に歌を楽しみたい方にピッタリの1曲です!
どんぐりころころ

子どもの頃は完全にドンブリコではなくドングリコと歌っていました。
殆どが耳だけで覚えた童謡なので、歌の意味もよくわかっていませんが、この歌はどんぐりにも感情があるという子ども心にどじょうやリスが親切にしてあげた歌なんだとは感じてました。
幼い時の感情って情緒を育てるためにも歌や絵本は大事ですね。
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(41〜50)
いちにのさんのしのにのご

数字を用いたリズミカルなフレーズを、指を立てたり曲げたりしながら歌うシンプルな遊び方で、世代を超えて愛され続けているわらべうたです。
NHKの子供向け番組『にほんごであそぼ』で取り上げられ、動画投稿サイトでも親しまれています。
dmgさんの「イチ・ニ・サン・シ」や星野源さんの「いち に さん」など、現代アーティストたちによって新たな形で受け継がれている本作。
親子や友達と一緒に楽しみながら、手先の器用さやリズム感を育むことができる楽しい1曲です。
おおなみこなみ

長縄跳びやリトミックの定番曲として位置づけられ、縄を左右に大きく揺らして波の動きを表現する動作とともに楽しめる本作。
歌いながら体を動かすことで、自然とリズム感や協調性が養われます。
子供たちの音楽教育や情操教育の現場でも活用され、教育芸術社の小学校音楽教科書『小学生のおんがく1』にも掲載されています。
子供の頃に、この曲を口ずさみながらみんなで大縄跳びを楽しんだ方も多いのではないでしょうか?
地域によって歌詞が異なるようなので、気になる方はチェックしてみてくださいね。