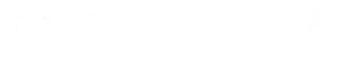【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
懐かしい童謡や民謡、わらべうたの優しいメロディを耳にすると、まるで時空をこえたように、幼い頃の思い出が鮮やかによみがえってきます。
皆さんにも、幼少期から心に残り続ける「懐かしの歌」があるのではないでしょうか。
本記事では、日本を象徴する童謡唱歌や、各地で大切に歌い継がれてきた民謡、わらべうた、そして、お遊戯会やレクリエーションなどさまざまなシーンで親しまれている童謡をご紹介します。
日本の四季と文化、そして人々の日常を優しく映し出す童謡の世界へ、心温まる音の旅に出かけてみませんか?
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 日本の唱歌・童謡・わらべうた|世代をこえて歌い継がれる心に響く名曲
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 童謡の人気曲ランキング【2026】
- 【みんなのうた】時代を越えて愛され続ける懐かしの名曲・人気曲
- 【手遊び】子どもに人気!流行の手遊び歌&懐かしのわらべうた集
- 【秋の童謡】秋のうた・唱歌・わらべうた。秋に歌いたい名曲集
- 【小学校の音楽】教科書に掲載されたことのある人気曲&懐かしの歌一覧
- 【童謡メドレー】誰もが知っている定番&人気の名曲プレイリスト
- 【みんなのうた】泣ける名曲。もう一度聴きたい感動ソング
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 京都の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(41〜50)
さよならあんころもち

日本の伝統的なお菓子「あんころもち」と「きなこ」を題材に、再会を願う気持ちを込めた言葉遊びが印象的。
手遊びや身振りを交えて歌うことで、子供たちの創造力やコミュニケーション能力を育みます。
保育園や幼稚園ではパペットを使って演じるなど、子供たちが楽しく別れの時間を過ごせるよう工夫されています。
伝承歌として長年受け継がれてきた本作は、子どもの情緒発達を支える教材として、多くの保育関連書籍やCDに収録されています。
親子で楽しく歌いながら、日本の伝統文化に触れたい方モオススメの1曲です。
たけやぶのなかから

シンプルながらリズミカルなメロディと、手遊びやじゃんけんと組み合わせた、子供たちの想像力やリズム感を育むのに最適な1曲。
教育現場では、コミュニケーション能力向上にも一役買っており、年齢を問わず楽しめる魅力にあふれています。
口承で伝えられてきた本作は、地域ごとに微妙な違いがあり、それぞれの土地柄や文化を反映しているのもおもしろいポイントです。
保育園や幼稚園の教育現場で広く活用されており、手遊び歌やじゃんけん遊びの定番として親しまれています。
つくしはつんつん

自然の息吹を感じさせるわらべうたの傑作。
単純な言葉遊びのなかに、植物が芽吹く瞬間の描写が見事に織り込まれていて、まるで春の野山を散策しているような楽しさを味わえます。
音楽としての高い芸術性よりも、気軽に口ずさめる親しみやすさが、長年にわたり愛され続けている理由でしょう。
手遊びとしても親しまれ、保育の現場で幅広く取り入れられています。
日本人の持つ季節感と、自然をいつくしむ心が見事に表現された本作は、子供から大人まで世代を超えて楽しめます。
自然豊かな春の訪れを感じながら、家族や友人と声を合わせて歌ってみませんか?
どんどんばしわたれ

簡単な歌詞とリズミカルなメロディのなかに、キツネが出てくるワクワク感と想像力を膨らませる要素がちりばめられた1曲。
多くの童謡集にも収録されており、この曲を題材にした絵本も出版されています。
本作は、幼稚園や保育園での集団遊びで活用されており、手をつないで門をくぐったり、橋を渡ったりする遊びを通じて、子供たちの協調性やリズム感を育むことができます。
大切な人と一緒に歌って遊べる、心温まる楽曲をぜひ体験してみてください。
なかなかほいわらべうた

手足の動きと歌をリズミカルに組み合わせた楽しい作品です。
内側と外側を意味する「なか」「そと」の掛け合いが生み出すリズムに乗って手や足を動かせば、自然と体も心も弾んでいきます。
輪になって遊ぶことで、子供たちの協調性や一体感が生まれ、笑顔の輪が広がっていくのも本作の魅力の一つでしょう。
保育園や幼稚園では年齢を問わず長く愛されており、2020年4月には全国保育士会が選ぶ「伝承遊び100選」にも選出されました。
お子さんと触れ合ったり、リズム遊びを楽しんだりしたい方にオススメの1曲です。
ひらいたひらいたわらべうた

日本の伝統的なわらべ唄として長く親しまれてきた本作は、春の訪れを感じさせる歌詞が魅力です。
花が開いたり閉じたりする様子を、子どもたちが手をつないで輪になって表現する遊びが楽しいですね。
シンプルな歌詞とメロディーながら、日本人の自然観や無常観が込められており、奥深い魅力があります。
幼稚園や保育園で歌われることも多く、子どもたちの情操教育にも役立っています。
江戸時代から歌い継がれてきたこの曲は、春の季節を感じたい方や、日本の伝統文化に触れたい方にオススメです。
お子さまと一緒に歌って、春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか。
おぼろ月夜

春を感じる目の前に広がる菜の花畑を詞にした詩も曲も本当に素敵な童謡曲のひとつです。
昔歌った歌はメロディから詩から全て頭に入っているのですが、残念ながらこの曲の知名度は現在の子たちにはいまいちのようです。
日本の童謡はどうしても詩が昔の言葉なので、馴染みが薄くなるのかもしれません。
日本の伝統はそれでも受け継がれて欲しいです。