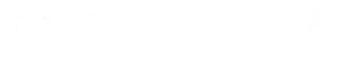【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
懐かしい童謡や民謡、わらべうたの優しいメロディを耳にすると、まるで時空をこえたように、幼い頃の思い出が鮮やかによみがえってきます。
皆さんにも、幼少期から心に残り続ける「懐かしの歌」があるのではないでしょうか。
本記事では、日本を象徴する童謡唱歌や、各地で大切に歌い継がれてきた民謡、わらべうた、そして、お遊戯会やレクリエーションなどさまざまなシーンで親しまれている童謡をご紹介します。
日本の四季と文化、そして人々の日常を優しく映し出す童謡の世界へ、心温まる音の旅に出かけてみませんか?
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 日本の唱歌・童謡・わらべうた|世代をこえて歌い継がれる心に響く名曲
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 童謡の人気曲ランキング【2026】
- 【みんなのうた】時代を越えて愛され続ける懐かしの名曲・人気曲
- 【手遊び】子どもに人気!流行の手遊び歌&懐かしのわらべうた集
- 【秋の童謡】秋のうた・唱歌・わらべうた。秋に歌いたい名曲集
- 【小学校の音楽】教科書に掲載されたことのある人気曲&懐かしの歌一覧
- 【童謡メドレー】誰もが知っている定番&人気の名曲プレイリスト
- 【みんなのうた】泣ける名曲。もう一度聴きたい感動ソング
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 京都の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(21〜30)
おんまはみんなアメリカ民謡

19世紀のアメリカで生まれたフォークソングを日本向けにアレンジした一曲です。
中山知子さんによる日本語詞は、馬がぱっぱかと走る様子や、こぶたのしっぽがちょろりとしている理由を「どうしてなのか、だれも知らない」と問いかける構成になっています。
幼児にも覚えやすいオノマトペがリズムに乗せて繰り返され、替え歌も作りやすい点が魅力です。
NHKの子ども番組でも歌われてきた本作は、神崎ゆう子さんや坂田おさむさんの歌唱で多くの家庭や保育の場に届けられてきました。
手遊びや行進の動きと組み合わせて、親子で楽しむのにぴったりの童謡です。
アルプス一万尺

2人で向かい合って遊ぶ手遊び歌といえば、誰もがこの歌を思い浮かべるのではないでしょうか。
もとはアメリカの行進歌『Yankee Doodle』ですが、日本語の小気味よい歌詞がのることで、独特の楽しさが生まれていますよね。
歌詞に登場する「小槍」とは、日本アルプスにある標高約3,000mの槍ヶ岳山頂付近の岩峰のこと。
そんな場所で踊るという、スケールの大きな情景が歌われています。
この楽曲は、1962年8月にNHK『みんなのうた』で放送されたのを機に全国へ広まりました。
速度を変えながら手遊びで盛り上がるのはもちろん、登山やキャンプで歌えば、歌詞の世界と景色が重なって、最高の思い出になること間違いなしです!
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(31〜40)
うみ作詞:林柳波/作曲:井上武士

青く雄大な海の景色が目に浮かぶ、誰もが知る唱歌。
作詞を手がけた林柳波さんと作曲の井上武士さんは、ともに海のない群馬県の出身というエピソードも有名です。
だからこそ、初めて目にする光景への素直な感動と憧れが満ちているのかもしれませんね。
本作は1941年に文部省の教科書で紹介され、2007年には「日本の歌百選」にも選出されました。
幼い頃に歌った記憶がよみがえる方も多いのではないでしょうか。
親子で一緒に口ずさみたくなる、やさしい時間をもたらしてくれる名曲です。
ずいずいずっころばし

お茶壺道中のでき事を歌ったという説もあり、やはり切り捨て御免の時代は子どもたりとも容赦されない時代背景の歌で、新茶を将軍に献上する行列をお茶壺道中といい戸をピシャリとしめ息をひそめて行列が過ぎていくのを待っているという命がけの歌なのです。
遊び歌にも鬼を決める時によく歌いました。
夕方のおかあさん作詞:サトウハチロー/作曲:中田喜直

『かわいいかくれんぼ』や『ちいさい秋みつけた』を手がけた、作詞家サトウハチローさんと作曲家の中田喜直さんによる、もう一つの秋の名曲です。
この楽曲で描かれるのは、秋の夕暮れのどこか寂しい風景と、その中で感じる母親の温かさ。
中田喜直さんならではの、やさしく心に染み入るようなメロディが、聴く人の胸に深く響きます。
本作は1950年代にラジオなどを通じて広まった作品で、アルバム『中田喜直 童謡名選集~かわいいかくれんぼ・めだかのがっこう~』などでも聴けます。
1973年、サトウハチローさんの葬儀で中田さん自身のピアノに合わせて参列者全員で合唱されたというエピソードは、二人の絆の深さと、この歌が持つ特別な力を感じさせますね。
秋の夕暮れ、家族を思うひとときにぴったりの、包み込むような優しさを持った1曲です。
おんごく

夏の夕暮れ、大阪の町を子供たちが列をなして練り歩く光景が目に浮かぶような、懐かしいわらべうたです。
作者不詳の伝承歌で、1990年に大阪府教育委員会が刊行したアルバム『大阪府の民謡』に貴重な歌声が記録されています。
賑やかな「天下の台所」のイメージだけではない、路地裏に響いていた子供たちの歌声に、大阪のもう一つの顔を発見する方もいらっしゃるかもしれませんね。
古き良き故郷の心を感じさせてくれる1曲です。
よもの景色を

聴けばぬくもりが感じられる、長く大阪で親しまれてきた遊び歌です。
春の訪れを喜び、梅の枝でさえずるうぐいすを眺める……そんなのどかな情景が目に浮かぶようです。
また、うぐいすの鳴き声と法華経を重ねた言葉遊びには、昔の人々ならではの洒脱な感性が光っていますね。
本作を聴いていると遠い昔、町に響いていた子供たちの無邪気な声が聞こえてくる気がします。