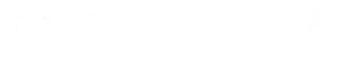【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
懐かしい童謡や民謡、わらべうたの優しいメロディを耳にすると、まるで時空をこえたように、幼い頃の思い出が鮮やかによみがえってきます。
皆さんにも、幼少期から心に残り続ける「懐かしの歌」があるのではないでしょうか。
本記事では、日本を象徴する童謡唱歌や、各地で大切に歌い継がれてきた民謡、わらべうた、そして、お遊戯会やレクリエーションなどさまざまなシーンで親しまれている童謡をご紹介します。
日本の四季と文化、そして人々の日常を優しく映し出す童謡の世界へ、心温まる音の旅に出かけてみませんか?
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 日本の唱歌・童謡・わらべうた|世代をこえて歌い継がれる心に響く名曲
- 春に歌いたい童謡。子供と一緒に歌いたくなる名曲集
- 童謡の人気曲ランキング【2026】
- 【みんなのうた】時代を越えて愛され続ける懐かしの名曲・人気曲
- 【手遊び】子どもに人気!流行の手遊び歌&懐かしのわらべうた集
- 【秋の童謡】秋のうた・唱歌・わらべうた。秋に歌いたい名曲集
- 【小学校の音楽】教科書に掲載されたことのある人気曲&懐かしの歌一覧
- 【童謡メドレー】誰もが知っている定番&人気の名曲プレイリスト
- 【みんなのうた】泣ける名曲。もう一度聴きたい感動ソング
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 京都の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(41〜50)
かあさんの歌

そもそも時代的にこの歌はもう歌われないかもしれません。
夜なべとは?
多分意味がわからない方が多いと思いますし、手袋ひとつなら100円均一でも手に入る時代に徹夜して子どものために朝から晩まで働きづめのお母さんが手袋を編んでくれたという歌なのですが、内容は時代に通用しなくても母の気持ちは時代が移っても変わらないと思いたいです。
【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ(51〜60)
かもめの水兵さん

かわいい歌で大好きでした。
後にセーラーカラーなどファッションでも大流行して、今もなおセーラー服として存在しています。
作られたのは戦前の昭和12年ですが、戦争の色を感じさせない可愛い歌は戦後は教科書にも載った曲です。
かわいい魚屋さん

今ではスーパーに行けば何でも揃う時代ですが、この歌は実生活をこどもが真似して遊んだ事を歌にしているのですが、昔は豆腐でも魚でも売りに来ていたなアと思い出します。
ゴミの削減の問題もこの時代は無かったのも当然です。
魚を包むのは新聞紙だし、豆腐は皆鍋を持って買いに行ってました。
すずめの学校

かなり有名な童謡なのですが、今の子どもはこの歌を知っているかは疑問です。
最近はすずめの数も少なくなったのか、カラスは頻繁に見かけますがすずめは昔は歩くたびに見かけたすずめがあまり見かけません。
ただこの歌ができたのは戦前ですので、やはりすずめの先生がムチを持って教育しているという今ではとんでもない歌になってしまいました。
ほたるこい

日本の自然の美しさを子供たちに伝える、伝統的なわらべうた。
夏の夜空に舞うほたるの光を、優しいメロディーと掛け声で表現しています。
「ほっほっ」という掛け声が印象的で、輪唱も楽しめる曲です。
盆踊りや夕涼みの時間に、みんなで歌うのにぴったり。
子供から大人まで、世代を超えて親しまれている1曲です。
季節の移り変わりを感じながら、日本の心に触れる時間を過ごしてみませんか?
家族や友人と一緒に歌えば、夏の思い出作りにもなりますよ。
みどりのそよ風

懐かしい歌ですね。
春になると豊な自然の緑が身体全身で感じられるまだまだ地球温暖化や少子高齢化など程遠い時代が思い出されます。
小池百合子さんのようにグリーンを取り戻すという姿勢は大事だと思います。
高度成長期に生まれた私はあたり前のように春先になると口ずさんでました。
スキー

今では殆どこの歌の存在が知られているかわかりませんが、以前は教科書にも載っていました。
スノボなどは存在しない時代でしたので、冬のスポーツはスケートかスキーでした。
白銀の世界を快適に滑るスキーの楽しさを歌った曲ですが、よく替え歌にも使われました。
頑張っているお父さんには失礼ですが、朝早く仕事に出ていくお父さんを子どもが替え歌にしたのだと思いますが、お弁当箱を持ってボロボロの靴をはいたお父さんの歌のオチは”頭は100ワット”でした。