世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌
世界のさまざまな国・地域で歌い継がれる童謡・子どもの歌を紹介します!
日本の教科書に載った歌から、実際に海外で歌われている歌、英語教育に使われている人気の歌など、さまざまな目線から集めてみました。
この記事を見ていただくとわかるのですが、実は日本の歌と思っている歌が海外の歌ということも多いんですよ?
「日本で有名な海外の童謡を知りたい」「外国語の童謡を歌いたい」という方はぜひチェックして、歌ってみてくださいね!
世界の童謡。海外で歌い継がれる子どもの歌(1〜10)
Green Green

1963年、アメリカのフォークグループ、The New Christy Minstrelsが発表した大ヒットソングです。
日本では1967年に『みんなのうた』で放送され、今日まで子供向けの曲としても親しまれてきました。
Old MacDonald Had a Farm(ゆかいな牧場)

動物の鳴き声が登場する楽しく、とてもポピュラーな童謡です。
英語の教材などにも利用されることも多く、とても親しみやすい曲ですよね。
日本では幼児向けにさまざまな替え歌もあるので、聴き比べるのも楽しいかもしれませんね。
Twinkle Twinkle Little Star

1806年の英語詩「The Star」による替え歌『Twinkle Twinkle Little Star』が童謡として広まったものです。
世界中、さまざまな言語に翻訳され、現在も広く親しまれています。
日本には大正時代に伝わり、1968年のNHK『みんなのうた』で放送されました。
MICKEY MOUSE MARCH

この曲は多くの人が知っているでしょう。
ディズニーキャラクター、ミッキーマウスのテーマソングです。
1955年から1960年にアメリカで放送されていた、子供向けテレビ番組『ミッキーマウス・クラブ』の主題歌に起用され、以来、ミッキーマウスのテーマソングとして広まっていきました。
Baa, Baa, Black Sheep
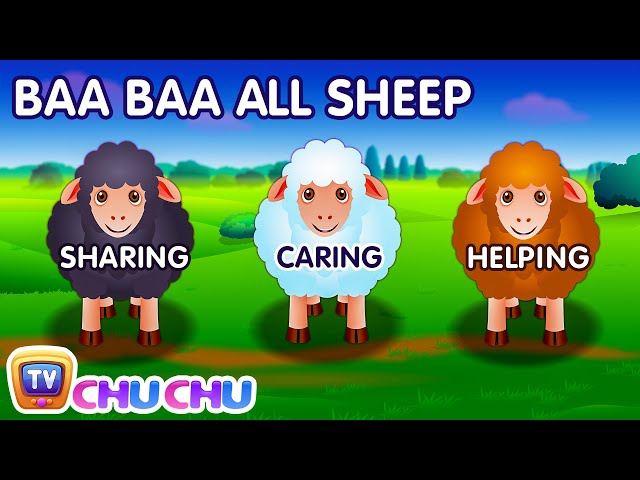
18世紀に生まれたイギリスの古い童謡です。
タイトル冒頭の「バーバー」はひつじの鳴き声をあらわしています。
日本語だと「めーめー」なので、かなりリアリティがある鳴き声ですよね。
曲の裏の意味はイギリス・アフリカ・アメリカ間の三角貿易のことや、羊毛税に苦しむ貧しい庶民のことを歌っているとも言われています。
Michael Row the Boat Ashore

1800年代にアメリカで、聖歌として歌われていた曲です。
1960年代にフォークグループのザ・ハイウェイメンの演奏したレコードがアメリカ、イギリスともにヒットチャートの1位になり、誰もが知っている名曲となりました。
子供番組などでも紹介されることの多い定番曲です。
Winter Wonderland

北半球の国ではクリスマスソングとしても親しまれているこちらの曲。
1934年にフェリックス・バーナードさんがが作曲し、リチャード・バーナード・スミスさんが作詞しました。
冬の男女のロマンス、結婚の約束についての歌詞がついていますが、1947年に子供が雪で遊ぶ内容の歌詞が加えられました。
本編に入る前の導入部分の、バースと呼ばれる部分の歌詞を見るとロマンスについての歌詞だとわかります。
古い曲はバースがついているものも多いので、知ると楽しいですよ。


