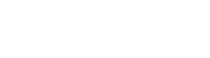Anton Brucknerの人気曲ランキング【2026】
オーストラリアを代表するクラシックの作曲者です。
オルガン奏者としても知られており、音楽史にただ多大なる影響を与えました。
今回はそんな彼に注目します。
これまでにYouTubeで再生頻度の高かった人気曲をランキング形式でリストアップしました。
ファンの方はもちろん、初めましての方は興味がありましたらご覧ください。
Anton Brucknerの人気曲ランキング【2026】(1〜10)
交響曲第4番 変ホ長調「ロマンティック」Anton Bruckner1位

副題の『ロマンティック』というタイトルでも知られる、オーストリアの作曲家にしてオルガン奏者のアントン・ブルックナーによって書かれた作品です。
ブルックナーといえば、難解かつ長い演奏時間の作品が多く、クラシック愛好者の中でも玄人好みの作曲家というイメージを持たれていますよね。
そんなブルックナーの作品の中では、この『交響曲第4番変ホ長調』は比較的短い演奏時間で親しみやすい旋律があり、ブルックナー初心者にもオススメできる作品です。
また、本人の名声を確立するきっかけとなった作品でもあります。
もちろん短い、といっても1時間弱の演奏時間はありますから、秋の夜長に腰を据えてじっくりと耳を傾けてみてくださいね。
交響曲第6番第2楽章Anton Bruckner2位

ただでさえマイナーなブルックナーですが、その中でもこの交響曲第6番は特にマイナーな1曲でしょう。
しかしながら、知る人ぞ知る名曲として、マニア人気の高い交響曲でもあります。
特にこの2楽章は、単純な音階にもかかわらず、どうしてこんなに綺麗なハーモニーが生まれるのだろうと思うはずです。
デ・テウム ハ長調Anton Bruckner3位

アントン・ブルックナーの宗教音楽の中でも比較的よく演奏されるのが、この『デ・テウム』です。
「神なる御身を我らはたたえ」という伝統的歌詞から始まる合唱曲で、全5曲から構成されています。
荘厳で力強く、重厚感あふれる曲調が印象的な作品です。
交響曲第9番Anton Bruckner4位

ブルックナーが取り組んだ最後の交響曲であり、作曲者が他界したときに未完の状態で残されました。
現在でも第四楽章の補筆完成の試みが続けられています。
全体として、明色系の豊かな音色にあふれ、序盤は若干早めのテンポで進み、中盤からは舞曲のような流れていくような美しい情景です。
終盤は夢を見るような静かな心地よさを感じ、終わりはあっさりとした感じで終わります。
無用な加減速がないので好感がもてます。
交響曲 第8番Anton Bruckner5位

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。
オルガン奏者の父の影響で音楽を始めたブルックナーは、マーラーと並び称される巨大な交響曲を書き上げたことにより、後期ロマン派最大の交響曲作曲家として位置づけられました。
交響曲第7番第2楽章Anton Bruckner6位

交響曲第7番はブルックナーの交響曲の中で、初めて初演が成功した曲とされ、第4番と並んで人気が高い曲の1つです。
第2楽章の作曲中に敬愛するワーグナーが危篤となり、ブルックナーは彼の死を予感しながら書き進め、ワーグナーが死去すると、ワーグナーのために「葬送音楽」とするコーダを付け加えました。
槍騎兵のカドリーユ WAB.120 第1番Anton Bruckner7位

1850年頃に作曲された『槍騎兵のカドリーユ WAB.120』は、6つのセクションからなる四手連弾のための作品で、19世紀の社交ダンス「カドリーユ」に基づいた軽快な舞曲の要素が含まれています。
交響曲の重厚な印象とは異なる、よりカジュアルで親しみやすいブルックナーの一面が垣間見える貴重な作品といえるでしょう。
クラシック初心者の方にもおすすめできる、ブルックナーの多様な才能を感じられる1曲です。