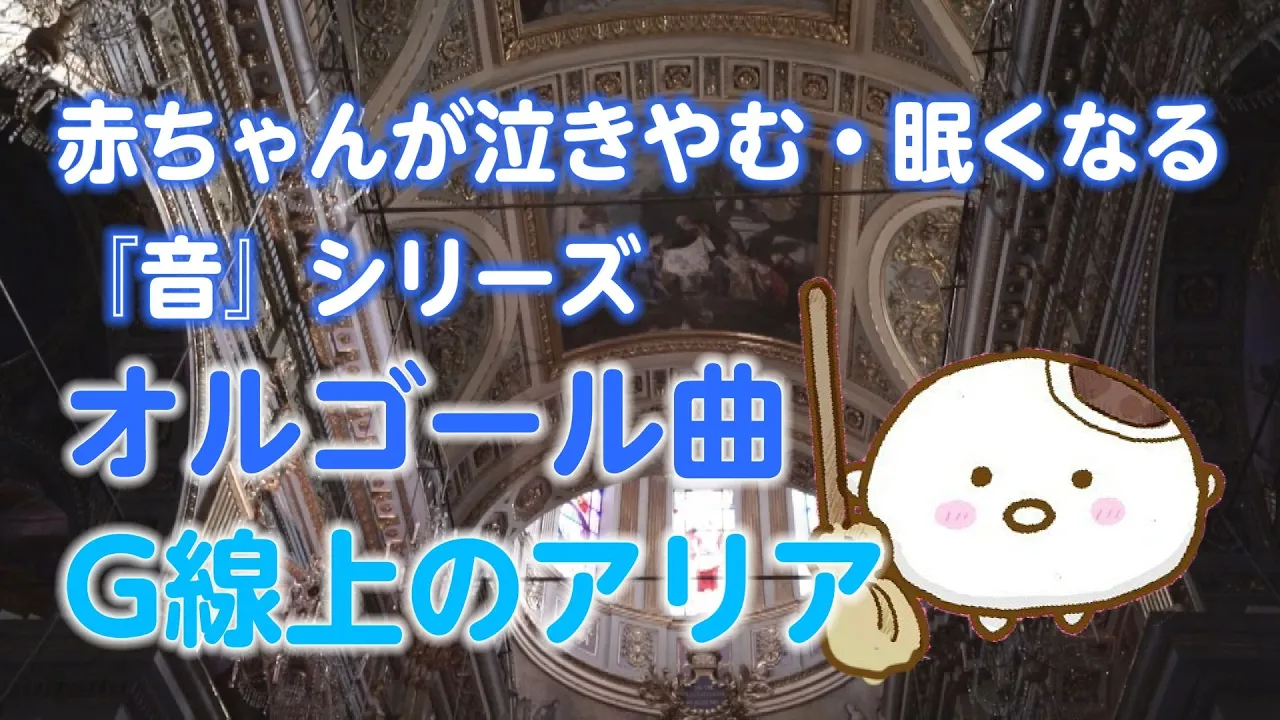J.S.Bachの人気曲ランキング【2026】
西洋音楽の基礎を構築した作曲家で、現代音楽の源流であるとも捉えられています。
今回はそんな彼の人気曲に注目しました。
これまでに再生回数の高かった楽曲をランキング形式でリストアップしましたので、ぜひご覧ください。
J.S.Bachの人気曲ランキング【2026】(1〜10)
G線上のアリアJ.S.Bach1位

どこまでも広がる澄み切った空を思い起こさせるような、穏やかな旋律が心に響く、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの名曲『G線上のアリア』。
この優雅で気品あふれるメロディがオルゴールの澄んだ音色で奏でられると、まるで天から降り注ぐ光の粒のようにキラキラと輝いて聴こえますよね。
規則正しく、そして優しく紡がれる音の連なりは、赤ちゃんの小さな胸の不安をそっと和らげ、深い安心感を与えてくれます。
心安らぐ旋律に包まれて、赤ちゃんもご家族も穏やかな夢の世界へといざなわれる、まさに魔法のような子守唄です。
主よ、人の望みの喜びよJ.S.Bach2位

癒やしの音楽として、また人生のさまざまな場面を彩る曲として親しまれているヨハン・ゼバスティアン・バッハの作品。
この楽曲は、信じる対象への揺るぎない想いと、それがもたらす心の安らぎを、温かく壮麗なハーモニーで表現しています。
歌詞に描かれるのは、困難な状況にあっても希望を失わず、心の支えとなる存在への深い感謝の念なのでしょう。
本作は、バッハが1723年に作曲した教会カンタータ『Herz und Mund und Tat und Leben』の終曲コラールです。
その人気はクラシックの枠を超え、1971年にはイギリスのバンド、アポロ100によるカバーがヒットしたことでも有名ですよね。
結婚式などの祝祭の場はもちろん、静かに自分と向き合いたいときに聴くと、心が洗われるような感動を味わえますよ。
平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第1番 ハ長調 BWV 846 プレリュードJ.S.Bach3位

バッハの『平均律クラヴィーア曲集』は、鍵盤楽器のための名作として知られています。
第1巻 第1番の前奏曲は、シャルル・グノーの『アヴェ・マリア』の伴奏としても有名。
1722年に成立した第1巻は、息子の教育用として書き始められた小曲集がもとになっているそうです。
和音の移り変わりが自然で美しい本曲は、複雑な作品が多いこの曲集のなかでは、比較的取り組みやすい1曲といえるでしょう。
ゆったりとしたテンポで、横の流れを意識しながら演奏すると、魅力がより引き立ちます。
心落ち着く名曲で、バロック音楽の世界に浸ってみてはいかがでしょうか。
トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565J.S.Bach4位

嘉門達夫さんといえば「鼻から牛乳」のフレーズが思い浮かぶという人も多いかもしれませんよね。
バッハの『トッカータとフーガ ニ短調』の有名なメロディーをいかしつつ、男女の関係における衝撃的なできごとを歌い上げていく楽曲ですね。
もとは1992年にリリースされてヒット、2024年には時代に合わせた歌詞に変更した『令和篇』がヒットしました。
鼻から牛乳を吹き出してしまうほどの衝撃、もしかしたら身近にあるかもしれないという共感がコミカルな内容です。
半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903J.S.Bach5位

バロック時代を代表する作曲家、ヨハン・セバスティアン・バッハの名作。
半音階的な動きが特徴的で、革新的な和声構造と大胆な表現力で知られています。
1717年から1723年の間に作曲されたとされるこの曲は、幻想曲とフーガの2部構成で、自由な即興性と厳格な形式美が見事に融合しています。
高度な技術を要する上級者向けの作品ですが、その音楽性の深さは聴く人の心に強く響くはず。
バッハの生存中から高く評価されていた本作は、挑戦する価値のある1曲です。
甘き死よ、来たれJ.S.Bach6位

バロック時代を代表するクラシック作曲家ヨハン・セバスティアン・バッハが、1736年にゲオルク・クリスティアン・シュメッリと共同で出版した宗教歌曲集の一部として収録された、深い宗教的感情を表現した作品です。
バッハの信仰心の深さと、音楽を通じて伝えようとしたメッセージの普遍性が感じられる曲で、死を恐れることなく、むしろ穏やかな死を迎え入れることで永遠の安息に至るというキリスト教の教えが歌われています。
シンプルで美しいメロディは、リスナーに深い感動を与え、バッハの音楽が持つ普遍的な魅力を今に伝えています。
心の安らぎを求める方や、バッハの宗教音楽の世界に触れたい方におすすめの一曲です。
ゴルトベルク変奏曲 BWV988J.S.Bach7位

バロック時代を代表する作曲家、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ。
「音楽の父」と呼ばれる彼が1741年に作曲したのが、この変奏曲です。
2段の手鍵盤のチェンバロのために書かれた本作は、アリアと30の変奏から成り、各変奏は繰り返しを含む2部構成。
3の倍数の変奏にはカノンが用いられ、音程が徐々に広がっていく構造が特徴的です。
バッハの数学への興味や数秘術を反映した工夫が随所に見られ、聴く者を飽きさせません。
チェンバロだけでなくピアノでの演奏も一般的で、グレン・グールドの1955年の録音は、この作品の普及に大きく貢献しました。
バッハの音楽に興味がある方にぜひおすすめです。