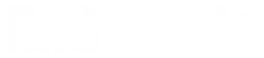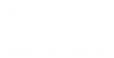ライブハウスで録音した音は使えないと決めつけていませんか?
音楽活動をしていればライブハウス出演することもあるでしょう。
出演時に申し込む機材レンタルのオプションに、出演時のステージパフォーマンスをビデオやCDなどに収録してくれるサービスがあります。
それらは多くの場合、自分たちのパフォーマンスや演奏ミスをチェックする最低限のツールとして活用するに留まります。
それが済んだら捨てないにしても、引き出しやクローゼットにお蔵入りしてしまうケースがほとんどです。
そんなライブハウス録音した音源が人に聞かせても恥ずかしくない「音質」にできればさまざまな利用価値が生まれます。
YouTubeにUPしたり、オーディション用音源、演奏の出来が良ければ安価で販売できるかもしれません。
そんなハイブリッド音源の作成法を紹介します。
- 【低音】高難易度なベースが聴ける邦楽まとめ【かっこいい】
- 【低音】ベースソロが光る邦楽曲まとめ【テクニック】
- 【2025】バンド初心者へ!ライブで盛り上がる人気バンドのおすすめ曲
- カラオケが上手く聞こえる曲
- カラオケで歌うとかっこいいヒップホップ|歌うコツも解説!
- 【苦手な人も必見】カラオケで歌いやすい曲
- 「自分は音痴かも…」歌が苦手な方もカラオケで歌いやすい曲
- 【男性向け】ミックスボイスの練習曲、参考になる曲
- 人気曲のアコースティック・バージョン。アレンジやカバー曲まとめ
- 【声が低い男性向け】カラオケで点数が出やすい曲
- カラオケの選曲にもぴったり!Z世代におすすめしたい盛り上がる曲
- 【ボカロ】初心者でも挑戦しやすいバンド曲【簡単】
- 【カラオケ】声が低い人でも歌いやすいボカロ曲まとめ
エフェクトルーティンと各エフェクト設定のポイント
エキサイター
抜けの悪い楽器などがありましたら、その帯域にエキサイター(その他サチュレーション)で色付けを加えます。
センターやサイドごとに調整できるプラグインもあるので、楽器が位置しているポイントを重点にエディットします。
ボーカルの抜けが悪い場合はシンプルにセンター音像の声成分(中域〜中高域)に微細な色を付ける作業で一気に良くなります。
EQ
マキシマイザーをインサートする直前にEQで音を整えましょう。
未調整でいい感じになればそれで問題ありませんが、暴れすぎた音像を抑えたり少し強調したい部分をこの段階で最終的な微調整を行います。
キックドラムとベースが被る85〜110Hzの帯域をQを強めに設定し、一気にボトムのグレードができるカット部分を探ります。
-0.2〜0.4dBくらい。
マキシマイザー
最終的な音圧調整のためにマキシマイザーを使用します。
プラグインごとに調整できるパラメーターが異なり一概のセッティングはありません。
入ってくる音像の下処理が大切なので、直前にインサートされたEQ調整を対にして作業し。
派手につぶしすぎないことがポイントです。
大きくはマスタリングと呼ばれる音処理工程に近いのです。
きちんとレコーディングされた音源に比べ、ライブは音像やノイズが暴れており、録音に関する下処理が何もない状態からスタートしますので、そのアプローチは調整というよりも大胆な加工という考え方で進めていきます。
ライブハウスでライン録音(2016年)された音をパンチあるサウンドへ
まとめ
マルチレコーディングされた最新のライブ音源より劣りますが、ぐっと聞けるサウンドに加工できます。
1曲ずつ仕上げるマスタリング作業のような手間をかける必要はありません。
ライブ収録したビデオ音声を処理することで、擬似的なライブアルバムが作れます。
YouTube投稿のネタ、簡易的な配布音源としても利用ができるクオリティ。
エア録音よりずっと聴きやすく、ライブハウスならではのエッセンスも感じられます。
YouTubeは多くの曲をUPすればするほど、SEO効果が期待できます。
生バンドがベストな音源(正式なレコーディング)を量産するのは経済的なことやスケジュールも含め、簡単ではありません。
せっかくのライブパフォーマンスを効率的に活かしきることを考えてみてはいかがでしょうか。
ライタープロフィール
![]()
サウンドクリエイター
yamakaWA
「色褪せたMusicをこの世から撲滅させたい….」 音楽のリフォームを提案するHybridSoundReform.comの山川です。
失敗したレコーディング&マスタリング音源の改善、ライブハウス音源のコンテンツ化、動画や講演会などの音声ノイズ除去。
非効率な音質改善サービスを運営しています。
ウェブサイト:http://www.hybridsoundreform.com