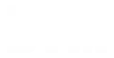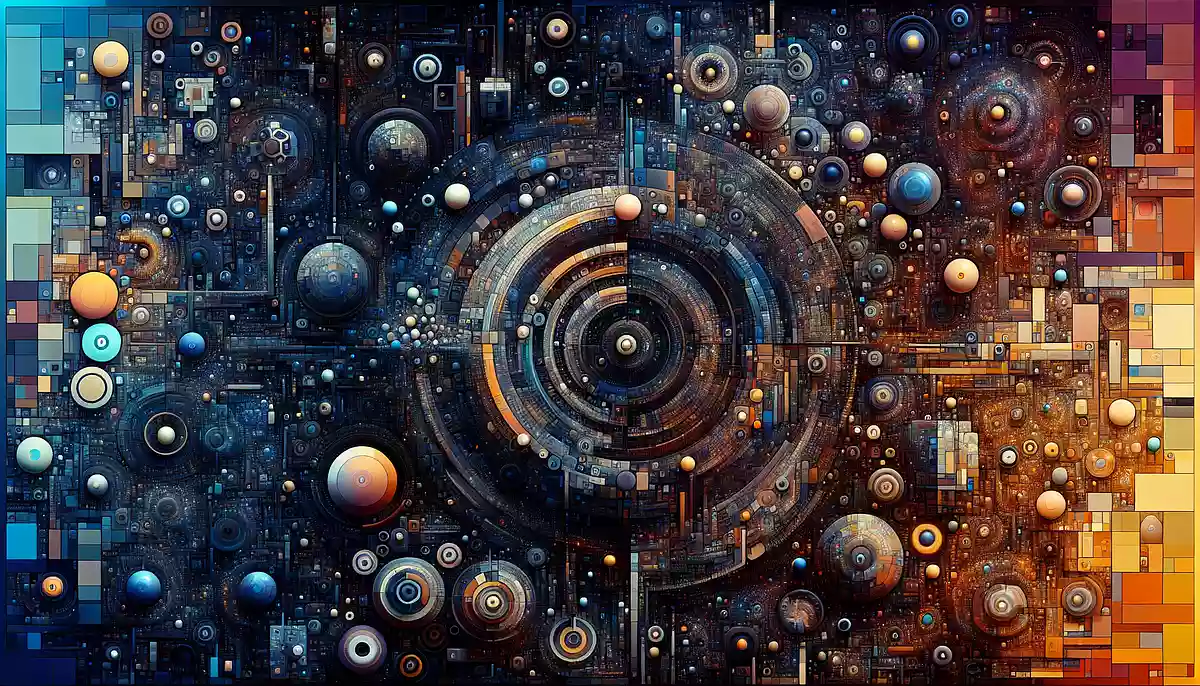【DTMerのための】「奥行き」のあるミックスをしてみよう!
タイトルにある通り、「ミックスで奥行きを演出する方法」をご紹介させて頂きます。
これまた以前同様、音楽仲間のそーだーすい(炭酸水P)さんにちょこっと質問された内容でして……それから大分経ってしまいましたが、聞かれたからには書かないと(笑)!
ということで、今回はミキシングにおいて、奥行きを演出するさまざまな手段をご紹介させて頂きます(笑)。
とはいえ、僕のミックスの腕前はというと……まぁ、言うまでもなくアレなので、あくまで「へぇ~……」程度の認識でお願いします(苦笑)。
しかも、ここで紹介するテクニック?
の大半は、ミックス教本からの受け売りです。
ミックスで「奥行き」を演出しよう!
下図(作画:マサシ)は、ミックス関連の書籍などによく載っているアレ。
……をよりチープに表記した物である。
ぶっちゃけ、サムネイル用に急きょ誂えた絵なので、参考にしないことを強く勧める。

では、本題に入ります。
↑の様な図、ミキシングの勉強をされている方なら誰しも見たことがあると思われます(僕が作ったこの図はチープ過ぎるけど 笑)。
これ系統の図……さも当然の様に奥行きを表記していますが、実際、図を参考にDAWでミックスをしてみると、LRはパンポットで調整できるものの、「奥行き」なんてパラメータはどこにも見当たりません(笑)。
それで「奥行きってどうやって調整すんの?」とググってみると、大体は”リバーブを使え!
”と書かれていたりしますね。
そう、それで正解!
なので、この記事では上手なリバーブの使い方をご紹介します!
……と、言いたいところですが(笑)、残念ながら、僕はリバーブの使い方がイマイチ分かっていません(苦笑)。
なので、リバーブを使った奥行き表現の記述は他の方に託すとして、ここでは主にコンプレッサーを使用した奥行き表現に焦点を当てていきたいと思います。
コンプレッサー……そう、音を圧縮するあのエフェクトです(笑)。
一見、奥行き表現とは無関係そうなエフェクトですが……私見では、(奥行き表現で)最も重要なエフェクトだと思っています。
コンプで奥行きを出せる様になると、表現の幅がグッと広がりますよ!
きっとね……。
サンプル音源もご用意しましたので、文章と併せて聴いて頂けると、言いたいことが伝わり易いと思います(笑)。
コンプレッサーを使用した「奥行き表現」
はい、ではコンプレッサーについての基礎知識から学びましょう!
……というのは、さすがにめんど……じゃなくて、調べればいくらでも出てくる内容なので、超アバウトに要点だけ書いておきます(笑)。
コンプレッサーの役割・効能
- 音を圧縮することによってダイナミクスの幅を狭め、均等な音量にそろえることができます(適度なコンプレッションは、音像が整い、ミックスがしやすくなる)
- 極度な圧縮を施し、均等な音量にそろえた状態を「音圧が高い」と呼び、人間の聴覚上、大きな音と認識されます(小さな音量でも、大きく聴こえる)
- アタック/リリースといったパラメータにより、元音よりもアタック感を強調させたり、余韻を伸ばす(正確には、余韻が伸びた様に聴かせる)ことができます
- 音の質感が変化します(例外はあるものの、基本的に圧縮するほどに音質が低下し、違和感が生じる)
要は、音を圧縮することで音量をそろえるのが目的のエフェクトですね。
使い方は人それぞれですが、基本的にダイナミクスの幅をそろえて、聴きやすくするのが当初の目的……だと思います。
最近では「コンプ=音圧を出すエフェクト」という風潮があり、積極的な音圧稼ぎの道具として使われています。
実際、音圧が高い状態は派手に聴こえるため、最近のCDなんかはインパクト重視で音圧をギリギリまで稼いでいたりします。
……で、それは分かるとして、それが奥行きとなんの関係が?
という話です。
あまりもったいぶっていても仕方ないので、結論から先に言っておきます(笑)。
コンプレッサーで奥行きを表現する方法を簡潔に説明すると……
音を圧縮:強くコンプが掛かると、音像が奥に引っ込む
↓
音量を調整する:ここで音量を上げ過ぎると音像が前の方に戻ってしまうため、距離感を測りながら調整……たったこれだけ(笑)。
音圧が高い状態の音は小音量でも存在感があるため、その性質を利用し、適度な音量に絞って(or上げて)、あたかも「奥で鳴っている」様に錯覚(?
)させるのです。
とはいえ、考えなしに高レシオ!
スレッショルド下げまくり!ぶっ潰せばOK!
という訳でもなく(笑)……重要なのは、アタックとリリースの設定。
使用するコンプの仕様に依る所はありますが、基本的に、強くコンプレッションを掛けたい場合は「アタック早め/リリース長め」に設定すると、ずっとコンプが掛かっている状態になります(スレッショルドを越えた音にすぐ反応し、解除するまでが長い)。
なので、ゼロタイム・アタック(アタック=0msec)&リリース数秒にすれば、とりあえず音像が奥に行く訳ですが……この設定は、正直オススメしません(笑)。
なぜかと言うと、全体的にのっぺりしてしまい、ダイナミクスが感じられない不自然な音になるからです。
それを避けつつ、音楽的に、なおかつ、可能な限り圧縮を施して奥行きを表現するには、それなりに元音のアタック感を残すことが重要となる訳ですね。
「んなこと言われても、msec(ミリ・セコンド)の変化なんて分かんねぇよ……」という方に、朗報(笑)!
どこまで信憑性があるのか不明ですが、人間の聴覚上でアタックを感知できるのは40msecが限界と言われています。
なので、とりあえずこの情報を信じてみて(笑)、アタックの設定は40~50msec辺りに設定(奥行きを出しつつ、程々にアタック感を残したい場合)するのがオススメ。
リリースに関しては……その曲のBPMにも依りますが、200~500msec辺りで探ってみると良いかと思います。
あと、これはコンプレッサーのモデルによりけりですが……ニー(Knee)が設定可能な物だと、より柔軟に・滑らかにコンプが掛けられます。
ソフト・ニーの方が掛かり方が自然ですが、ハード・ニーで思い切り潰しても面白い効果が出せますよ(笑)。
レシオ(圧縮比率)は……う~ん、やはり1:2~3辺りがナチュラルかと思います。
ストリングスやパッドなど、音の粒をそえてしまっても良い(むしろ、その方が良い)楽器は、1:5位の高圧縮設定でも良い感じでしょう。
デモ音源
では、この手法を利用したサンプル音源をご用意しましたので、参考程度にお聴きください。
曲目は、僕のオリジナル曲「みどりの日」のリメイク版(制作途中 笑)です。
それのイントロを抜粋しました(笑)。
ちなオリジナル版→「みどりの日」(みんなの歌詞へ飛びます)
ちょうどGWだし、ローゼンの翠星石の話もしたし(笑)で……色々とベストなタイミングの選曲かと思いまして。
フラット(デフォルト)
制作途中のMIDIを、そのままオーディオに変換(ドラムはキット丸ごと書き出して纏めてあります)。
最後にチョロっと入るボカロには少しだけリバーブ&冒頭のSEにも、もともと含まれている残響が入っていますが、各音源の空間系エフェクトは全てOFFにし、音量調整もメチャクチャ……な、真っ裸状態にしています(笑)。
コンプ・ミックス(コンプ以外のエフェクトは使用せず、奥行きを調整)
各トラックにコンプレッサーのみをインサート。
圧縮&出力調整を行い、奥行きを調整してみました。
(フェーダーは動かしていません)
※このサンプル音源で使用したコンプは、音質・設定の多様性を考慮しSonnox「Oxford DYNAMICS」を選択しました。

……いかがでしょうか……?
僕もこの手法については、まだまだ勉強中でして……下手糞で申し訳ないです。
正直、この程度ならフェーダーの音量操作しただけと大差ないかも……。
なので「コンプで奥行き表現」とドヤ顔するのは少々おこがましい気がしますが(苦笑)……後に施す空間系エフェクトなどと併用することで、より明確な空間・奥行きが感じられる様になる!
……はず。
まぁ、アレです……いわば「空間演出の下ごしらえ」みたいな物だと思って頂ければ幸いです(笑)。
まとめ+α
- コンプレッションを掛けて音圧を稼ぎ、その後、前に出過ぎない程度に音量を調整する
- アタック/リリースの設定が重要。
ある程度のアタック感を残した方が良い
- 同じ設定にしても、コンプのモデルによって奥行き感が異なる
- 実は「マキシマイザーで一気に音圧を稼ぐ→フェーダーで音量調整」でも、同様の効果が得られる(ニュアンスがやや曖昧になりやすいけど……)
……まぁ、大方この様な感じです。
マキシマイザーを使った手法はお手軽ですが、アタックの調整ができない物も多いため、これに頼り過ぎるとのっぺりとしてしまいがち。
なので、コンプと併用して音圧・出力の調整を行うのが吉です(笑)。
あと、コンプによって奥行き感がかなり異なるので、自分に合ったコンプを1つでも用意できるといろいろと捗りますよ(笑)。
参考までに、僕が今までに使用してみた中で、特に奥行き表現が優れていると感じたオススメのコンプ(プラグインオンリー)を掲載しておきます。
奥行きを出しやすいコンプ一覧(マサシ脳内統計)
onnox 「Oxford DYNAMICS」
一言コメント:とにかく音質的な変化が少なく、ナチュラルに奥行きを出せる。
 12db 「Big Blue Compressor」
12db 「Big Blue Compressor」
一言コメント:GUIもさることながら、リリースが美しい……
 Elysia 「Mpressor」
Elysia 「Mpressor」
一言コメント:柔軟性・出音ともにハイレベルなコンプ。
GR Limit機能を使うと、独特な奥行きを出せる。
 WAVES 「API 2500」
WAVES 「API 2500」
一言コメント(笑):アタック/リリースの変化が分かりやすいため、奥行きを出しいやすい。
おまけに出音も良い(笑)。
 LA-2A系(画像はWAVESのCLA-2A)
LA-2A系(画像はWAVESのCLA-2A)
一言コメント:アタック/リリースがオートなので設定不可だが、光学式特有の緩いつぶれ方が意外な奥行き感を生みだす異端児(笑)。
 以上、コンプレッサーを使用して奥行きを操作する方法の解説でした。
以上、コンプレッサーを使用して奥行きを操作する方法の解説でした。
コンプで音圧調整を行うことにより、音像を整える(あるいはぼかす)のがコツです!
フェーダー操作だけでも似たような効果が得られるのは確かですが……やはり、ダイナミクスの幅が整っていると聴こえ方が俄然違いますし、後に控えているマスタリング工程での完成度が大きく変わってきます。
なので、面倒くさがらずにシッカリと音像を作っておきましょう(笑)。
リバーブ&ディレイも併用する
ここまでで、コンプコンプ奥行き奥行きと連呼してきましたが……やはり、ドライな音では限界があります(笑)。
ということで、リバーブ&ディレイも併用しましょう。
リバーブ・ディレイの設定に依ってはさらに奥行きが変化してきますが……残念ながら、空間系については(も)まだまだ勉強中ですので、ここでは割愛させて頂きます(苦笑)
これは個人的な感覚……なのかどうか分からないですが、リバーブのみでは意外と奥行きって出ないんですよね。
空間系で最も奥行きに関わってくるのは、ディレイです。
まぁ、だからと言って「リバーブはいらない子!」という訳でもなく(笑)、この二つを組み合わせる事で真価を発揮します。
ひどく適当な言い方ですが、「リバーブは音同士をくっつける接着剤(横軸)・ディレイは音に尾ひれを付ける(縦軸)」様な感覚で扱うと、分かり易いかも(笑)?
では、先程のコンプ・ミックスにセンド/リターンでリバーブ&ディレイを掛けてみました。
ベース以外のソース、全てに掛けています。
う~ん、いまだにリバーブとディレイの送り量の多寡が分からない……。
コンプのみで奥行きを調整した物に……
リバーブ&ディレイも併用して、さらに奥行き・広がりを演出(笑)!
……はい、いかがでしょうか……。
大分ね、こうね、雰囲気出ますよね(笑)?
ドライ状態では音がブツ切れになる箇所が、リバーブ&ディレイによって尾ひれが付き、わりと自然な余韻が生まれました。
冒頭のSEみたいな自然界の音を収録したソースは、打ち込みとの馴染みが悪かったりするので、多目のリバーブ&ディレイを送ってあげる事でうまく溶け込んできます。
ここでのディレイはテンポ同期(テンポ・ディレイ)はせず、手動で設定(189msec)しています。
詳しい事はよく分からないのですが(笑)、189msecが最もボーカルとの相性が良いディレイ・タイムらしいです。
この設定は曲のBPMを問わず、ボーカルに良い具合に尾ひれが付いて、元よりもうまく聴こえる……らしい。
その他の楽器はどうか分かりませんが、今回は全ての楽器に一律でそのディレイを送っています。
使ってみた感じ、他の楽器でもそれなりに有効っぽいので……ディレイがよく分からない方は、とりあえず「ディレイ・タイム=189msec」を目安にしてみては(笑)?
今回は入れていませんが、フィード・バックも少し足してみると良いと思います。
奥行き操作に使える、ちょっとした小技
コンプ+リバーブ+ディレイの組み合わせで、奥行き操作はバッチリ!
……と思うじゃん(笑)?
いや、実際、この組み合わせで奥行きを作っていくのが正しいと思いますが……実はあるんですよ、とあるエフェクトを使った奥行き操作が……!
~エフェクト控え室~
コーラス(俺だな)
フランジャー(来たか……)
フェイザー(そろそろスタンバっておくか) ガタッ
ディストーション(滅びよ……)
パンナー(左右に揺れ過ぎて吐きそう……)
いや違う、お前らじゃない。
お前らも使えなくはないけど、今回は意外な盲点、EQを使用した奥行き操作をご紹介します(笑)!
他のエフェクトは帰って、どうぞ。
EQで奥行き操作ぁ?
と思われるかもしれませんが、実はできるのです(笑)。
やり方は至極簡単でして、「奥に引っ込めたい楽器の、1kHz(1000Hz)近辺をEQで少し削る」だけ!
例えば、この「コンプ+リバーブ+ディレイ」の音源で言うと……まぁ、大方こんな感じのバランスでOKだと思うのですが、ピアノがもう少し奥に行ってくれると、もっと良くなりそうだと思うんです。
しかし、コンプをこれ以上掛けると不自然になるし、リバーブ&ディレイ送り量を増やしてもなんか違うし……という時に、EQの出番です。
ということで、ピアノのトラックにEQをインサートし、1kHzをポイントの軸に、ほんのり広めのQ幅で2.5db程カット。
すると……
こうなります(笑)。
ピアノが大分奥に引っ込み、他の楽器との分離も向上しました。
特にオーボエ(イントロの主旋律)・ボーカルとのバランスが良くなり、スッキリとした印象ですね。
なぜ1kHzなのかと言いますと、この帯域はさまざまな楽器のアタック部分が重なるポイントだからです。
つまり、この近辺を削る事でアタック感を希薄化させる効果が出て、結果的に「奥に引っ込んだ」様に聴かせる事が可能……という算段です(笑)。
削る量・範囲次第では、コンプレッサーで捉えきれなかった or どうしても残しておきたかったアタック感を適度に維持できるのがミソ。
しかし、ここで注意したいのは……削り過ぎない事。
裏を返せば(?
)1kHzは美味しいポイントでもあるため、削りすぎると変な音になり、ボヤボヤな音像になってしまいます。
今回のサンプル音源の-2.5dbも結構な量ですので、全体的に軽くなった感がありますね……。
まぁ、これは効果が分かり易い設定なので、実際にミックスする時はもっと少量のカットにします。
ともかく、この「1kHzカット」は意外と使えるテクニックなので、オススメです。
スネアなどのセンターに定位する楽器はボーカルとバッティングしやすいので、ほんの少し「窪み」を作ってあげると効果的だったり。
まぁ、スネアはアタック感が重要なので加減が難しかったりしますけど(苦笑)、今回の様なピアノなどは良い感じに作用すると思われます。
ぜひ、お試しあれ(笑)。
おわりに
とりあえず、僕が知っている奥行き操作テクニック(笑)は以上です。
いかがでしたでしょうか?
……え?
知ってた?
……すみません。
プロエンジニアさんの音は録音環境・機材が高水準なのはもちろんのこと、それを差し引いても、まず奥行きがしっかりと作られています。
「奥行きが感じられるミックス=巧いミックス」とは一概には言えないでしょうが、「奥行きを作れているかどうか」がミックスの善し悪しを探る一つの指針ではないかと考えています。
つたない内容の記事でしたが「自身の楽曲のクオリティー・アップを図りたい!」と願う皆様に、少しでもご助力できたら幸いです(笑)。
それでは、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。