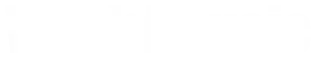沖縄の楽器一覧。琉球音楽の民族楽器
沖縄の音楽ってどこか独特な雰囲気があって、ゆったりした曲は聴いていると心が落ち着いたり、アップテンポな曲は踊りたくなるような楽しげな曲がたくさんありますよね!
沖縄の音楽の独特な雰囲気は、琉球音階によるところも大きいですが、沖縄ならではの楽器が使われていることも大きく影響していますね!
とくに三線は沖縄を代表する楽器で、誰しもがその音色を聴いたことがあると思います。
この記事では、そのほかにも沖縄でよく演奏されている楽器を紹介していきますので、ぜひそれぞれの楽器の背景や音色を知るキッカケにしてみてください。
- メキシコの音楽|ノリノリなラテン・ミュージックが登場!
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- アフリカ発祥の民族楽器まとめ
- 【2026】バンド初心者へ!ライブで盛り上がる人気バンドのおすすめ曲
- 【チルな1曲】ハワイアン・ミュージックの名曲
- 20代に人気のバンド曲ランキング【2026】
- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】
- 【なんだこれ】世界の珍しい・ユニークな楽器まとめ
- ウクレレの名曲。おすすめの人気曲
- 【ウクレレの弾き語りにおすすめ!】ハワイアンミュージックの名曲
- フラダンスの曲選び。ハワイの癒やしと文化が感じられる名曲
- 【世界の音楽】民族音楽のススメ・海外の民謡まとめ
- ウクレレ初心者も楽しい!少ないコードで弾ける簡単な曲
沖縄の楽器一覧。琉球音楽の民族楽器
胡弓

胡弓は沖縄の言葉で「クーチョー」と読むこの楽器は、琉球古典音楽の伴奏に使われることも多い楽器です。
丸い胴にヘビの皮が張られているなど、同じく沖縄のメジャーな楽器である三線と似たような形をしていますが、三線よりも少し小ぶりなサイズ感の楽器です。
さらに演奏方法も異なっており、三線はバチで弦を弾いて演奏しますが、胡弓はバイオリンのように弓で弦を擦ることで音を奏でています。
こうした演奏方法の楽器を擦弦楽器と呼びますが、擦弦楽器ならではの連続的な音からは洋風な雰囲気を感じる一方、その音色からはしっかりと沖縄らしさが感じられるという、不思議な魅力のある楽器です。
ウフデーク

ウフデークは大太鼓のことで、エイサーで演奏される太鼓の中でももっとも大きい太鼓を指します。
大きいものだと直径40cmから50cmにもなり、いわゆる和太鼓らしい「ドンドン」と力強い音が特徴です。
エイサーで演奏される際には、胴につけられた輪っかにヒモを通し、肩から吊るした状態で叩きます。
パーランクーやシメデークーと比べる大きな太鼓ですが、ウフデークも踊りながら演奏されるんですよね。
一般的に「エイサー太鼓」というとウフデークのことを指すようです。
おわりに
沖縄でよく演奏されている楽器を一挙に紹介しました。
三線はもちろん、エイサーで演奏される楽器や古くから伝わる民族楽器などがありましたね。
この記事をキッカケに沖縄の楽器への興味を深めていただければうれしいです。