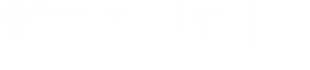よくわかるトロンボーンの音を変える仕組み。スライドと7つのポジション
ライブなどの際にお客様から声をかけられることがありますが、その中でよくこんな質問をされます。
「スライドでどうやって音を変えてるんですが?」
「スライドには目印とかあるんですか?」
今回はその疑問にお答えしましょう。
これからトロンボーンを始めたいという方も、この機会にぜひ楽器の仕組みを覚えてください。
音を変える仕組み

http://www.photo-ac.com/
トロンボーンはスライドを動かし管の長さを変えることで音を変化させます。
スライド上には7つのポジションがあり、となり合ったポジションは半音の関係です。
同じポジションでも息のスピードをコントロールすることで音の高さを変えられ、スライドとの組み合わせによってさまざまな音が出せるという仕組みになっています。
ポジション
7つのポジションと、各ポジションで出せる音を一覧にまとめました。

それでは、実際にスライドを動かした状態を写真で見ていきましょう。
第1ポジション

楽器を構えた基本の状態が第1ポジションです。
音によっては完全に入れたままではなく、ほんの少し抜くこともあります。
第2ポジション

少しだけ抜きました。
第1ポジションと第3ポジションの中間あたりです。
第3ポジション

スライドを持つ手(握っている支柱)が、ベルのあたりにきます。
ただしベルの長さは楽器によって違うので、そこを視覚的な頼りにしすぎるのはあまりオススメできません。
あくまで最初の段階での目安程度に考えてください。
第4ポジション

ベルを少し越えたあたりが第4ポジションです。
第5ポジション

第4ポジションと第6ポジションの中間あたりです。
多分覚えるのに最も苦労するポジションですが、とにかく練習して慣れていきましょう。
第6ポジション

かなり長く伸ばしますが、この先に第7ポジションが残っているので、まだギリギリまではいきません。
第7ポジション

スライドが抜ける手前まで目一杯伸ばした状態が最後の第7ポジションです。
人によっては右肩を少し前に出すような感じになると思います。
手が届かない場合、右手にひもを付けて演奏する人もいます。

ひもが長すぎるとスライドが抜けてしまいますし、短すぎると役割をはたしません。
ちょうど第7ポジションのところにスライドがくるよう長さを調節してください。
スケール(音階)を演奏してみる
下の譜面はBbメジャースケール(B dur / 変ロ長調)に各音のポジション番号を書いたものです。

最初に解説した通りスライドと息のスピードを組み合わせてフレーズを演奏します。
1オクターヴのスケールを吹くだけでも、これだけ伸びたり縮んだりを繰り返すのですから、実際に曲を演奏している時のスライドの動きは見ているだけでも面白いですよ!
注意点など
今回ご紹介したように、ポジションには「だいたいこのあたり」という目安はありますが、例えば第2ポジションのG(上の一覧表参照)は他の音よりもスライドを少し入れないと音程が低くなる…といったように、同じポジションでも音によってスライドの位置に微調整が必要になります。
反復練習によって、ていねいに体に覚えさせていくことで、瞬時に調整ができるようになっていきます。
ポジションに不安があると演奏中ついスライドを凝視しがちですが、視線が近くに固まるとケータイやパソコンをしている時と同じように、だんだんと姿勢が悪くなったり息の流れも停滞しやすくなったりと、からだ全体を使って演奏するトロンボーンにとっては好ましくありません。
ポジションを確認したらなるべくスライドから目線をはずし、少し遠くを見るような習慣をつけていきます。
また、ポジションが正しくても息や唇の変化で音程が変わってしまうので、ポジションを覚えると同時に、まずはリラックスしたまっすぐな息で吹けるように心がけてみてください。
チューナーに頼り過ぎず耳を使って音程を感じるようにすることも大切です。
最終的には目をつぶったままでも正確に演奏できることを目標にしてみましょう。
最後に
最初は「ちょっと難しそう」と感じるかもしれませんが、やってみると意外に覚えられるものです。
スライドという特徴も「音程が不正確になりやすい」ではなく「自由な演奏が可能」と考えると、もっと楽しめるのではないでしょうか。
人の声のように自由に音程を変化させて歌う管楽器、それがトロンボーンです!