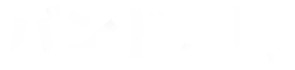口笛がある程度吹けるようになったら習得したいのがしゃくり。
これからしゃくりの練習をする方はもちろん、すでにしゃくりができるようになっている方にとっても注意すべき点があるので紹介しますね!
- 世界レベルの口笛奏者が教える!ビブラートで口笛をプロっぽく聞かせる方法
- 口笛の名曲。聴いて幸せ&練習したくなるステキな口笛ソング
- 世界レベルの口笛奏者が教える!口笛の発音をきれいにするコツ
- 楽器が上手くなる人の共通点とは?
- 世界レベルの口笛奏者が教える!口笛が吹けるようになるコツ
- 曲を速く覚えられる「耳コピ」のコツ
- 世界レベルの口笛奏者が教える!口笛に音程をつけるコツ
- ビブラートの練習曲。歌うまへの第一歩を踏み出そう!
- 【女性向け】ミックスボイス(ミドルボイス)習得に役立つ練習曲
- 【演歌・歌謡曲】チャレンジ!こぶしを出しやすい曲まとめ
- 【男性向け】ミックスボイス練習曲・高音が出やすくなる参考曲
- フルート初心者のための練習曲。おすすめの練習曲
- ドラム中級者にオススメの練習曲。表現力や演奏力を養える楽曲まとめ
はじめに

https://www.pexels.com
どんな楽器でも、慣れてくると少々自分の「癖」が出てくるものです。
口笛の場合、上手になってくると多くの人が陥りがちな罠があります。
それが「しゃくり」です。
ではしゃくりとは一体どういうものなんでしょうか?
「しゃくり」とは?

https://www.pexels.com
詳細な定義は異なりますが、音程を滑らかに変化させながら音の間を移動することを「ポルタメント」「グリッサンド」などと言ったりします。
音楽的にはとても重要な表現技法で、効果的に使えば表現の豊かさを増してくれますが、使いすぎるとくどくなってしまう諸刃の剣です。
特によくいるのが、各フレーズの頭で必ず下からしゃくり上げる人です(私がそうでした)。
毎度毎度同じでは聴いている人も飽きてしまいますし、クラシックの曲を演奏する場合など、楽譜にポルタメントの指示がないのにしゃくってしまうと作曲家の意図したのとは全く違う演奏になるだけでなく、クラシック音楽ファンからひんしゅくを買う可能性があります。
どうやってかけるの?
下からすくい上げるような、音程を上げていくいわゆる「しゃくり」を入れる場合は、音程の変化(第2回)やビブラート(第3回)の際に使った「うゆうゆうゆ」の「うゆ」(舌先が下から上に上がる動き)を1回だけやります。
その際、終着点がちゃんと狙った音程になるように気を付けましょう。
逆に、上から音程を落として狙った音にたどり着くような動きをしたければ、「ゆう」(舌先が上から下に落ちる動き)を1回だけやります。
どういうときに使えるの?
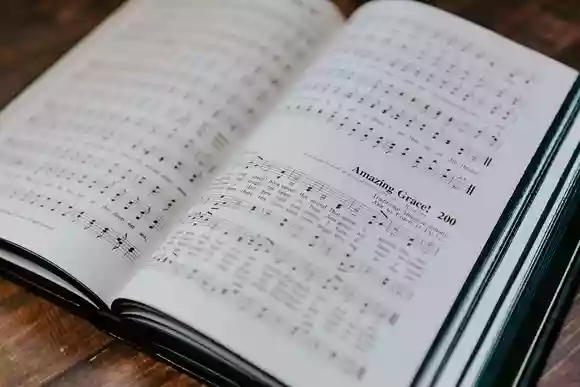
https://unsplash.com
使い方としては、主に3つあります。
- フレーズの頭で、本来の音程の半音または一音下(あるいは上)から滑らかに(ある程度勢いをつけて)狙った音程まで移動します。
これが一番よくみられる「やりすぎ」の原因にもなりますので気をつけてください。
- フレーズの途中で、離れた音の間を音程を滑らかに変化させながらつなぎます。
人によっては「スラー」と呼ぶこともあります(厳密には異なります)。
- フレーズの最後の音を伸ばす際に、最後の瞬間に音程をなめらかに落としながら(もしくは上げながら)音を切る、あるいはフェードアウトします。
使い過ぎ注意!
特にポップスを演奏するときなど、簡単に「うまい」と思わせることのできるしゃくりですが、多用しすぎるととてもくどくなってしまいます。
また、ビブラートと同様に出だしの音程をごまかせるため、慣れすぎてしまうといざストレートに吹こうと思ったときに音程がとれない!
ということになりかねません。
一度癖がついてしまうと矯正するのはとても時間がかかります。
基本はストレートに狙った音程をバシッと当てて吹きながら、ここぞというところで効果的に使えるとかっこいいですね。
今回のまとめ
- 口笛中級者はしゃくりを多用しがち!
- 上がるときは「うゆ」、下がるときは「ゆう」
- フレーズの頭、終わり、途中で、上がるときにも下がるときにも使える
- 意識して、使うべきところでだけ使うようにしよう
一度できるようになると楽しくてついつい使いすぎてしまいますが、一音一音を意識して、コントロールを確実にしていきましょう。