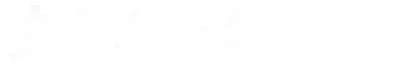【文化祭・学園祭】謎解きゲームの作り方やコツ
子供から大人まで人気を集めている謎解き!
各地でイベントが開催されるほか、謎解き問題を扱ったテレビ番組などもあり、たくさんの人がその魅力にハマっていますよね。
そんな謎解きを文化祭や学園祭の出し物に取り入れたい、と考えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、文化祭の出し物に使える謎解きの作り方を紹介します!
問題やストーリー作りのコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
どこのイベントにも負けない、楽しい謎解きを作りましょう!
- 文化祭で脱出ゲームをしたい!リアル脱出ゲームの作り方とコツ
- 【文化祭・学園祭】教室でできる珍しい出し物
- 【小学生向け】暗号クイズ。面白い謎解き問題
- 【文化祭・学園祭の出し物に】迷路のオススメのアイデア・トラップ
- 縁日やバラエティ番組顔負け!?文化祭・学園祭で盛り上がるゲーム
- 【文化祭】出し物の人気ネタランキング
- 【高校生向け】文化祭でオススメの出し物まとめ
- 【ひっかけクイズ】子供から大人まで盛り上がるクイズ問題
- 文化祭・学園祭で盛り上がるレクリエーションまとめ
- 【文化祭でカジノ】カードやサイコロなど定番のカジノゲームを紹介
- 【中学校】文化祭の出し物。人気の展示やゲーム、ステージ発表まとめ
- 【文化祭】ジェットコースターを作ろう!
- 高校生だから作れる!?文化祭のアトラクションアイデア
ストーリー作りのコツ(1〜10)
現実的なイメージしやすい内容にする
ストーリーを決める上で、謎解きゲームは非現実的な世界観よりも、日常でありそうな現実タイプの内容にするのがオススメです。
いくらストーリーが大切といえども、謎解きゲームの肝は謎解きです。
非現実的すぎるストーリーにすると、本来重きを置きたい謎よりもストーリーの方が力を持ってしまいます。
そのため、なるべく現実的な内容で製作する方が好ましいといえるでしょう。
教室や電車内、スーパー、家など、よく過ごす場所をストーリーの拠点とし、そこで起こる謎や事件という形でストーリーを作ってみましょう。
5W3Hを意識して作る
どういうストーリーなのかを明確に表すために、5W3Hは重要です。
5W3Hの5Wとは、日時を表す「when」、場所を表す「where」、人を表す「who」、物などを表す「what」、理由を表す「why」。
そして3Hは、方法を表す「how」、どれぐらいの量かを表す「how many」、お金がいくらかを表す「how mucu」が3Hです。
つまり、誰がいつどこで何をどうしておこなったのかを明確にし、それをどんな方法を使って何分、何時間で謎を解き、答えた先にはどんなご褒美が待っているのかを明確にすることが大切なのです。
ストーリーを作る際には、ぜひこの部分もしっかり考えてみましょう。
謎解き問題の作り方(1〜10)
次は、謎解きの問題の作り方を紹介します。
実際のイベントやテレビなどで公開されている問題を見ると、自分で作るなんて難しそうと思う方も少なくないでしょう。
謎解きの問題は、基本的に答えを考えてから逆算して問題を作ります。
小さいころに遊んだなぞなぞのように、問題作りも答えから発想をいろんなところに飛ばすことで作れます。
ここからは問題作りの考え方を詳しく紹介していきますね。
誰もが楽しく謎解きに取り組めるような問題を作ってみてくださいね。
謎を解くための法則を考える
先に問題の答えを決めたら、次に問題を解くための法則を考えておく必要があります。
その法則の中でも、もっとも一般的なものが変換です。
つまり、問題文やキーとなりそうな部分をひらがなからカタカナ、漢字や英語に変換したり、問題のイラストを文字に直してみたりすることが変換です。
よくテレビのクイズ番組などでもこういった法則を使って解く問題が出てきますよね。
問題を作るときには「どのような法則を使って解いてもらうのか」をしっかり考えておくことで、お客さんにひらめきを与え、楽しく問題に取り組んでもらえます。
答えと謎解きの法則をつなげて問題文を作る
答えと問題を解く法則が決まったら、いよいよ問題作りの本番です。
法則を用いて答えにたどり着けるように問題文を考えましょう。
しかし、問題を考えていると、こじつけのような問題が出来上がってしまうこともあります。
そうなってしまうとお客さんの気持ちも冷めてしまうので、答え合わせをしたときに誰もが納得できるよう、しっかり時間をかけて問題を考えていきましょう。
問題の作り方のコツ(1〜10)
次は、謎解きの問題を作る際のコツを紹介します。
問題をただ作って解いてもらうだけでは、ゲームとして単調になりがちです。
しかし、ちょっとした工夫を加えることで、ゲームはより楽しくなり、もっともっとと興味もワクワクも感じてもらえます。
簡単にできる工夫ばかりなので、問題を作ったらぜひ取り入れてみてくださいね。
また、全体のストーリーとも絡めながら問題の出し方、表示の仕方を工夫すると、ストーリーの世界観も尊重できますよ!
問題を解きたくなるような形で表示する
お客さんに楽しく謎解きをしてもらうためには、問題の見た目も大切です。
ただただ問題が書かれてそこにあるだけのものより、色や書体、問題の設置の仕方などが工夫されているものの方が、やってみたい!という気持ちが湧いてくるという方が多いのではないでしょうか。
そこにただ問題があるだけ、というスタイルがストーリーに沿っていればいいですが、そうでない場合はお客さんにより楽しんでもらうためにも、少し工夫が必要です。
みんなで協力して問題の表示方法などを工夫しましょう。
問題の中に違和感を持たせヒントにする
謎解き問題を解く一つのコツとして、問題の中に隠れた違和感に気付くというのが重要です。
その違和感を問題の中に作るのが、ドキドキワクワクする謎解き問題を作る上での重要なコツでもあります。
たとえば、「この絵の中にこれがあるのはおかしい」「この文章にこの表現って変じゃない?」「これは何かに変換できそうだ」などが、違和感となるようなポイントです。
これらの違和感となる部分をキーにすることで謎が解明される、といった形を作りましょう。
違和感はわかりやすすぎてもすぐに謎が解けておもしろくないので、ちょっと考えてわかるような絶妙なポイントを探ってくださいね。
イラストを使う
謎解き問題には、イラストがとても役に立ちます。
問題をわかりやく表現できるというのもありますが、問題を解く法則にたどり着いてもらう際にもイラストは便利です。
文字だけで表すよりも絵の方が、いろんな解釈がしやすくなります。
たとえば、一つの丸いのイラストがあった場合に、見る人によってはボールに見えたり、スイカに見えたり、ただの円に見えたりさまざまです。
こうしたいろんな解釈を探っていく中で法則が見つかり、答えにもたどり着けます。
いろんな解釈で惑わせたい、逆に法則にたどり着きやすくしたい、というときはぜひイラストを活用してみてくださいね。