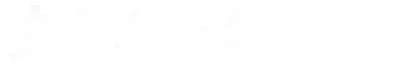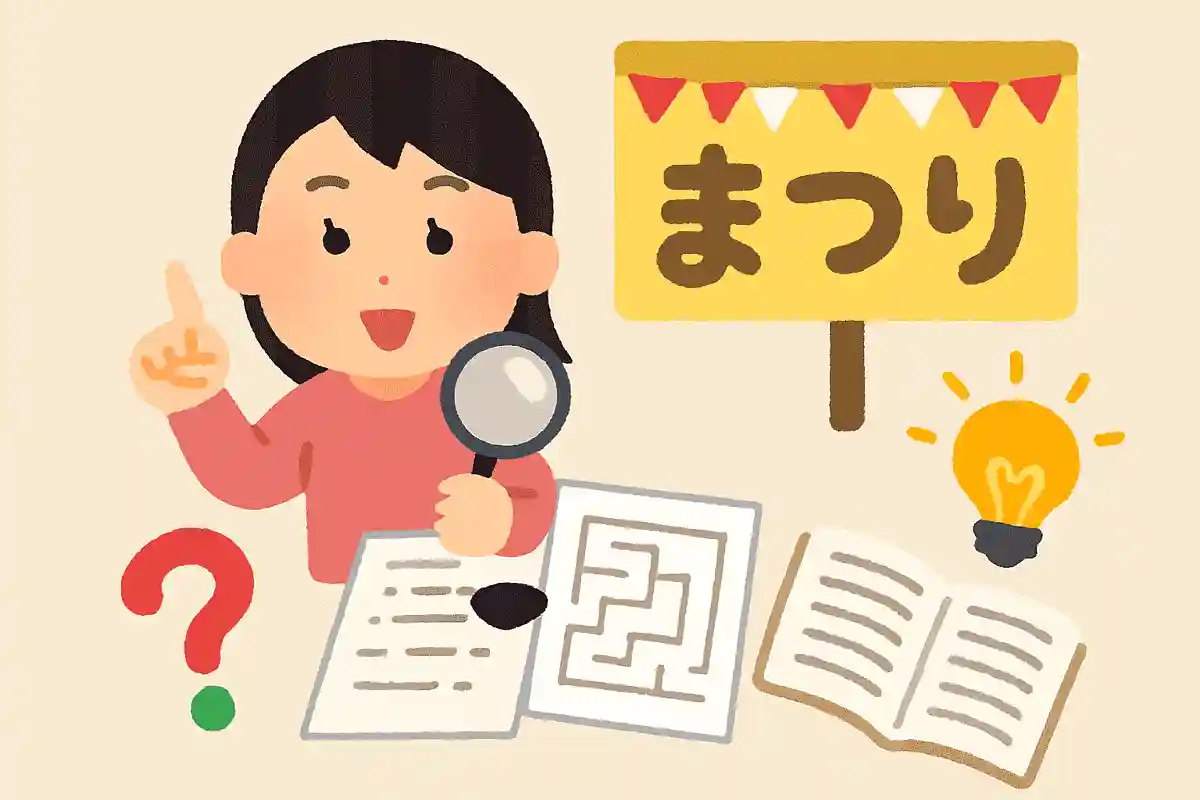【文化祭・学園祭】謎解きゲームの作り方やコツ
子供から大人まで人気を集めている謎解き!
各地でイベントが開催されるほか、謎解き問題を扱ったテレビ番組などもあり、たくさんの人がその魅力にハマっていますよね。
そんな謎解きを文化祭や学園祭の出し物に取り入れたい、と考えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、文化祭の出し物に使える謎解きの作り方を紹介します!
問題やストーリー作りのコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
どこのイベントにも負けない、楽しい謎解きを作りましょう!
初めにやること(1〜10)
まずは、謎解きを作るときに1番初めにやることを紹介します。
「こういうことがしたいな」と思っていても、土台となる部分がちゃんと決まっていないとうまく完成しなかったり、完成してもおもしろくないものができてしまうこともあります。
文化祭や学園祭に来てくれる人はもちろん、製作者側も楽しくなければ意味がありません。
みんなで思い出に残る文化祭にするために、まずはこれから紹介することをしっかり決めてから、細かな部分を詰めていくようにしましょう。
会場を決める
謎解きゲームを作る際にまずやらなければならないことは、会場決めです。
学校であれば教室や体育館、音楽室や視聴覚室などの特別教室など、さまざまな部屋がありますよね。
他のクラスの出し物との兼ね合いもありますが、自由に選びやすい環境であれば、作りたいイメージにあった場所を選びましょう。
また、会場を選ぶ際にはそこにあるものをどう使うか、使わないもので撤去できるものは撤去してしまうのかも決めておかなければいけません。
さらに動線も考慮して、会場を選びましょう。
回答者のターゲットを決める
謎解きゲームを主にどういう人にやってほしいか、ターゲット決めが大切です。
文化祭には、同世代や保護者の方世代、または兄弟の世代など、来られる方の年齢層は意外に幅広いというのを頭に置いておかなければいけません。
その中でもとくにこの世代の人に楽しんでほしいというターゲットを決めておくと、難易度の設定や問題に取り入れるテーマ決めなど、問題作りの際に役に立ちます。
年齢層を決めたからといって、それ以外の人は参加できないということにする必要はありませんが、ある程度のターゲットをしぼっておくことで、全体にまとまりできるでしょう。
ストーリーを考える
謎解きゲームを作る際、謎解きの問題をひたすらに解いてもらうというスタイルもいいかもしれませんが、ストーリーを作るとさらに楽しいゲームが出来上がります。
ストーリーは、異世界や現実にはあまり経験できない状況を作り出す非現実型。
そして、学校や会社、家での日常を切り取ったような現実型と大きく2パターンあります。
謎解きゲームは謎解きが主な目的なので、あまり現実離れしすぎていない、現実に近いストーリーの方がオススメです。
非現実型で作る際は、謎解きの問題がしっかり生きる形で作りましょう。
謎と仕掛けの量を決める
ストーリーが決まったら、作ったストーリーの中に謎解き問題をどのくらい用意するかを考えなければいけません。
また、謎解き問題を解くことで起こる仕掛けについても一緒に考えておきましょう。
やみくもに作りたいだけ作っても、それでは謎を解く側のお客さんは飽きてしまい、結果的に楽しくない出し物になってしまいかねません。
そのため、考えるストーリーにどれだけの問題を作り、どういった仕掛けを付随させていくのかということは、最初に決めておくべきところでしょう。
大きな謎を考える
謎解き問題を考える際は、まずストーリーの根幹となる大きな謎から考えましょう。
全体にちりばめられた細かな謎を解くことで、最終的にゴールでストーリーに詰まった大きな謎が解明される、といった形にしてみましょう。
たとえば、ミステリー系のストーリーにする場合に、ゲームの中の謎を一つずつ解いていくことで犯人がわかる、この犯人の解明を大きな謎にする、といった形です。
こちらは、ストーリーを決める段階である程度この出し物にはどんな謎、秘密を持たせるのかを考えておくのがいいでしょう。
小さな謎を考える
全体に包まれる大きな謎を考えたら、大きな謎を解くまでの道のりとなる小さな謎を作っていきましょう。
大きな謎にたどり着くための指示になるような謎、ヒントとなるような謎など。
注意しなければならないのは、必ずストーリーや大きな謎に沿った内容にするということです。
お客さんにしっかりゴールにたどり着いてもらうために、問題の内容は難しくても解ければちゃんと道が開けるような謎を用意しましょう。
答えの入力の仕方を考える
謎解きの問題を解いてもらった後に、どこにその答えを示してもらうのかを決めておきましょう。
問題が出題されるポイントにそれぞれスタッフを配置し、スタッフに答えを示して正解かどうかを確認してもらうのも一つの方法です。
しかしストーリーの世界観的に、あまりスタッフを各所に配置したくないという場合は、タブレット端末を利用して問題の正解を確認してもらうという形もいいでしょう。
そのほか、ナンバーロックに答えの数字をセットすると次の扉が開く、正解が書かれたボタンを押せば次に行ける、などの仕掛けを作って答えを入力してもらうのもオススメです。
ストーリー作りのコツ(1〜10)
次は、謎解きのストーリーを作る際のコツを紹介します。
謎解きゲームの中で問題と並んで重要になるのが、ストーリーです。
そのため、問題の作成と同じくらい悩んでしまうところだと思います。
ストーリー作りに悩んでいる方は、ぜひこれから紹介する内容を参考にしてみてください。
また、近くで謎解きイベントが開催されている場合は、実際のイベントに足を運んでみるのもオススメです。
問題はもちろん、描かれるストーリーそのものも楽しんでもらえるようにしましょう!