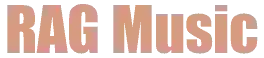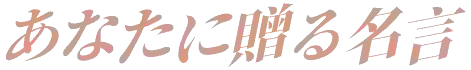美しくも恐ろしい…童磨の名言。狂気と博愛が同居する言葉たち
『鬼滅の刃』の鬼の中でも特異な存在感を放つ上弦の弐、童磨。
その明るく気さくな振る舞いとは裏腹に、冷酷な性格と深い洞察力を隠し持っているキャラクターです。
時に残虐で、時に美しく、そして人のもろさを鋭く突く彼の名言には、はっとさせられた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、童磨が物語の中で残した印象的な言葉をご紹介します。
狂気さを感じずにはいられないその言葉の数々に、あなたは背筋を寒くさせながらも魅力を感じてしまうはず!
美しくも恐ろしい…童磨の名言。狂気と博愛が同居する言葉たち(1〜10)
命というのは尊いものだ。大切にしなければ
https://www.tiktok.com/@anicinemelodies/video/7509553765905599766後に上弦の陸となる妓夫太郎と堕姫に対し、鬼になることを誘った時の名言「命というのは尊いものだ。
大切にしなければ」。
殺害した遊女を喰いながらの説得力を欠いたセリフは、童磨というキャラクターの狂気や不気味さを演出していますよね。
生き死にに対しての感情が著しく欠落している童磨にとっては、2人が鬼になろうが死のうがどちらでも良かったのではないでしょうか。
当時上弦の陸だった童磨が上弦の弐にまでなっていることから相当数の命を奪っている童磨の、心を感じない名言です。
全部全部無駄だと言うのにやり抜く愚かさ。これが人間の儚さ素晴らしさなんだよ
蟲柱・胡蝶しのぶの攻撃を全て無効化し、捕らえた時に発せられた名言「全部全部無駄だと言うのにやり抜く愚かさ これが人間の儚さ素晴らしさなんだよ」。
「姉さんより才も無いのによく鬼狩りをやってこれたよ 今まで死ななかったことが奇跡だ」から続くセリフで、童磨がいかに人間を見下しているかが分かりますよね。
同じ見下しているでも他の鬼と決定的に違うのは、挑発ではなく言葉どおりの思考であることではないでしょうか。
言葉とともにその強力さや残酷さを感じさせる名言です。
君は俺が食うに相応しい人だ。永遠を共に生きよう
全力を出し切った蟲柱・胡蝶しのぶに対して発した名言「君は俺が食うに相応しい人だ 永遠を共に生きよう」。
圧倒的実力差があるにもかかわらず諦めない意志の強さと、鍛え上げられた身体能力に対し、童磨なりの敬意を込めたセリフなのではないでしょうか。
もともと女性を喰うことに異常な執着を持っている童磨にとって、これ以上ない獲物であると考えているのが見えますよね。
その余裕が後に自分を追い詰めることになりますが、それも含めて童磨らしさを感じさせる名言です。
情報は有益。使える技も出しきらせて殺す
自身が放った血鬼術を吸わずに戦い続ける嘴平伊之助に対して向けた名言「情報は有益 使える技も出しきらせて殺す」。
軽薄でありながらも冷静に戦局を把握し、戦力を分析する童磨の高い戦術眼が分かるセリフですよね。
普段から常に余裕を感じさせ、あまり深く物事を考えていないような雰囲気を出していますが、この観察力こそ童磨の強さを支えているのでは無いでしょうか。
長きにわたり上弦の弐として君臨するのも納得の名言です。
極楽なんて存在しないんだよ。人間が妄想して創作したお伽噺なんだよ
人間であった頃の童磨が子供である自分を崇める大人に対して思った名言「極楽なんて存在しないんだよ 人間が妄想して創作したお伽噺なんだよ」。
両親に特別な存在だと信じられて教祖に据えられ、大人から死後に極楽へ導いてほしいとすがられ続けたことから生まれた思考を表したセリフですよね。
現代よりも神仏の存在が重要視されていたことから考えると自然なのかもしれませんが、こうした環境が童磨の性格や考え方をゆがめてしまいました。
相談された内容ではなく、その考え方自体に同情するような名言です。
何も感じない。死ぬことが怖くもないし、負けたことが悔しくもない
自身の死に直面しても心が揺るがない童磨の思考が見える名言「何も感じない 死ぬことが怖くもないし、負けたことが悔しくもない」。
その環境もあり人間であった頃から人としての感情が欠落していた童磨らしいセリフなのではないでしょうか。
両親が壮絶な死に方をしても他人事のように感じていた童磨は、最期の時まで人間が抱く感情を理解できませんでした。
童磨というキャラクターの一貫した不気味さと存在感を表している名言です。
悲しい。一番の友人だったのに……
上弦の参・猗窩座の死に気づいた時の名言「悲しい 一番の友人だったのに……」。
性格も考え方も自分と正反対であるが故に何かと絡んでいた猗窩座に対して涙を流しながら発したセリフですが、その後栗花落カナヲに本当は何も感じていないのに上辺だけのことを口にしていると見破られてしまいます。
しかし、陽気かつフレンドリーでありながら仲間内にも言動を流されてしまう童磨にとって、何かしらの反応が返ってくる猗窩座の存在は、もしかしたら本人も気付かぬうちに特別になっていたかもしれませんね。
後に見えてくる童磨のキャラクターを象徴する名言です。