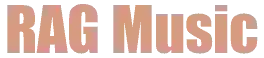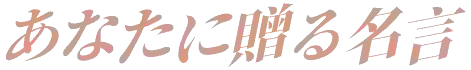20世紀最高の物理学者、アルベルト・アインシュタインの名言
理論物理学者や社会主義者として数多くの功績を残し、その名を歴史に刻んでいるドイツ出身の偉人、アルベルト・アインシュタインさん。
今回は、そんなアルベルト・アインシュタインさんが残したとされている名言をご紹介します。
さすが物理学者と感じてしまうものから、誰もが納得してしまうものまで、幅広くリストアップしてありますよ。
落ち込んでしまった時や心が折れそうな時に寄り添ってくれる言葉ばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね!
20世紀最高の物理学者、アルベルト・アインシュタインの名言(1〜10)
どんな条件であれ、私には確信がある。神は絶対にサイコロを振らない。アルベルト・アインシュタイン

アルベルト・アインシュタインが20世紀最高の物理学者と呼ばれたことにもつながる、不確定とされているものへの考え方を示した名言です。
量子力学においては同じ実験でも違う結果が出る場合があるものとされていましたが、これに反抗するようにして世界の現象には不確実なものなどないのだという意味で、この言葉が放たれました。
実験の条件という意味が強い言葉ではありますが、神様の気まぐれはないという点で、何事にも正しい評価や目線が必要だという意味にもとらえられます。
当時の量子力学のように、運で片付けてしまうのではなく、しっかりと分析して進めていくことがより良い未来につながるのだという、前向きな呼びかけにも思えてくる言葉ですね。
何かを学ぶのに、自分自身で経験する以上に良い方法はない。アルベルト・アインシュタイン

学びを進めていく際には、誰かが重ねてきた経験、誰かが提唱した理論に触れることもあるかと思います。
そんな学習の常識とも言える誰かの体験をなぞる方法に、あえて疑問を投げかけているような名言です。
なによりも大きな学びになるのは自分の体で実感した経験で、これがより良い学びや、新しい発見につながる方法なのだと語りかけています。
机の上で理論を展開するだけでなく、ときには体を動かして学びを得ることも必要だと思わせてくれるような言葉ですね。
天才とは努力する凡才のことであるNEW!アルバート・アインシュタイン
相対性理論を提唱し、「20世紀最大の物理学者」とも呼ばれるアルバート・アインシュタイン。
この名言は、生まれつき特別な才能がある人だけが天才なのではなく、地道な努力を積み重ねられる人こそ、本当の意味での才能があるのだと教えてくれます。
受験勉強も同じで、「自分は向いていない」と感じることがあっても、あきらめずに続ける姿勢が力になります。
テストの点よりも、「昨日より少し理解できた」という前進の方が大切なんですよね。
天才と称されたアインシュタイン自身も、失敗と試行錯誤を重ねてきた人物。
努力を続ける自分を信じたい受験生に、寄り添ってくれる言葉です。
学校で学んだことを一切忘れてしまった時に、なお残っているもの、それこそ教育だ。アルベルト・アインシュタイン

教育といえば学校で習うものというイメージが強く、それが教育のすべてだという考えを持ってしまう人も多いかもしれません。
そんなイメージを持っている人に考えるきっかけをくれる、教育とは何かという考え方を示した名言です。
教育というのは勉強した内容よりも、勉強をとおして身に着けた調べ方や感情の動きが大切、それが人生に大きく影響を与える要素なのだと語りかけています。
勉強の内容を忘れた際に何が残るのかを、自分の中で振り返れば、本当に大切なものが見えてくるかもしれませんよ。
間違いを犯したことのない人とは、何も新しいことをしていない人だ。アルベルト・アインシュタイン

相対性理論を提唱した著名な物理学者アルベルト・アインシュタインの名言を紹介します。
アルベルト・アインシュタインは、「間違いを犯したことのない人は、新しいことに挑戦していない人だ」という言葉をのこしています。
これは、失敗を恐れずに新しいアイデアや冒険に挑むことが大切だという意味です。
誰でも最初はうまくいかないことがありますよね。
そこから学んで成長することが大切。
失敗するのが怖くなったときはこの言葉を思い出して、いろいろなことにチャレンジしてみてくださいね。
弱点は、いずれキャラクターになるアルベルト・アインシュタイン

天才として語り継がれるアルベルト・アインシュタインにも、数字や記号をおぼえるのが苦手だという弱点があったとも言われています。
そんな誰もがかくしたくなるような弱点に、ポジティブなものとして向き合うきっかけを与えてくれそうな名言です。
弱点は解消したり乗りこえたりするものというイメージが強いですが、場合によってはそれを許してともに生きていくことで、キャラクターにもなり得るのだと語りかけています。
気になっている弱点が乗りこえるべきものか共存していけるものか、弱点にしっかりと向き合うきっかけにしてみるのはいかがでしょうか。
天才とは努力する凡才のことであるアルベルト・アインシュタイン

天才として語り継がれている人の言葉だからこそ説得力がある、天才がどのように生まれるのかを示した名言です。
凡才が努力を重ねていくことによって天才と呼ばれる、その努力への姿勢こそが天才への条件なのだと語りかけています。
誰でも天才になれるのだという事実とともに、努力を重ねられる素質によって天才になれるかが分かれるのだと伝えていますね。
才能がないとあきらめずに、努力を重ねて成果向かっていこうという希望を与えてくれる言葉です。