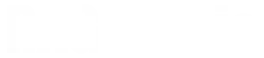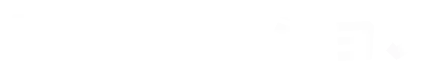季節と行事のクイズ特集。高齢者と一緒に笑顔あふれる時間を
四季折々の美しさを感じられる日本では、季節の移ろいとともにさまざまな行事が私たちの暮らしを彩っています。
春の桜祭りから夏の七夕、秋の月見、冬の年末年始まで、それぞれの季節には豊かな文化と伝統が息づいていますよね。
そんな季節や行事をテーマにしたクイズは、懐かしい思い出を呼び起こし、自然と会話が弾むステキなレクリエーションです。
今回は高齢者の方に盛り上がっていただける、季節と行事にまつわるクイズをご紹介します。
昔から親しまれてきた風習や食べ物の意味など、知っているようで意外と知らない豆知識もたくさん登場しますよ。
- 【高齢者向け】夏祭りの雑学クイズ&豆知識問題。知識が増える楽しいクイズNEW!
- 日本文化・地理・健康がテーマ!高齢者の方が笑えるクイズ特集NEW!
- 高齢者と楽しもう!食べ物・料理の盛り上がるクイズ集NEW!
- 【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がるNEW!
- 高齢者が盛り上がる!雑学豆知識クイズで頭も心もすっきりNEW!
- 昭和のレトロで懐かしい笑えるクイズ。高齢者の方と楽しむ思い出話NEW!
- 昭和レトロが懐かしい!高齢者の方に盛り上がるクイズ特集NEW!
- 【どこまで知っている?】高齢者の方向け・昭和文化と生活の豆知識健康雑学クイズNEW!
- 高齢者の方が楽しく学べる!健康クイズで盛り上がる時間をNEW!
- 【高齢者向け】動物と自然をテーマにした盛り上がるクイズ集NEW!
季節・行事クイズ
柏餅にはどのような願いが込められているでしょうか?NEW!
こどもが健やかに成長していくことを願うこどもの日は、5月を代表する祝日ではないでしょうか。
そんなこどもの日は、かしわ餅やちまき、ちらしずしなどのさまざまな食べ物でお祝いの気持ちを表現しますよね。
またそれらの食べ物は、季節に合っているというだけでなく、こどもの日にちなんだ意味が込められており、こどもの日の代表的なお菓子であるかしわ餅にも意味があります。
柏の木や葉っぱの、新芽が出るまで古い葉が落ちないという特徴にちなんで、「家系がたえない」や「子孫繁栄」などの意味を表したものと言われています。
毎年8月16日に京都で「大文字」「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」の順に山に火が入れられるこの行事。何と呼ばれる行事でしょうか?NEW!
毎年8月16日に京都で「大文字」「妙法」「船形」「左大文字」「鳥居形」の順に山に火が入れられるこの行事、何と呼ばれる行事でしょうか?
答えは「五山の送り火」です。
京都の夏の有名な伝統行事で、お盆の精霊を送り出すためにおこなわれています。
毎年この行事を見に、多くの方が観光客として京都を訪れるんですよね。
テレビでもよく中継されていますが、暗闇にゆらゆらと揺れる火の文字は美しく、とても力強く感じられます。
一度は見たいと感じる、お盆の行事ではないでしょうか。
満月から少し欠けた月を見る、別名「豆名月」や「芋名月」と呼ばれるお月見のことを何というでしょうか?NEW!
満月から少し欠けた月を見る、別名「豆名月」や「芋名月」と呼ばれるお月見のことを何というでしょうか?
答えは「十三夜」です。
お月見といえば9月におこなう十五夜が有名ですが、実は10月頃におこなうお月見もあるんですよね。
それがこの十三夜です。
実は十五夜は中国伝来の風習で、十三夜は日本の風習。
どちらも月を見て楽しむというのに変わりありませんが、十三夜は秋の収穫に感謝するといった意味合いがあります。
9月のお月見ができなかった方は、ぜひ十三夜を楽しんでみてはいかがでしょうか?
ひなまつりは元々何を祈願して始まったでしょうか?NEW!
3月3日のひなまつりは、もともと女の子の厄払いと健やかな成長を祈願して始まりました。
中国から、じょうしの節句という水辺で身を清める厄払いが日本に伝わってきました。
そのことが平安時代には紙の人形にけがれを移して川に流す流しひなへと発展していきました。
時代が変わるにつれて人形が屋敷の中に飾られるようになっていきました。
このことから、ひなまつりは女の子の健やかな成長と幸せを願うひな祭りに変わっていったと言われております。
夏のイベント「肝試し」は何時代から始まった文化でしょうか?NEW!
夏の夜に行われることが多かった肝試し。
今は遊園地などでもアトラクションとして肝試しエリアを設置しているところも多くみられますよね。
肝試しは平安時代から始まった文化と言われております。
歴史物語の大鏡には花山天皇が藤原道長ら臣下たちに恐いといわれている場所へ行かせ、その度胸を試す「肝試し」のようなお話が書かれています。
平安時代の貴族といわれている人たちの間ではもののけや鬼神は実際にいると信じられ不吉な出来事などはそのことから起こるといわれていました。
肝試しは昔の人たちにとって命がけのことだったといわれています。