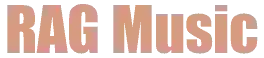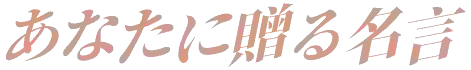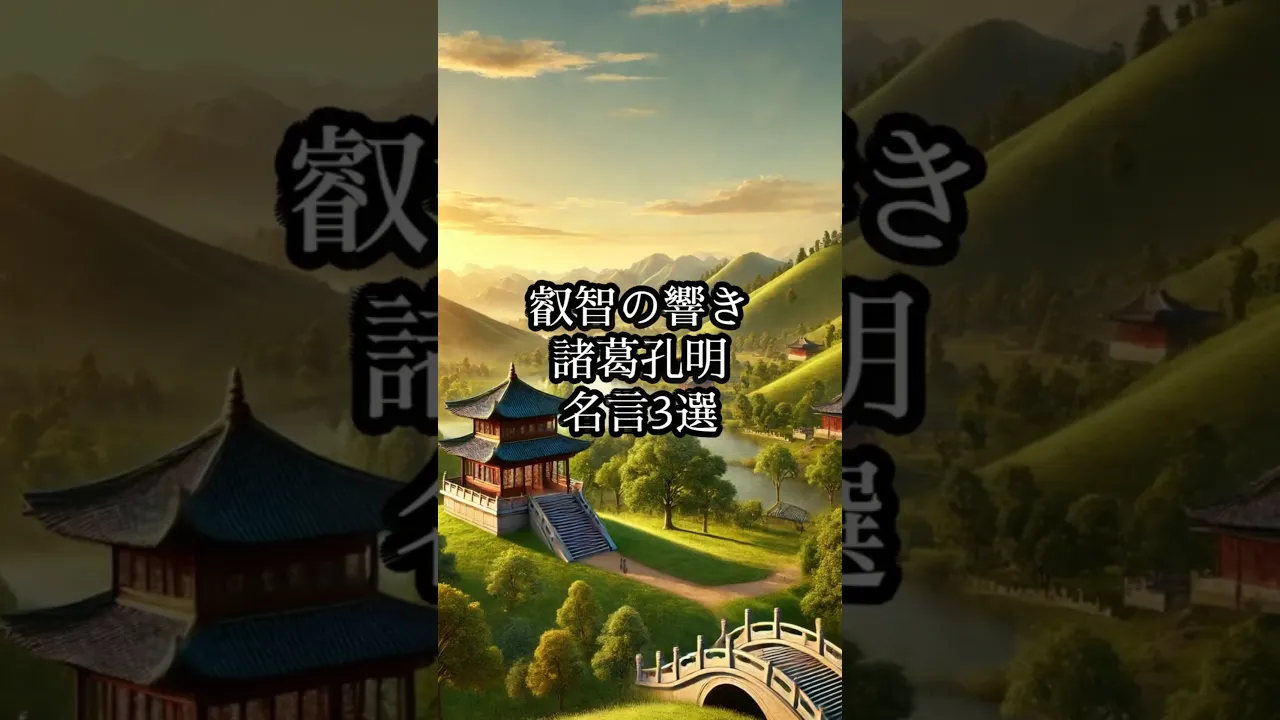言葉から哲学や生き様が見える。歴史上の人物による短い名言
偉業を達成し、歴史にその名を刻んだ人物と聞かれたら、誰を思い浮かべますか?
現代では当たり前になっているものや考え方を生み出した人や、文化の礎を作った人など、学生時代に習った方もきっと多いですよね。
今回は、そんな歴史上の人物の中でも、誰でも名前くらいは聞いたことがあるであろう特に有名な偉人が遺した短い名言をリストアップしました。
それぞれの哲学や生き様が見える名言ばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね!
言葉から哲学や生き様が見える。歴史上の人物による短い名言(1〜10)
優れた人は静かに身を修め、徳を養なう諸葛孔明

三国史の時代に活躍した諸葛亮孔明は、軍師として蜀のために尽力したことで知られ、数々の伝説と合わせて語り継がれています。
そんな歴史的な軍略家が残した、優秀な人はどのように行動しているものなのかという考え方を示した言葉です。
表に立ってアピールする人が優秀と思われがちですが、本当に優秀な人は静かに自分を高めているものなのだと主張しています。
静かに努力を重ねていける人こそが優秀なのだという、努力の大切さも呼びかけているような言葉ですね。
進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。福沢諭吉

幕末から明治の日本で教育者として活躍した福澤諭吉は、一万円札の肖像画に起用されたことも有名で、慶應義塾の創設者としても知られてますね。
そんな日本の教育のために尽力した人物が残した、進む人と立ち止まる人についてを語った言葉です。
進み続けるためには、退かないという前向きな姿勢がなによりも大切で、その意思を持ち続けた人こそが目標にたどり着けるのだと伝えています。
自分がかかげた理想や、自分のことをしっかりと信じることが大切なのだという呼びかけにも感じられるような言葉ですね。
小を積んで大を為す二宮尊徳

江戸時代の後期に農政家や思想家として活躍した二宮尊徳は、学び続ける姿勢を表現した二宮金次郎の像のモデルとして知られていますね。
そんな生涯にわたって学びを続けてきた人物が残した、積み重ねていくことの大切さを語った言葉です。
まずは小さなことを積み重ねていくのが重要で、その信じて積み重ねていった先にこそ、大きな成果が待っているのだと伝えています。
あきらめない努力の姿勢、自分を信じて進んでいくことの大切さもあわせて教えてくれるような言葉ですね。
歩け、歩け。続ける事の大切さ伊能忠敬

江戸時代に名主の子として生まれ、商人や地理学者として活躍した伊能忠敬は、日本全国を測量して地図にすることを目指した人物としても知られていますね。
そんな測量に時間をかけてきた人物だからこその説得力がある、続けていくこと、歩き続けていくことの大切さを語った言葉です。
結果がどのように出るのかがわからなくても、信じて進み続けることが重要で、あきらめずに進めていった先にこそ大きな成果が得られるのだと伝えています。
周りの目を気にすることはなく、自分を信じて進んでいくべきだという呼びかけにも思えてくる言葉ですね。
笑われて、笑われて、つよくなる。太宰治

昭和の初期を中心に小説家とて活躍した太宰治さんは、代表的な作品として『走れメロス』や『人間失格』などが知られていますね。
そんな偉大な文豪が残した言葉の中でも、苦しみを経験したからこその強さという部分に注目した言葉です。
周りから笑われるというマイナスの経験があったとしても、それを乗りこえて進んでいくことが強い人間を作るのだと語りかけています。
強さを得るためには、苦しみから学びを得るのも大切だという呼びかけにも感じられるような言葉ですね。
もう一押しこそ慎重になれ武田信玄

戦国時代の武将として活躍した武田信玄は、現在の山梨県にあたる甲斐をおさめ、甲斐の虎の異名でもおそれられていました。
そんな戦国武将の中でも大きな力を持っていたとも言われる人物が残した、油断しないことがどれほど大切なのかを語った言葉です。
目標としていたものが目前に迫った時にこそ気が緩みやすいので、最後のもうひと押しほど、より慎重に取り組むべきなのだと伝えています。
大きな力があっても油断しない、最後まで全力でやりきるのだという姿勢も強く感じられる言葉ですね。
環境より学ぶ意志があればいい。津田梅子

日本における女子教育の先駆者として評価されている津田梅子さんは、現在の津田塾大学の創設者としても知られています。
そんな女性の教育に尽力した偉大な教育者が残した、意志を持つことが何よりも大切だという考え方を語った言葉です。
自分が置かれている環境によって何かをあきらめる人が多い中、それでも意志さえあれば学びは得られるのだと伝えています。
自分の中にある気持ちを自覚して、それを貫ければ、大きなことも成し遂げられるはずだという前向きな気持ちもわいてくるような言葉ですね。