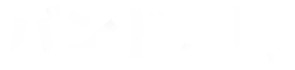お客さんに喜んでもらうために僕がレコ発ライブで工夫したこととその成果
全国のライブハウスで毎日のように行われているライブも、裏側を見るとさまざまな工夫があることが分かっていただけると思います。
ぜひ参考になればと思いますのでご覧ください。
イベントに対して僕がどう向き合ったか

僕がやっているバンドcolor chordのレコ発企画ライブ札幌編と苫小牧編が終了しました。
いろんな人に大変お世話になって、盛況のうちに終わった二日間。
この二日間のイベントに対して僕がどう向き合ったか、イベント作りにおいてどういう工夫をしたかについて書こうと思います。
ライブイベントは可能性がいくらでもあって、基本的な流れのテンプレートこそありますが、イベントの色はさまざまです。
結局はお客さんにいかに楽しんでもらうか、いかに喜んでもらうか、という部分を最大の目的にしてはいるんですが、そのアプローチにおいてやりようがいくらでもある。
この二日間のイベントでどういったアプローチをして、どういった成果があったかを書いていこうと思います。
僕のバンドのことを知らない人も、インディーズバンドのライブがどうやって作り上げられていくのかを垣間見ることができると思います。
始めたてのバンドマンは参考にしたり、先輩バンドマンは助言したりしてくれたら、この記事を書いた意味があるってもんです。
よろしくっす!
いくぜ!
1. そもそもレコ発とは
本題の前にまず、基礎知識の説明にちょっとお付き合いいただきたい!
レコ発とは、多分「レコード発売」の略です*1。
「レコ発ライブ」や「レコ発企画」、「レコ発」と若干表記が違う場合も意味合いはほぼ全部一緒で、CDの発売を記念して行われるライブのことです。
「CD発売記念」なのになぜか「レコ発」と呼ばれています*2。
せっかく時間と労力とお金をかけてCDを作ったんだから、盛大に発売記念パーティーをやろうぜ、という意味合いのライブのことですね。
お客さんの立場としても、「なんとなく自然とライブでCDを売り始めた」というより、「今日が記念のライブですよ!」と言われた方が、CDを買うタイミングがわかりやすいというのもあるんじゃないかという気がしています。
バンド側としては、予約して発売日に買ってくれるのもとてもうれしいんですけども。
「レコ発ツアー」とか「リリースツアー」となると、レコ発を冠して各地を回ることを指します。
日本各地に友達ができると楽しいし、何度もライブに足を運んでくれるお客さんが増えるとまた行きたくなります。
「自主企画」という言葉があれば、それはレコ発の主役バンドがライブを主催しているということです。
ライブハウスを決めたり、他の出演バンドを決めたりもバンドがやっているということですね。
自分で自分のお祝いパーティーを主催するという点では結婚式みたいなものですね*3。
ちなみに、今回のcolor chordのレコ発は、今年3月に全国発売した「くらし」というアルバムのレコ発でした。
全国流通について書いた記事もあります。
基礎知識は以上です。
それでは、実例を交えてご紹介します。
*1:どの業界にもある「慣例的に使われていて、本来の意味を考えることが放棄された言葉」の1つと考えていいでしょう。
*2:「C発」だとかっこ悪いから旧来の「レコ発」をいまだに採用しているんじゃないでしょうか。
*3:ちょっと違うか。
2. ホーム札幌の自主企画で、他とは”ちょっと違う”イベント作り

5月13日(金)に札幌REVOLVERでレコ発を行いました。
この日は自主企画なのでライブに関するほとんどのことを自分で決めました。
せっかく自分でいろいろ決められるということで、お客さんに楽しんでもらうようにいくつか工夫をしました。
1. 少ないバンド数でたっぷり贅沢なライブ
まずこだわったのはバンド数。
出演するバンド数を4組にして、1バンドの持ち時間を35分ずつにしました。
僕らがたまに出るようなライブハウス主催のブッキングだと、持ち時間25分で6バンドくらい出演というパターンが多いのだけど、この企画は僕の大好きな札幌のバンド3組と自分のバンドの計4組。
1バンドずつの時間を長めにすることによって、バンドの魅力をより深く体感できるライブにしようという狙いでした。
たっぷり贅沢なライブという感じです。
ちなみに出演したのは「青空教室」「スモゥルフィッシュ」「Os Banda」という札幌の素晴らしいバンドたち。
どのバンドも個性があって、もっともっと聴きたくなるくらいグッとくるライブでした。
35分でも短かったかーと思ってしまいましたが、でも長すぎてもイベントを通しで観たときに疲れちゃうし、「もっと聴きたい!」くらいが一番ちょうどいいという話もあります。
腹八分。
2. 演奏中以外も飽きさせないDJ&サプライズアクト
オープンしてからスタートするまで、そして転換中にもお客さんに楽しんでもらおうということで、DJをお願いしていい感じの曲をかけてもらいました。
普段は「エマローズ」という名義で弾き語りをしている「DJ過保護」。
みなさんが想像するようなクラブのアゲアゲDJではなく、DJが淡々とセンスのいい曲を繋いでいくことによって、演奏中以外の時間の空気作りをしてもらうという感じでした。
僕が知らないような、マニアックだけど超かっちょいい曲をたくさんかけてくれて、良い雰囲気の中イベントが進んでいきました。
バンドの演奏が終わって、次のバンドの準備中にどんな曲がかかるかで会場の雰囲気が結構変わったりするので、何気にイベントを左右する部分でもあるんです。
無意識のうちにお客さんは空気を感じ取っていたり、または意識的に「この曲かっこいい!」となったり、転換中というのもイベントに含まれているなと感じます。
そして1バンド目が始まる前のオープン中の時間には「エマローズ」として弾き語りもしてもらいました。
エマローズの出演はイベント当日に急に発表しました。
こういう突発的なアクトがあるとテンション上がったりしませんか。
めちゃくちゃ良く言うと、フェスとかでスカパラのライブに急に甲本ヒロトとか奥田民生が出てきたらテンションが上がるような、そんなサプライズのイメージです。
オープン中に始めてもらうことによって、その時間を目指して来てくれるお客さんも増えるので、イベントの頭からそこそこお客さんが入っている状態も作れました*4
実際エマローズはめちゃくちゃ良いライブをしてくれて、イベントは最高の滑り出しを見せました。
*4:インディーズバンドがたくさん出演するようなイベントだと、イベントの頭の方はお客さんが少なくて、後半どんどん増えてくる、という現象が起きがちです。
4. 来場者全員に記念品をプレゼント
お客さんみなさんにサイン&格言*5入りポスターをプレゼントしました。
今日のイベントの記念として、モノを持ち帰ってほしいなという気持ちでした。
結婚式でいう引き出物みたいなものですね*6。
当日急にプレゼントすることにしたので荷物になっちゃって申し訳ないかなとも思ったんですが、部屋にポスターを貼った写真をTwitterにアップしてくれている方もいたので、少なくとも喜んでくれた人もいたみたいです。
よかった(ホッ)。
この日と、その翌日の苫小牧公演の2日間は来場者全員にポスターをプレゼントしました。
*5:「食べ放題で元を取ろうとするな」とか、しょうもないけど真理を突くやつ。
*6:引き出物でポスターもらったら嫌だけど。
5. 普段は観れないスペシャル編成でのライブ
僕らcolor chordはドラム、ギター、ベースボーカルの3人組のバンドなんですが、この日はTHE武田組*7のキーボード山本裕太郎くんをサポートに迎えて4人編成でライブをしました。
3人のシンプルなアンサンブルにピアノやオルガンの音が増えると、曲に彩りが増して、より艶やかに、より上品になりました。
初めて聴く人にも曲がわかりやすく、伝わりやすくなったんじゃないかとも思います。
アンコールの曲では、間奏を普段の4倍くらいの長さに延長してギターと鍵盤でソロ対決をしてもらったりして、このメンバーならでは、ライブならではの演奏も披露できました。
音が増えれば増えるほどいいってもんじゃないけど、普段と違う編成だといつもライブを観てくれている人には新鮮に聴こえて面白いかなと思います。
めちゃくちゃ良く言うと、ハナレグミのバンド編成ライブに原田郁子がキーボードで参加してたらテンション上がる感じです。
山本裕太郎くんには翌日の苫小牧公演にも参加してもらいました。
*7:道新ホールという収容人数700人のホールでワンマンライブを去年成功させ、今年も開催予定というモンスターバンド。
ライジングサンロックフェスにも2回は出てるはず。
3. 人の力を借りて、自分の範疇を超えるイベントとなった苫小牧公演

札幌公演の翌日5月14日(土)は苫小牧ELLCUBEでのレコ発。
北海道第二のホームである苫小牧ではいつもELLCUBEにお世話になっています。
拠点の札幌以外にホームがあるというのはとても心強いです。
このレコ発は、出演バンドを決めるブッキングから、何から何までをELLCUBEにお任せしました。
1. ジャンルかぶりなしのバラエティに富んだお祭りイベント
出演バンドは前日の倍の8組。
前日は出演バンドが少なかったので、こちらは敢えて出演バンドを多くすることで二日間のイベントの方向性に違いを出しました。
打ち込み・エフェクターを使う弾き語りや、シンプルなアコースティックデュオ、ラウドな4人組ロックバンドや多彩な音色を使い分ける4人組バンド、エレクトロニカなデュオや3人組シューゲイザーバンドなど、さまざまなジャンルがごちゃまぜになったイベントでした。
8組も出演して1組もかぶりがないなんていうのは、狙ってやらないとできるもんじゃないと思います。
音楽性を近づけてイベントの色を濃くするというよりかは、あえてジャンルをばらけさせてバラエティに富んだお祭りという感じです。
8組出演の長丁場となると最後の方は疲れてきたりもするんですが、それでも飽きることなく最初から最後まで聴いていられたのは、出演バンドの力量ももちろんのこと、ジャンルがバラバラだったからというのも作用していると思います。
2. 自分でブッキングをしないから出会いがある
出演バンドはほとんど知っているバンドばかりではあったんですが、初めて共演するバンドも出演していて*8、そこでバンドと知り合うこともありました。
7年ぶりくらいに共演するバンドがいたり、苫小牧でよく共演するお馴染みの面々もいたりと、共演バンドの親密度の幅も合って面白味がありました。
共演者同士の関係性については、お客さんからしたら一見関係なさそうな部分ではあるんですが、そういうバンドの関係性がイベント全体に影響を与える部分も実は大きかったりします*9。
color chordを中心に考えさせてもらっていますが、そういう意味でもバランスがよかったなと思いました。
最後のアンコールとかは身内ノリの愛のあるワイワイ感もちょっとあって、でも基本は馴れ合っていない感じでイベントが進んでいてクールでした。
*8:メンバーの1人がcolor chordのことを好きでいてくれたバンドや、こちらが一方的にずっと聴いていた先輩バンドとも初共演でした。
*9:マジで知らないバンドしか出てないと殺伐とするかギクシャクするし、マジで仲良すぎるバンドしか出てないと良くも悪くも身内ノリになりがち。
4. 企みに乗っかって楽しんじゃおう
こんな感じで二日間のイベントを行いました。
良かれと思ってやったことがハマらなかったり、狙いどおりにいかなかったりすることもあるんですが、ライブイベントはだいたい主催の「お客さんに楽しんでもらいたい!」という思いによってできています。
今回はやらなかったけど、会場をオシャレに装飾することによって特別な空間・時間を提供しようというイベントもあれば、プロジェクターを使って煽りVTRを流したりするイベントもあります。
お客さんの立場としては、もちろん自由に楽しむのが大前提なんですが、主催が用意したおもてなしを存分に楽しむ、存分に乗っかるというのがイベントを楽しむコツだとも思います*10。
もし気が向いたら、もし思い出したら、そんな主催の企みに一度乗っかってみてください。
きっとライブの新たな楽しみ方が見えてくると思います。
*10:会場装飾があれば細かく見てみたり、転換中に流れている曲に耳を傾けてみたり。