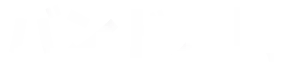バンドで練習するときに「他のパートや自分の音が聞こえない!」ということはありませんか?
よりよい環境で質の高い練習をするためにも、バンド内におけるパートそれぞれの音量はとても大切です。
それでは一体、どのように音量バランスをとればいいのでしょうか?
- バンドアンサンブルでまず知っておきたい10のこと
- 意外と知らない!?ゲイン(GAIN)とボリューム(Volume)の正しい使い方
- エレキベース初心者のための練習曲
- 【女性向け】ミックスボイス(ミドルボイス)習得に役立つ練習曲
- 夏休みに1曲マスター!ベースのレベルアップにおすすめな練習曲
- 楽器別のバンド初心者にオススメの曲
- バンド初心者にオススメの曲。簡単で盛り上がる曲
- 【2026】バンド初心者へ!ライブで盛り上がる人気バンドのおすすめ曲
- 【初心者向け】女性ボーカルバンドにオススメの曲。曲選びの参考に!【2026】
- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】
- ロック初心者のための練習曲
- カラオケで歌いやすいガールズバンドの名曲
- WANIMAの歌いやすい曲。高音が苦手な方でも挑戦しやすい曲も!
まずは主役を意識する
あなたのバンドは、どの楽器が主役にありますか?
例えば歌モノの楽曲なら、主役であるボーカルがはっきり聞こえることが大前提です。
自分のパートの音が聞こえにくいからといってそれぞれが音量を上げていくと、スタジオの中が音の洪水になってバンドアンサンブルが成り立たなくなります。
特にマイクはハウリングさせずに調整できる音量には限りがあるため、ボーカルを中心にバランスをとるのがスムーズです。
小さい部屋やスタジオなどでドラムの音が大きすぎるときは、タオルなどでミュートしたり、シンバルにガムテープを貼るなどして楽器自体の音量を下げてみてください。
役割を知る
音楽の世界には、音の3要素・音楽の3要素、この2種類で構成されています。
まず音の3要素は、
- 音の高さ
- 大きさ(強さ)
- 音色
音楽の3要素は、
- メロディ
- ハーモニー(和音)
- リズム
です。
バンドで演奏する場合、これらの要素を、それぞれのパートが意識するだけでも音量バランスを保てます。
バンドの編成が多ければ多いほどより明確な役割が必要になるでしょう。
音の位置・向き
音は空気の振動です。
音は高音域になるにつれ直進性が高くなり、低音域は拡散しやすく全体に広がる特性を持ちます。
例えば、ギターを弾いている時に自分はちょうどよくても、他のメンバーからはアンプの音が大きいということがあります。
その際はボリュームツマミだけでなく、立ち位置やアンプの向きを変えてみましょう。
自分の目線から見てスピーカーが正面に見えるポイントが音もはっきりするため、アンプを丈夫な台に載せたりアンプ自体を傾けたりするのも大変効果的です。

http://www.fender.co.jp
ボジションを見直す
楽器は音量だけではなく、押さえり叩いたりするポジションによって音の存在感が変わります。
マイクと口元・楽器の距離を近くすることで、音の明瞭度が高くなりハウリングにも強くなります。
ギターやベースではポジションによって音量だけではなく音の高さはもちろん、アタック感や音の長さも変わってきます。
ドラムは叩く強さだけでなく叩く位置によっても音量をコントロールできます。
リズムを合わせる
音量バランスがとれたら、他のパートの音をよく聴いてリズムをしっかり合わせましょう。
リズムが合っていないと音がさまざまなタイミングで発音され、ビートやフレーズのフォーカスが甘くなりバンドサウンドが濁る原因になります。
しっかりリズムを合わせることで、それだけで音がクッキリするのです。
最後に
このように、音量バランスを解決する手段は、ボリュームツマミだけではありません。
バンド内の音量バランスを改善するだけで、スタジオ練習も驚くほど充実してくるはずです。