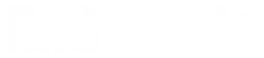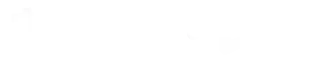知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学
新しいクラスにも慣れ始める5月。
花粉症も落ち着き、外遊びが楽しくなる季節ですよね。
こどもの日や母の日など、小学生にとって関係の深いイベントも多い5月ですが、それ以外にもさまざまな雑学があることをご存じでしょうか?
国語や英語などの授業で言葉としては聞いたことがあっても、その由来まで知っているという小学生はあまりいらっしゃらないかもしれませんね。
今回は、5月に関する聞いたことがあるであろう言葉や、イベントについての雑学を紹介します!
知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学(1〜10)
こどもの日にこいのぼりを飾る理由
知って驚く!
こどもの日にこいのぼりを飾る理由をご紹介します。
山奥にある、流れの速い滝である竜門を登り切ったこいが、りゅうになって天に上るという中国の故事『登竜門』が由来とされています。
こいは川を泳ぎながら滝を登る力強さがあり、これになぞらえて、子供たちが元気に、そして幸せに成長することを願って飾るようになったといわれていますよ。
そして今では、こいのぼりが風にたなびく様子が、子供たちの健やかな成長を祝うシンボルとして親しまれています。
こどもの日に兜を飾る理由
知らなかった!
こどもの日にカブトを飾る理由をご紹介します。
身を守るためのお守りとして飾られたのがはじまりとされています。
武士たちが戦いに行くときに、カブトをかぶっていたのは知っているでしょうか?
鎌倉から室町時代、武士の家ではこの梅雨の目前に、武具へ風を通して手入れをしていたようです。
武家がおこなっていた習慣に由来していると思うと、歴史を感じますよね。
子供の身を守って、元気に大きく育つようにという意味が込められているともいわれていますよ!
新茶が縁起ものである理由
季節によっておいしい食べ物が変わってくるように、お茶は5月が収穫のはじまるシーズンとされています。
そんな最初に摘み取られる新茶が、特別なもの、縁起がいいものとして語られる理由とはなんでしょうか。
お茶はこの時期だけではなく、年に何度も収穫の時期がやってくる生命力の強い木だといわれていて、その最初の収穫の時期である新茶は特に生命力が強いものとされています。
そのことから、生命力が強い新茶を無病息災の願いを込めた縁起物として飲んでいたという流れですね。
こどもの日が始まった時代
お休みが続くゴールデンウィークは5月の大きな楽しみのひとつ、その祝日の中でもこどもの日はおぼえやすい日だと思います。
そんなゴールデンウィークの大切な要素でもあるこどもの日は、どの時代に始まったものなのでしょうか。
日本の祝日としては1948年、昭和23年に制定されたものですが、その起源は古代の中国にあるといわれています。
もとは「端午の節句」という日で、男の子の健やかな成長を願う厄払いをおこなっていた行事ですね。
この日に飾る菖蒲も端午の節句に由来するものなので、しっかりと飾りつけて起源を感じてみるのはいかがでしょうか。
端午の節句の昔の主役
友達や家族に教えたい!
端午の節句の昔の主役をご紹介しますね。
近年では「こどもの日」として親しまれている5月5日。
もともとは、男の子の成長を祝う日である「端午の節句」ですが、江戸時代には武士の家で特に盛大に行われていました。
そんな端午の節句の主役が、昔は男の子ではなかったというのを知っていますか?
端午の節句は、もともと女性が主役の日だったそうです。
5月の最初の午の日、女性たちは「五月忌み」で心身を清め、田の神様に収穫の恵みを祈っていました。
この日、女性たちは家にこもり、しょうぶという植物を飾って祭りを盛り上げていたそうです。
しかし、鎌倉時代以降、武士社会で男の子の成長を祝う日として変わり、男の子が家を継ぐ重要性から、端午の節句は男の子の祝いに変わっていったといわれています。
こいのぼりの1番上にある吹き流しの意味
こいのぼりはこどもの日には欠かせない飾り付けのひとつ、大きな鯉が風に舞う様子は力強さとさわやかさを感じさせますよね。
そんなこいのぼりの鯉ではない部分、鯉よりも上で舞っている吹き流しにはどのような意味が込められているのでしょうか。
吹き流しがカラフルなところにも意味があり、これは陰陽五行説の自然界の要素をあらわしていて、これが子供を守ってくれるという魔よけの意味を持っています。
また神様への目印の意味もあるとされ、全体的に家や子どもを守ってほしいという願いをこの吹き流しで表現していますね。
みどりの日の由来
ゴールデンウィークの連休の中でも、憲法記念日とこどもの日に比べて、みどりの日は由来や願いがわかりくいですよね。
そんなみどりの日はどのように誕生して、どのような思いが込められた祝日なのかを考えてみましょう。
みどりの日が5月4日になったのは2007年からで、それまでは現在の昭和の日である4月29日がみどりの日とされていました。
この4月29日は昭和天皇の誕生日ということで、自然をこよなく愛する人だったということにちなんで、崩御後にその精神を受け継ぐ願いを込めてみどりの日という名前が付けられたという歴史ですね。
この由来を意識して、みどりの日は自然に目を向けてみるのもいいかもしれませんよ。