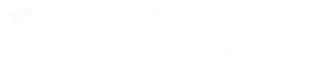【子供向け】鯉のぼりの豆知識&雑学クイズ
5月には大きな連休、ゴールデンウィークがあり大人も子供も楽しみにしている、というご家庭も多いのではないでしょうか?
そんなゴールデンウィークの最終日にある「こどもの日」には全国各地でこいのぼりが青空に大きくはためいているのを見かける機会も多いはず。
この記事ではこいのぼりに関する雑学や豆知識クイズをご紹介していきますね。
お子さん向けの問題ですが大人も知らないという雑学もたくさんあるはず。
ぜひお子さんと一緒に楽しんでみてくださいね。
【子供向け】鯉のぼりの豆知識&雑学クイズ(1〜10)
こいのぼりはいつの時代から飾られるようになったでしょうか?
- 平安時代
- 江戸時代
- 昭和時代
こたえを見る
江戸時代
こいのぼりは、もともとは武士の家庭で「端午の節句」に子供の健康と成長を祈るために飾られるようになり、その起源は江戸時代にさかのぼります。平安時代には五月人形や武者人形が飾られる風習がありましたが、こいのぼりが広く普及したのは江戸時代以降です。昭和時代に入ると、こいのぼりを飾る風習はさらに全国的に広まりました。
端午の節句にこいのぼりを飾る意味は?
- 子供の健康と成長を願う
- 悪い霊を追い払う
- 家族の絆を深める
こたえを見る
子供たちの健康と成長を願う
端午の節句にこいのぼりを飾る理由は、「子供の健康と成長を願う」という意味があります。鯉が滝を登る姿を子供の成長と健やかなたくましさに例え、家族が子供の健康と将来の成功を願って飾る習慣があります。
こいのぼりは何歳まで飾るもの?
- 子供が小学校に上がるまで
- 子供が中学生になるまで
- 家庭によりそれぞれ
こたえを見る
家庭によりそれぞれ
こいのぼりを飾るのは子どもが健やかに育つことを願い、無事に成長したことを祝うためです。なので特に飾る年齢は決まってなく、家庭や地域によって変わってきます。飾られる日数も地域によって風習があります。
こいのぼりはなぜ5月5日の象徴になっているのでしょうか
- こいのぼりが作られた日だから
- 「端午の節句」という行事のため
- 5月5日が魚の日だから
こたえを見る
「端午の節句」という行事のため
こいのぼりを飾る習慣は、端午の節句という5月5日の行事と深く関連しています。端午の節句は、古来から中国に起源を持ち、邪気を払い健康や無病息災を願うための行事とされています。日本に取り入れられてからも、この日に男の子の健康と成長を祈る風習として、こいのぼりを飾る習慣があります。
子供が女の子だけの家庭ではこいのぼりを飾ってはいけない?
- 飾ってはいけない
- 飾ってもよい
こたえを見る
飾ってもよい
こいのぼりは端午の節句、5月5日に向けて飾る風習ですが、これは子供の健やかな成長を願う行事とされています。飾ることができるかどうかに家庭の子供の性別は関係ありません。もともと男の子の節句として知られている端午の節句ですが、「子供の健康と成長を願う」という意味では、女の子がいる家庭でもこいのぼりを飾ることが全く問題ありません。近年では女の子用のピンクのこいのぼりも販売されています。
こいのぼりの上にある「ふきながし」にはどんな意味がある?
- 家族の健康と幸福を願う
- 邪気を払い、家を守る
- 豊作を願う
こたえを見る
邪気を払い、家を守る
「ふきながし」は5色の色それぞれに意味があり、家族を災いから守るため、また家の中の邪気を払うという意味が込められています。風になびかせて邪気を払い、家を守る役割をしているとされています。
黒いこいのぼり「まごい」は家族の誰に当たるでしょうか?
- お父さん
- お母さん
- おじいちゃん
こたえを見る
お父さん
こいのぼりの「まごい」は家族の象徴として最も大きな鯉のぼりで、家族のお父さんを表しています。江戸時代、こいのぼりが広まった頃は黒いまごいが1匹だけ飾られていましたが今は家族の姿を表すものになっています。