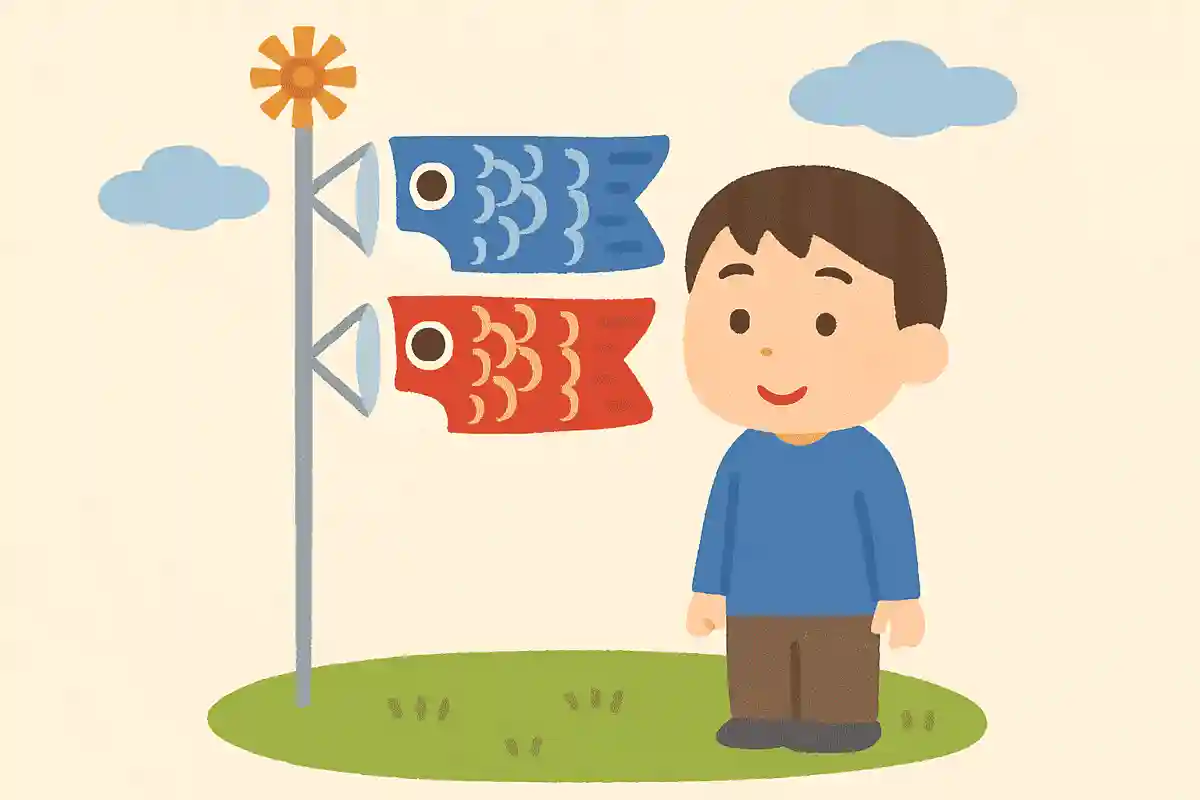【意外と知らない】鯉のぼりにまつわる雑学&豆知識
5月5日のこどもの日が近くなるとそこかしこで見かけることが増えるこいのぼり。
昔からの伝承で男の子が生まれると飾るというしきたりのところも多いですが最近では住宅事情などもあり、あまり大きなものは見かけなくなりましたが室内に飾れるものやインテリア性の高いものなどが増えましたよね。
そんなこいのぼりにまつわる雑学、豆知識をこの記事ではご紹介していきますね。
そう言われれば知らないな……というような雑学、知っておくと話のネタにもなりますよ。
お子さんがいるご家庭でもぜひこいのぼりのルーツなど、ご家族でお話してみてくださいね。
【意外と知らない】鯉のぼりにまつわる雑学&豆知識(1〜10)
こいのぼりはひな人形のように厳密に飾る期間は決まっていない
ひな人形は3月3日を過ぎても飾っていると「婚期が遅れる」と言われていますよね。
こちらは迷信であり、情操教育の一環であると言われていますが、心配で早々に片付ける方も多いのではないでしょうか。
少なくとも、ひな祭りのあと2週間以内に片付ける事が一般的です。
しかしこいのぼりには、片付けるタイミングが定められていません。
5月中旬ごろまでに片付けることが多いようですが、地域によっては6月に入っても飾られているようですよ。
男性は婚期というものがないからでしょうか……不思議ですね!
こいのぼりの先端にある回転球、矢車には魔除けのほかに神様へのアピールの意味がある
こいのぼりのさおの一番上についている矢車、何のためについているんだろう?と不思議に思った方もいるのではないでしょうか。
矢車に使われている矢羽には、幸せを射止め邪気をしりぞける意味があるのですが、実はもう一つ役割があるんです。
それは、男の子が生まれましたよ、という神様へのアピール!
矢車は回すと音が鳴るでしょう?その音が神様へのお知らせになるそうなんです。
こいのぼりにはいろいろなものが付いていますが、実はすべてにしっかり意味があるんですよね。
1964年東京オリンピック以前はこいのぼりは2色、オリンピック以降カラフルになった
日本でこいのぼりを飾るようになったのは、江戸時代と言われています。
その頃は黒いマゴイが1匹だけで飾られていましたが、明治時代に入ると赤いヒゴイと1セットで飾られるようになり、1964年に東京オリンピックが始まると五輪のマークにちなんで今のようにカラフルなこいのぼりになったそうです。
思えば有名な童謡『こいのぼり』の歌詞にはマゴイとヒゴイしか出てこないんですよね。
時代によって見た目は変化したこいのぼりですが、子供に大きく育ってほしいというのは今も昔も変わらない願いのようです。
2020年代、男の子がいる家庭でこいのぼりを出している家は3割ほど
昔は男の子がいるご家庭では、必ずと言って良いほど飾られていたこいのぼりですが、最近ではこいのぼりを飾るご家庭は約3割だそうです。
その背景には集合住宅の増加や、景観維持のためにベランダにこいのぼりを飾ることを禁止するマンションが増えたことがあるようですね。
とはいえ室内用のこいのぼりは人気があるようなので、外で見かけることは少ないけれど、家の中にはしっかり飾っているご家庭もあるでしょう。
こいのぼりは子供が元気に大きく育つ願いを込められたものなので、ぜひ飾ってほしいものですね。
日本でのこいのぼりの歴史は江戸時代、武家の出陣の時のぼり旗が由来である
現在の日本では端午の節句に、こいのぼりや五月人形を飾ったりしますよね。
しかしこいのぼりは、以前は形状の違うのぼりを飾っていたそうですよ。
飾っていたのぼりを武者のぼりといい、旗指物が由来だそうです。
旗指物は、戦国時代の武士が戦の時に、自分の存在や所属などを示すために身に付けていた旗だそうです。
端午の節句にも飾る風習もあり、庶民もマネをして飾るようになりました。
旗指物には家紋が描かれますが、庶民がマネしたものには武者が描かれており、武者のぼりとよばれました。
中国の伝説である、立身出世のシンボルである滝を上るこいも描かれることも多かったようです。
ここから、現在のようにこいだけの飾りになりました。
昔の鯉のぼりは黒がお父さん、赤が子供でお母さんのこいのぼりはなかった
こいのぼりには基本的に、黒いマゴイ、赤いヒゴイ、小さいコイの3匹がいますよね。
マゴイはお父さん、ヒゴイはお母さん、小さいコイは子供と言われていますが、昔はマゴイとヒゴイだけで、ヒゴイはお母さんではなく子供でした。
童謡『こいのぼり』の歌詞でも、マゴイはお父さん、ヒゴイは子供と紹介されていますよね。
実はこいのぼりが今のように増えてカラフルになったのは、1964年の東京オリンピックのあとです。
ちなみに江戸時代は、マゴイの1匹だけで飾られていましたよ。
こいのぼりの上に飾られる吹き流し、こいのぼりと七夕では意味が違う
こいのぼりと一緒に飾る吹き流し、七夕飾りとして定番の吹き流し、どちらも同じ吹き流しですが、実は意味が違うのをご存じでしたか?
こいのぼりの5色の吹き流しは春夏秋冬と土用、または木、火、土、金、水の5つの要素を表し、邪気を払ってくれると言われています。
そして七夕飾りの吹き流しの方は織姫の織り糸を表しており、裁縫や織物の上達を願って飾られるそうです。
同じ吹き流しなのにまったく意味も飾る理由も違っておもしろいですね。