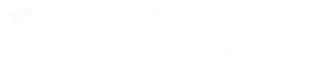知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学
新しいクラスにも慣れ始める5月。
花粉症も落ち着き、外遊びが楽しくなる季節ですよね。
こどもの日や母の日など、小学生にとって関係の深いイベントも多い5月ですが、それ以外にもさまざまな雑学があることをご存じでしょうか?
国語や英語などの授業で言葉としては聞いたことがあっても、その由来まで知っているという小学生はあまりいらっしゃらないかもしれませんね。
今回は、5月に関する聞いたことがあるであろう言葉や、イベントについての雑学を紹介します!
- 【高齢者向け】5月にまつわる雑学をご紹介!
- 【小学生向け】3月にまつわる雑学まとめ
- 【子供向け】鯉のぼりの豆知識&雑学クイズ
- 【簡単】小学生が解ける!知恵を育むクイズ集
- 雨が好きになる!梅雨に関する子供向けの雑学&豆知識クイズ
- 【小学生向け】母の日に関するなるほどなクイズ
- 【小学生向け】4月にまつわる雑学まとめ
- 【子供向け】6月に関する雑学&豆知識クイズ
- 【子供向け】11月の雑学クイズ&豆知識問題。楽しく知識を深めよう!
- 【常識&雑学】小学生向け知識になるマルバツクイズ
- 【子供向け】12月の雑学クイズ&豆知識問題!行事や季節のことを学べる!
- 意外に知らないことも多い?5月に関する雑学を知れるクイズ!
- 母の日の雑学まとめ。起源や海外の風習も紹介
知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学(21〜30)
5月5日の「こどもの日」も母に感謝する日である
母親に感謝を伝える日といえば母の日だけだと思いがちですが、実はこどもの日も母親への感謝を伝える記念日です。
国民の祝日に関する法律によると、こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と書かれています。
このことからもこどもの日は、子どもの健やかな成長を願うとともに、産んだ母親にも感謝する日だということが見えますよね。
自分が子供として健康に生きられているのは誰のおかげなのかなど、愛情を考えるきっかけにもなりそうですね。
イタリアでは母の日の収益の一部ががん研究に役立てられている
母の日をどのようにお祝いするのかは国によってさまざまで、その方法によっては思いの強さも感じられますよね。
そんな方法の違いの中でもイタリアの母の日に注目、母だけではない多くの人々への愛情が伝わってくるような内容です。
イタリアでは、カーネーションではなくアザレアの鉢植えが販売されていて、そのアザレアが販売されるイベントでは、収益の一部ががんの研究に使われています。
病気の人に役だてたいという思いだけでなく、母が病気にならないようにという願いも感じられるようなお祝いの形ですね。
知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学(31〜40)
ノルウェーは世界で1番母の日を迎えるのが早い
日本の母の日は5月の第2日曜ですが、国によってはこれとは違う時期に母の日のお祝いが行われている場合もあります。
そんな時期が違う母の日の中でも、世界で母の日が最初にやってくるノルウェーの文化に注目してみるのはいかがでしょうか。
ノルウェーの母の日は2月の第2日曜で、日本でのカーネーションのような、特定の花をプレゼントする文化ではないそうです。
それぞれが考えるプレゼントで感謝を伝えるという点からも、それぞれの思いの強さが感じられますね。
母の日の発祥の国はアメリカ
日本でも定着して世界中に広がっている母の日は、時期ややり方が違ったとしても世界で共通の行事だという印象ですよね。
そんな世界中で親しまれている母の日は、アメリカで生まれて広がっていった文化だといわれています。
1907年にアンナ・ジャービスさんが亡くなった母の追悼会を開催、生前に好きだった白いカーネーションを参列者に配ったというできごとが母の日のはじまりです。
ここから当時のウィルソン大統領が、5月の第2日曜日を母の日として定め、国民の休日に制定、徐々に世界に広がっていきました。
「立夏」とは
春のはじまりの立春、秋のはじまりの立秋は、あたたかさと寒さの境目という意味でよく聞く言葉かと思います。
そんな季節のはじまりは他の季節も同様で、立夏という言葉も聞く機会は少なくてもたしかに存在する言葉です。
時期としては春分と夏至の真ん中あたり、5月の5日ごろがこの立夏にあたるといわれていますね。
二十四節気という季節を表す言葉のひとつなので、この立夏の知識をきっかけにして他の言葉にも興味を広げてみるのもいいかもしれませんよ。
そら豆を「空豆」や「蚕豆」と書く理由
そら豆は初夏に食べごろをむかえる豆で、その鮮やかなみためと粒の大きさも魅力ですよね。
そんなそら豆は漢字だけで書くときには「空豆」や「蚕豆」と表記されます。
その漢字に込められた意味とはどのようなものなのでしょうか。
空豆は植物としての成長の姿に由来するもので、さやが空に向かって伸びていくような独特な成長の形から空の字があてられました。
そして蚕豆はさやの見た目や食べる時期に由来するものと言われ、さやが蚕のまゆに形が似ていること、食べごろと蚕を飼う時期が近いことなどから、蚕の字を当ててそらまめと読ませるようになったといわれています。
どちらもそらまめと読むという部分はややこしくも思えますが、それぞれの由来がそら豆を深く知るきっかけにもなりそうですね。
博多どんたくの「どんたく」とは
博多どんたくは5月の3日と4日に福岡県でおこなわれるお祭りで、松ばやしという行事が起源だといわれています。
「福岡市民の祭り」という名称も持つほどに住民から親しまれるお祭りの「どんたく」にはどのような意味が込められているのでしょうか。
「博多どんたく」と呼ばれるようになったのは明治12年に再開してからのことで、オランダ語の「Zondag」、休日が語源だといわれています。
意味としてはシンプルなものではありますが、みんなで楽しもうという強い思いが感じられますよね。