AI レビュー検索
福沢諭吉 の検索結果(1〜10)
人生は芝居のごとし、上手な役者が乞食になることもあれば、大根役者が殿様になることもある。とかく、あまり人生を重く見ず、捨て身になって何事も一心になすべし。福沢諭吉

福沢諭吉(1835年-1901年)は、著述家、啓蒙思想家、教育者で、慶應義塾の創設者でもあります。
社会では、なぜこんな人がこんな高い地位にいるの?
逆に、なんでこんな優秀な人が世間に認められていないの?
と思うことはたくさんあります。
そのなぜは解明できませんが、福沢諭吉先生もそんな同じ思いをしていて、そんな事実にも負けず、自分のやるべきことをちゃんとしていたらよいのだ、と教えてくれているようです。
天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず福沢諭吉
慶應義塾を創設したりと、教育家として活躍した福澤諭吉、一万円紙幣の肖像画に起用されたことでも知られていますね。
そんな現在の教育にもつながっている偉大なる教育者が残した、平等についての考え方をしめした名言です。
人は生まれたときには平等ということにくわえ、そこからの環境や教育で差が生まれているのだということも伝えています。
差別や上下を感じる人ほど、それを解消する方法を探していくことが大切という、学問のきっかけにもなりそうな言葉ですね。
進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。福沢諭吉

幕末から明治の日本で教育者として活躍した福澤諭吉は、一万円札の肖像画に起用されたことも有名で、慶應義塾の創設者としても知られてますね。
そんな日本の教育のために尽力した人物が残した、進む人と立ち止まる人についてを語った言葉です。
進み続けるためには、退かないという前向きな姿勢がなによりも大切で、その意思を持ち続けた人こそが目標にたどり着けるのだと伝えています。
自分がかかげた理想や、自分のことをしっかりと信じることが大切なのだという呼びかけにも感じられるような言葉ですね。
今日も生涯の一日なり。福沢諭吉

福沢諭吉さんは日本の明治時代に活躍した思想家、教育者であり福沢諭吉の代表作である『学問のすすめ』は学びの重要性を日本国民に教えてくれました。
西洋に渡り学びを深め日本に広めたことも有名ですよね。
今日も生涯の1日なりという名言があります。
人生は有限で日々の積み重ねで人生は作られていきます。
過去や未来のことを思うのも大切ですが、今に集中して生きることも大切だということを伝えてくれてる言葉です。
忙しい日々が続いた日こそ今の自分に集中することの大切さに気づかせてくれる言葉ですね。
一日生きることは、一歩進むことでありたい。湯川秀樹

湯川秀樹(1907年ー1981年)は、日本人初のノーベル賞受賞者(物理学賞)です。
研究生活では全く成果が出ない時期も経験し、他の教授からさらに勉学に努めるよう注意されたこともあるそうです。
そんな日々からあげられた偉大な業績は、まさに日々の努力の積み重ねだったのでしょう。
毎日の研究からは目にみえる成果がみえなくても、毎日ほんの少しでも前進していたい、という願いや、そこからしか大きな成功をつかむ道はないのだと示してくれている貴重な言葉ですね。
人生はむつかしく解釈するから分からなくなる。武者小路実篤
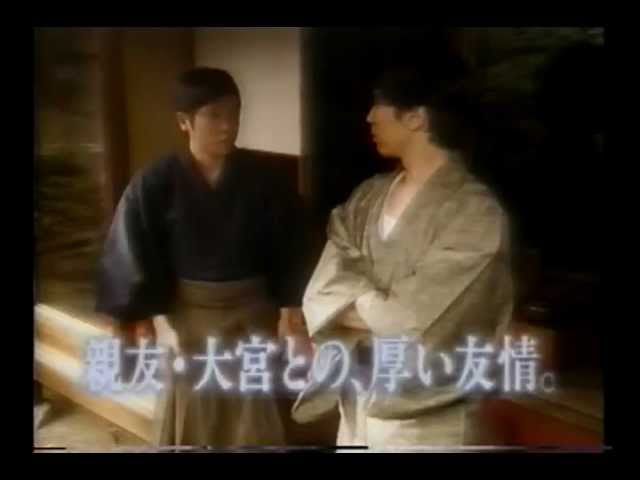
武者小路実篤(1885年-1976年)は、小説家・詩人・劇作家・画家で、代表作に、「友情」、「愛と死」などがあります。
生きていれば、日々自分にふりかかってくることを、なぜこんなふうになってしまったのだろうと考え込んだり、そのせいでなかなか前にすすめないことがあります。
でもこの言葉は、そんなに難しく考えるからわからなくなるのだから、もう少しシンプルに、気楽にかまえて生きていけば?
と元気づけてくれるように感じます。
あきらめなければ必ず道はある。必ず。豊田佐吉

豊田佐吉(1867年-1930年)は、日本の発明家、実業家で、トヨタグループの創始者です。
18歳のころ、「教育も金もない自分は、発明で社会に役立とう」と決心して、手近な手機織機の改良を始め、その後、多くの偉大な業績をあげました。
試行錯誤の毎日で、変人扱いされても、けっしてあきらめなかったことが、その後に多くの大輪の花を咲かせることにつながりました。
それなら自分も!
と奮い立たせてくれる言葉です。



