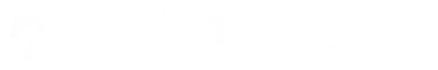心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ
8月は花火やお盆、海水浴と、さまざまなイベントが盛りだくさんですよね!
でも、暑すぎて外に出る気になれない〜という方も多いのではないでしょうか?
そんなときは、涼しいお部屋でちょっと新しい知識を勉強してみませんか?
この記事では、8月に関する雑学&豆知識を紹介します。
8月の行事や旬の味覚に関することをはじめ、さまざまな視点から暑い8月がちょっとおもしろくなるトピックスを集めてみました。
ぜひチェックして、8月をまた違った形で楽しんでみてくださいね!
心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ(1〜10)
そうめんの発祥地は奈良県
ツルツルとのどごしの良いそうめんは、暑い夏に食べる機会が多いですよね。
実は、そうめんの発祥の地は奈良県なんです。
1200年以上も前から、奈良県三輪山麓にある大神神社周辺でそうめんが作られていたという記録が残っているんですよ。
病気や飢餓に苦しむ人のために祈願したことで、神から啓示を受けて生み出されたといわれています。
豊かな自然と清らかな水が育んだそうめんは、長い年月をかけて全国に広がり、日本の夏に涼しさをもたらす食べものです。
奈良県で生まれた三輪素麺のほかにも、ご当地のそうめんのルーツをたどってみるのも楽しそうですね。
サンゴは夏バテすると白くなる
ピンクや赤などのカラフルな色素を持つサンゴが白くなる理由をご存知ですか?
なんと、サンゴは夏バテすると「白化」と呼ばれる現象で白くなるんです。
サンゴは、共生する褐虫藻(かっちゅうそう)が光合成することで色素を持ちます。
海水温が上昇することで、サンゴにストレスが加わると褐虫藻が体内から抜け出して白化してしまうんです。
白化してしまったサンゴは栄養不足で弱ってしまうため、26〜28度の海水温の海で生息する必要があります。
地球温暖化により海水温が上昇していることや海の汚染が影響しているため、サンゴの白化を止める方法や対策は世界中で議論されています。
盆踊りは平安時代から始まった
全国各地の夏祭りで欠かせないイベントの一つとなっている「盆踊り」。
お盆に現世に帰ってきたご先祖や死者の霊を送り出すための舞である盆踊りは、平安時代に始まったとされています。
当時、とある僧侶が念仏をおぼえてもらうために踊りながら唱えることを思いつきました。
これが「念仏踊り」「踊り念仏」として広まり、お盆の行事と結びついて「盆踊り」として親しまれるようになっていったのです。
ただし、盆踊りの起源には諸説あるため、このエピソードもそのなかの一つにすぎません。
ご興味のある方は他の説も含め、調べてみてはいかがでしょうか?
心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ(11〜20)
かき氷は平安時代から食べられていた
暑い夏に食べたくなるかき氷。
キンキンに冷えた氷に、甘いシロップをかけて食べる定番スイーツですが、かき氷のルーツは平安時代までさかのぼります。
平安時代の貴族たちは、冬に切り出した氷を氷室に蓄え、夏にそれを削って食べていたそうです。
当時のかき氷は、現在のようにシロップをかけるのではなく、甘葛(あまかずら)という植物から作った甘い液をかけて食べていたんです。
かき氷の歴史を知ると、夏の風物詩であるかき氷が、より一層美味しく感じられるのではないでしょうか。
花火の際に言われる「たまや」や「かぎや」は花火を作っていた店の名前
夏の夜空を彩る花火大会。
見上げる度に聞こえてくる「たまや」「かぎや」という掛け声を聞いたことはありますか?
このフレーズは、単なる応援言葉ではなく深い歴史が隠されているんです。
実は、「たまや」と「かぎや」は江戸時代、花火を作っていたお店の名前に由来しています。
花火屋の鍵屋と、のれん分けの玉屋の2軒の花火を打ち上げて、技術や美しさで優れていると感じた方の花火の屋号を掛け声にすることが文化として親しまれていました。
江戸時代に活躍した花火師の屋号を夜空に向かってさけぶことが現在まで続く日本の伝統的な風習の一つです。
スペインでは毎年8月の最後の水曜日に「トマト祭り」が開催される
真っ赤なトマトを人びとが投げ合うお祭りをご存じですか?
スペインのバレンシア州にある街、ブニョールでは毎年8月の最終水曜日にラ・トマティーナと呼ばれるユニークなお祭りが開催されています。
世界中から街の人口よりも多い人が集まって熟したトマトを投げる様子が印象的。
街全体がトマトで覆われて、まるで赤い海のように染まります。
トマトをつぶしてから投げることや、人の服を破ってはいけないなどのルールが定められており、毎年数千人が集まるイベントとして楽しまれている世界の行事です。
五山送り火は台風でも開催される
京都の夏の風物詩として行われる五山送り火。
毎年8月16日に開催されており、お盆に迎えた先祖をふたたび送る意味が込められています。
京都の四大行事の一つであり、大雨や台風などの悪天候の年も含めて50年以上中止になったことがありません。
台風が来ても先祖の霊をお送りする行事は決行されます。
ただし、河川氾濫の危険性がある場合は鴨川の河川敷に立ち入ることを禁止するなど、安全性を確保した上で実施された年もありました。
夜空を彩るかがり火の大きな文字が五山で点火される様子が人びとから親しまれている日本の伝統行事です。